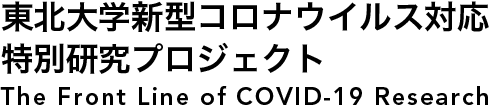PEOPLE
インタビュー
今こそ総合知を ― COVID-19は転換点
押谷仁教授は、国のCOVID-19対策に従事する傍ら、東北大学新型コロナウイルス対応特別研究拠点プロジェクトの一環として、「感染症共生システムデザイン 学際研究重点拠点SDGS-ID」を立ち上げています。その思いも含めて、前回に続き、押谷さんのこの2年間の活動を振り返っていただきました。
(2022年3月10日にオンラインで収録)
瀬名: 先日、Yahoo!ニュースのコメント欄に、ロシアのウクライナ侵略関連のニュースがトップに出るようになったことで、コロナの新規感染者数がトップに出なくなって気持ちが落ち着くようになったという意見が出ていました。これを見て、いろいろ考えさせられました。その気持ちはわかるのだけれども、なんというか、人々の世界観の限界を突き付けられた思いがしました。自分の目に見える新型コロナのニュースは怖い、あるいはこれまで怖かったけれど、ウクライナはまだその人にとって遠い存在で、だからあまり感情が動くこともない。他人事だからこそ落ち着けるわけですが、それでは未来はやはり変わらない。ぼくらの「共感」という感情にはそういう両側面があって、人間には限界があるのかと。
前回も話題に出た『分水嶺』(注1)は、押谷先生が東京から仙台に帰り、東北大学医学部近くにある「疱瘡神」の石碑(注2) に手を合わせるという印象的なシーンから始まっています。
押谷: それは2020年の年末の話ですね。ぼくにとっては、2020年4月の初め、桜が満開の仙台に帰ったときに見た光景のほうが強く印象に残っています。西公園に行ったら、金子みすゞの「明るい方へ 明るい方へ」という詩の一節を引用した看板が立っていました。そしてその下に、「みんなのために― がんばるでもなく、たたかうでもなく、予防対策を徹底し、ルールを守って明るい方へ!」と書いてあったのです。それを見て以来、このウイルスと「戦う」という言葉は使わないことにしました。

2020年4月、仙台市西公園に立てられた看板(撮影 押谷仁)
瀬名: たしかに戦うというと、戦争のイメージで考えてしまいますね。最初はほしがりません勝つまではという感じで総力戦でやるぞと挑むのだけれど、だんだん消耗してきてどこを目指したらいいかわからなくなるから、戦争のメタファーはやめたほうがいいですね。しかしそんなことを言うと、SNSのコメント欄で叩かれかねない。
そういえば、東京都庁の感染症対策部門と保健所の公衆衛生医師として都の新型コロナ対策にあたっていた関なおみさんの著書『保健所の「コロナ戦記」 TOKYO2020-2021』(光文社新書、2021)に、「とにかく保健所職員の誰もが思っているのは、今は道に迷わず、ゴールが見えなくとも、まっすぐに続く一本の道を走っていきたいということだ。何本もある道を誰にも決められず、矢印もなく歩くのは、少なくとも勘弁してほしい。この道でいいの? と思いながらも、この道しかないから行くのだというあきらめにも似た信念をもって進んでいきたいのだ」(p.253)という記述があります。自分たち保健所の人間は決して道が平坦でまっすぐではないことは知っているけれども、とにかく前を目指して歩いて行くのだから、少なくともあっちの道だ、いやこっちの道だなどと迷わされることなく進みたい、ということで、ここには胸を衝かれました。確かにその通りだとは思います。
押谷: その本のことは知っています。われわれの基本的な目標は最初から変わっていません。専門家会議(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)が2020年2月24日に出した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解」がそれで、そこには「これからとるべき対策の最大の目標は、感染の拡大のスピードを抑制し、可能な限り重症者の発生と死亡数を減らすことです」とあります。それ以来、やるべきこともさほど変わっていません。クラスター対策も未だに局面によっては重要で有効であると思っているし、そこはぶれていません。緊急事態宣言を出す基準や重点措置のあり方に関する考えは変わるけれど、現場の戦略は大きくは変わっていないのです。
メディアへの不信
瀬名: ただ、その思いは、いまも保健所の方々には充分に伝わっていない、あるいは国民に伝わっていない、ということなのでしょうか……。押谷先生自身、その見解を出した以降の心境の変化のほうはどうだったのですか。
押谷: 瀬名さんとNHK BS1スペシャル(注3)で対談した3月11日くらいから、これはまずいことになりそうだと思っていました。あの朝、兵庫県でよくわからないクラスターが出ていたので。その頃から強い危機感をもつようになりました。
イタリアの窮状はわかっていて、スペインがひどくなりそうだということもわかっていました。これを止める術があるのか。3月中旬までに感染者数はイタリアが3万5000人、スペインが1万3000人、フランスが9000人、ドイツが1万2000人で、どんどん増えていた。同じようなことが日本で起こることに危機感をもっていたのです。そうならないようにするにはどうすればいいのか、その時点ではわかっていませんでした。イギリスからは、いったん抑えても再流行するというような予測が出ていました。抑えてもしょうがないのか。ワクチンがない以上、みんなが自然感染するまで待つしかないのか。そういう危惧がありました。東京では大規模な院内感染も起こっていた。武漢やヨーロッパ、ニューヨークのような医療崩壊が心配でした。
最初に、総合放送のNHKスぺシャル(注4)に出た3月の20日前後から、これは確実に大きな流行が起こると思うようになっていました。ただし北海道を含む最初の流行を制御することは、うまくいきそうな気がしていました。
瀬名: それはなぜですか。
押谷: あちこちでクラスターが起きたけど、何とか抑えられていたので、15日くらいまでは手ごたえを感じていて、この波は抑えられるかもしれないと思っていたからです。そして実際、武漢株は3月の終わりまでに抑えられました。一般の人たちも、日本はうまくいっていると思っていたし、当時の安倍晋三首相も3月14日(日)の会見で、わりと楽観的な発言をしていました。
ところが15日前後から、輸入例が首都圏を中心にあちこち山のように降ってきました。まるで絨毯爆撃のようでした。中国からの輸入例は13例くらいだったのに対し、それ以後、それ以外の国から300例以上も見つかりました。確認されているのはごく一部なので、実際にはもっと多いはずだと思います。その時点で、確実に国内でも流行が起こると思ったのです。
専門家会議の脇田座長が、検疫を強化しないと感染が拡大するという要望書を厚労省に出したのが3月17日。19日には専門家会議が状況の分析を行い、「クラスター(集団)の早期発見・早期対応」「患者の早期診断・重症者への集中治療の充実と医療提供体制の確保」「市民の行動変容」という基本戦略の3本柱をさらに維持すると同時に必要に応じて強化し、速やかに実施しなければならないと提言しました。しかし、検疫強化は4月になるまで実施されなかったことで、4月の第一波が起こったのです。
瀬名: 3月24日にオリパラ延期が決まり、26日に改正特措法に基づく対策会議の初会合が開かれ、志村けんさんが29日に亡くなったという報道が30日にあり、4月7日に緊急事態宣言発令という流れでしたね。
押谷: ええ、その頃わかっていたのは、西浦さんのデータから、多くの感染者は誰にも感染させないのに一部の感染者が多くの人に感染させることで、感染が広がるという仕組みでした。そこからどうやったら感染を食い止められるのかを考えていた。そういう状態でした。
瀬名: そういえば、その頃に拝見した押谷先生の講演スライドで、一部の感染者がたくさんの人に感染を広げるのがこのウイルスの特徴だということを強調されていましたね。そこがインフルエンザとの違いだと。
押谷: 3月30日くらいに、公衆衛生学会のセミナーでそういう話をしました。それ以前には、対応策がわかっていなかったので、このままいくと日本でも1カ月2カ月のあいだに何万人もの人が死亡する事態が起こりうると思っていました。アメリカでは、その第一波で、2020年5月までに10万人が死亡しています。イギリス、イタリア、フランスでも2~3万人が死亡しています。
瀬名: とにかく、人流、3密を止めようと、国民の行動変容を訴えていらっしゃいましたね。そのときはどういう気持ちだったのですか。

押谷 仁 教授
押谷: ぼくらが変えようとしていたわけではなく、政府がやるべきことでした。治療法もわかっていなかったあの時点では、とにかく感染機会を抑えるしかなかった。当時の第一波の致死率は5%を超えていました。2月13日から5月30日まで、感染者数はそれほど多くなかったのに、891人が亡くなっています。感染機会を抑えるには、人と人の接触を減らすしかなかったのです。
2011年の東日本大震災の直後、仙台では2月の終わりくらいから始まっていた季節性インフルエンザH3N2の流行がパタッと消えました。人流が途絶えたからです。じつは2009年の新型インフルエンザH1N1の勢いが2010年の年末になってもまだ残っていて、12月から始まった流行が翌年の2月の終わりくらいに季節性インフルエンザH3N2の流行と置き換わっていたのです。それが、震災の被害は悲惨でしたが、インフルエンザの流行のほうはパタリと消えました。あれくらいに人流をいったん止めないと、COVID-19も止まらないと考えていたのです。
しかしぼくは、8割外出抑制は行き過ぎで、危険な接触さえやめればいいと思っていました。公園まで閉鎖する必要はなかった。
瀬名: 西浦先生と激論になったと『分水嶺』で書かれていますが、そのことでだったのですか。
押谷: 西浦さんともめたのは、42万人の件でした。その発表をすることは事前には知らなかった。あの発表を知ったのは、新橋のオーロラビジョンで見たときが初めてでした。
それは荒唐無稽な数字ではありません。何もしなければそれくらい死んでもおかしくない。実際、アメリカではすでに95万人くらい、イギリスでは16万人以上死亡しています。イギリスの率を日本の人口に換算すると30万人くらい、アメリカの率だと36万人くらいになる。イギリスもアメリカも全く対策をしてこなかったわけではなく、かなりの程度の対策を講じてもそれくらい死亡している。そういった危険なウイルスなのだということが一般の人になかなか伝わらないことが、あのときも今も、大きなフラストレーションの元となっています。
瀬名: つまり、推定値としては正しいけれど、伝え方が悪かったということですか。
押谷: あのタイミングでそれを言ってはダメだと思ったのです。4月15日の西浦さんの記者会見の時点では、感染者数の減少傾向は明らかでした。緊急事態宣言を出した4月7日でも、感染者数は減少傾向にあった。その前、花見の人出で感染が増えましたが、志村けんさんも亡くなるということもあり、緊急事態宣言前に自発的な行動変容が起こっていた結果だと思います。なので、この第一波では死亡者数を1000人以下に抑えるという目標でやっていました。発表のタイミングとコミュニケーションの取り方がまずかった。そのことは、彼にも何度か話しました。
瀬名: コミュニケーションということでいうと、サイエンスコミュニケーションの専門家として東京大学医科学研究所の武藤香織さんが専門家会議のメンバーに入っていました。コミュニケーションの専門家が誰もいないから迷走しているのかと思っていたのですが、感染症の専門家ではないけれど、武藤さんがリスクコミュニケーションの専門家として呼ばれていました。ならばもっとうまくできたのではないかと思うのですが。
押谷: 公表する文書の文面など、武藤さんがかなり気を使って修正していました。しかし、それを伝える段階でさまざまな課題があったということだと思います。
2009年の新型インフルエンザの総括会議の報告書でも、リスクコミュニケーションの重要さは指摘されていました。あのときもリスクコミュニケーションがうまくいかなかったことが問題だった。しかしその後もそれは解決しなかった。国立感染症研究所にも厚労省にもリスクコミュニケーションの専門家はいないし、内閣官房にもいません。そこが日本の構造的な弱さの1つだと思います。
瀬名: テレビのワイドショーなどでも、いろいろな人が勝手な発言を繰り返してきました。押谷先生はああいうテレビはご覧になっていましたか。
押谷: いや、Nスぺの問題もあり、最近はテレビはいっさい見ていません。
瀬名: それがきっかけで、メディアや会見に出なくなったのですか。
押谷: それ以外にもいろいろな理由がありました。2020年5月29日の会見は、体調はよくなかったのですが前半だけ出ました。緊急事態宣言は解除されたけれど、東京の感染連鎖が収まっていなかったので、感染者数が増加に転じることが見えていた。そのあたりのことはぼくじゃなきゃ説明できないからと、専門家会議副座長だった尾身先生から言われ、無理を押して出ました。しかしぼくが1時間で退席した後、専門家会議の議事録はなぜ公表されないのだと、記者たちの吊し上げみたいなことが始まりました。結局、ぼくらが一生懸命説明したことは、ほとんど報道されませんでした。
そういうことから得た教訓は、こんなことにエネルギーを使ってはいけないということでした。メディアは、短期的なことにしか興味がない。それまでもそういった視点でしか報道していなかった。2月の初め、感染は国内で確実に広がるということを何度もメディアに伝えたのに、報道は《ダイヤモンド・プリンセス号》一色だった。3月20日を過ぎると東京の病院の院内感染の報道しかしなくなった。目の前にある短期的なことにしか目が向いていない取材に付き合うのはエネルギーの無駄だと思うようになりました。重要なのは長期的にどうするかという視点であって、重点措置がまもなく切れるといったことではない。あと1年、2年、このウイルスの被害をどうやって最小限に抑えていくかを考えなくてはいかないのに、メディアの焦点は目先のことばかり。
瀬名: 当時の記者会見ライヴの映像があるので、ちょっと観直してみましょう。緊急事態宣言が5月25日に解除されて数日後、〝比較的感染状況が落ち着いた〟という時期でした。専門家会議の座長の脇田隆字先生、副座長の尾身茂先生、そして専門家会議メンバーの押谷先生と、クラスター班の西浦先生の4名が登壇されて、専門家会議メンバーの鈴木基先生も脇に控えていらっしゃいました。改めてうかがいます。この5月29日夜の会見で押谷先生が伝えようとしたことは何だったのでしょうか。

瀬名秀明さん
押谷: それまでの取り組みや対策と、緊急事態宣言の効果など、その時点での評価を話したと思います。しかしメディアは反省会モードで、議事録問題の質問ばかりしか出なかったし、それ以外は記事になりませんでした。
瀬名: 尾身先生のプレゼン冒頭で、「今日の一番のテーマは、これまでの取り組みや対策、緊急事態宣言について、感染状況が落ち着いている今だからこそ、この時点での評価をする」ことだ、それが「われわれ専門家の責任だ」「私どもの務めだ」と、はっきり述べられています。改めて視聴すると多くの学びがありますね。その後に必要となったことは、確かにこの会見に集約されていたように思えます。
初期の各国の感染者数を見ると、日本とヨーロッパでは明らかな違いがある。ドイツやイタリアでは2月下旬や3月上旬に一気に感染拡大しているのに対して、日本はもっと前からごく少数の感染者が出ていたものの、大きな波とはならなかった。とくに中国由来と思われる最初期の株は抑制できていた。それは保健所やクラスター班の解析によって、かなり早い時期から新型コロナの特徴を炙り出すことができたからだ、ということですね。
まずこの新型コロナは、感染した人が必ずしもみんな一様に他の接触者へ感染拡大させるわけではない。5人のうち4人は、たぶん他者へ感染させない。だが残りの一人が多くの人に感染させてしまうので、それでクラスター(集団感染)が発生してしまうという事実。これを日本が各国に先駆けて見つけ出した。それでインフルエンザやエボラとは異なるそうした感染伝播の特徴があるならば、これまで常識として行われてきて、しかも今回の初期のころ諸外国でも行われてきたような、感染者ゼロを目指す「前向き(プロスペクティヴ)接触者調査」ばかりに力を注いでいると、そこから発見できる感染者数も少ないし、保健所も疲弊してしまう。だから日本では前向き調査に加えて、「さかのぼり(レトロスペクティヴ)接触者調査」も行った。それが「3密」プラスアルファ、すなわち声を出すとかみんなで歌うといったシーンへの注意喚起、という概念の発見へとつながっていった。この二つの概念を見つけ出して、国民に注意喚起できたことが日本のクラスター対策のいちばん重要な点だった、ということで、確かにこれはいまでも通用する、変わることのない、基本の考え方です。
そして4月上旬から中旬の感染者拡大が見られた時期に、検査が必要な人に対してPCR検査等が迅速に行えなかったと振り返り、今後の方向性として、①抗原検査やPCR検査と言ったツールをそれぞれの場で適切に使い分けて迅速な検査体制を敷く、②研究者がこれから頑張って、患者をより確実に補足できるよう、前駆症状や初期症状の解明や、重症化マーカーの研究・開発を急いで、より早期の医療の介入を実現する、③せっかく保健所がいろいろ情報を取っても、それが有効に活用できていない現状を踏まえて、迅速に研究を企画し、散逸するデータをまとめ、調整する。つまり指揮者がオーケストレーションするような、感染症研究の体制を整備して、次なる流行時に機動的にさまざまな研究ができるようにしておくべきだ、と提言されています。「検査体制」「医療提供体制」「感染予防対策」の強化と、「治療法・治療薬の確立、開発促進」へ向けての総力結集、ですね。国と地方自治体で疫学情報を共有するルールを明確化しよう、感染症対策を担う人材をもっと養成しよう、という展望まで語られています。
2時間半の会見のうち、押谷先生が会見に臨まれたのは前半の1時間半でした。記者からの「追跡できない市中感染が増えてきたら、保健所とのマンパワーとの兼ね合いで、クラスター対策にはいったいどこまで効果があるのか」といった質問に対して、押谷先生が次のように答えていらっしゃるのが胸に沁みます。
「クラスター対策という言葉が独り歩きして、われわれがクラスターを潰すこと〝だけ〟をしているんじゃないかと誤解されている面がある。だが〝さかのぼり〟調査や、諸外国に比べてたくさんのクラスターを見つけることで、クラスターに共通する特徴を見つけることができた。それが3密とプラスアルファだ。それがわかってきたことによって、みなさんに、そういうことが起きる環境をなるべく避けてくださいというメッセージを効果的に送ることができた。これが諸外国ではほとんどできていない」
「今回のウイルスは感染経路が見えにくい特徴があるので、まったく別の場所から感染者が発見されることはむしろ想定内」
「だがクラスター対策をしていったことで、そうした孤発例の意味づけができたことが大きい。孤発例がたくさん出るということは、その地域内で裏側にクラスターがきっとあることがわかったから、積極的な感染対策を見つけることができる。だから感染者がたくさんになっても、われわれのクラスター対策が破綻するということではない。そういう状況になってもできるだけクラスターの発生を抑える」。そうすることで国民に注意を喚起できるのだ、と。
そして、なぜ日本ではそういう〝さかのぼり〟調査が最初からできていたのか、という点について、押谷先生は「日本ではまだ結核があって、保健所が以前からそうした調査をしていたこともあるのではないか」と日本ならではの疫学文化の歴史にも言及なさっている。
こうしたメッセージが発せられていたのに、いつの間にかぼくら国民はその前提、以前から変わらない一本の道を忘れてしまって、「専門家会議や分科会が頑固にゼロコロナを目指していて、それが経済を破綻させているんだ」という誤解、擦れ違いにとらわれていってしまった。そのように思います。こうして振り返ると、とても難しい道だったのだなと、改めて感じます。
切り札の切りすぎ
瀬名: 第一波が6月に収束し、6月24日に専門家会議が廃止され、分科会(新型コロナウイルス感染症対策分科会)が設けられました。そこには経済系の人も入っています。
押谷: そもそも専門家会議の立ち位置が曖昧だったのです。その原因は特措法に起因するもので、特措法が発令されると、対策の主体が厚労省から内閣官房に移るということによるものだと考えられます。
《ダイヤモンド・プリンセス号》の頃は、アドバイザリーボード(新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード)でした。それが厚労省所管の専門家会議になりました。特措法のあたりから内閣官房が仕切るようになったのですが、会議の場所は厚労省だったため、位置づけが不明瞭でした。その整理がなかった。長期にわたる可能性もあり、公衆衛生の専門家だけで決められる問題でなくなってきていたので、経済の人たちも入ったのは自然な流れでした。
瀬名: 2020年7月から第二波が起こる中で、さまざまな問題が出てきました。Go To トラベル事業をどうするかなど、経済の問題も議論されるようになり、さまざまな学者や評論家がテレビで発言するようになりました。分科会の中で、公衆衛生の専門家と経済の人たちとはどういう議論をしていたのですか。
押谷: 2時間くらいの会議なので、発言の機会は1回、多くても2回。3、4分話せればいい中で、きちんとした議論にはなりません。なので、専門家会議の時代から、武藤香織さんのところとかでほぼ毎週日曜日に自主勉強会をやっていました。そこには経済の専門家も入っています。そこで議論はしているのですが、歩み寄れないところももちろんあります。その後の緊急事態宣言のときなどは、経済の人たちのほうが前のめり気味のこともありました。経済の人たちが、対策するなと言っているわけでは必ずしもありません。
瀬名: 2021年4月25日、4都道府県に3回目の緊急事態宣言。4回目は7月12日。2021年の年末年始あたりが第三波、5月6月あたりが第四波。少し減ったところでオリンピック、デルタ株で第五波。そのあたりの1年間の迷走ぶりをどう振り返りますか。2020年5月29日の会見では、今後起ち上がる感染者情報把握・管理支援システムのHER-SYS(ハーシス)や、接触確認アプリのCOCOA(ココア)といったその後のICT分野への期待も語られていたわけですが、日本は結果的にこれらで完全に失敗してしまいました。
押谷: 第二波から第五波が終わるまで続いていた問題が、大都市圏で収束しないことでした。特に首都圏。首都圏に感染源が残ってしまう。第二波でも、首都圏に感染源が残ってしまった。それが2020年夏の流行につながりました。夏の流行はいったん収まったのに、東京の感染者数は百数十というところまでしか下がらなかった。それが2020年の12月から翌年の1月にかけての第三波につながりました。そこで、11月25日に西村康稔大臣と尾身先生が「勝負の3週間」と発言しましたが、勝負にならなかった3週間でした。
瀬名: 「○○の何週間」というキャッチフレーズが何度も繰り返されたせいで、みんな疲れていたせいかもしれません。
押谷: 12月に入ると忘年会シーズンになるので、今のうちに下げておかないといけないという意味だったのですが、下げられませんでした。東京都には尾身先生が何度も時短の積極的な実施を訴えたけれど、11月25日、10時までの時短要請という中途半端なことしかしませんでした。大阪は流行開始が早かったので、9時までの時短をしていたため、ある程度下がりました。しかし東京はそうはならず、12月31日に初めて感染者数が1000人を超えました。それであわてて、首都圏を中心に2回目の緊急事態宣言が出たわけです。ぼくとしては、あそこで緊急事態宣言をすべきではなかったと、あのときも今も思っています。それがきっかけで、2021年は緊急事態宣言がデフォルトみたいになってしまった。東京では1年の半分くらい、緊急事態宣言が出っぱなしになった。あの流行は、年末年始の集まりで広がった流行だったので、それが終わればそれ以上広がる理由はないはずでした。年末に50代の政治家が亡くなるなどの出来事があり、年明けには危機感が高まって行動変容が起きていたということもあります。
その直後に特措法の一部改正が行われ、蔓延防止法当重点措置ができるはずだったので、あそこでの緊急事態宣言を出さないというオプションもありました。切り札に取っておくべきだったのに、逆に緊急事態宣言慣れが起こってしまった。2020年4月7日以降の第一回緊急事態宣言のような切り札として使えるように取っておくべきでした。緊急事態宣言をしても飲食店が遅くまで営業していたり、必ずしも人流が減らないというようなことも起きてしまいました。それが、デルタ株による第五波の後半の状況でした。このまま止まらなかったらどうするんだという話になり、ロックダウンも話題になっていました。ぼくは、強制力を伴うロックダウンは日本では絶対にすべきではないと思っていたし、今も思っています。
瀬名: そういう方向への法改正は反対ということですね。
押谷: 権力者がいいように使えるような法律は、日本になじまないと思っています。今後、ほんとうに深刻な状況になって緊急事態宣言を出しても行動変容は期待できない状態になってしまったことのほうが問題だと思っています。
パンデミックは都市問題
瀬名: これからは、パンデミックは大都市から広がるのがスタンダードになるという意見があります。2009年の新型インフルエンザでは、最初の発生が神戸で、初の死亡者は沖縄でした。そのせいで東京の人たちには切迫感がなかったのではないでしょうか。COVID-19では、東京、神奈川など、メディアのおひざ元である首都圏から流行が始まりました。東京での危機感がつのり、それが電波で地方に伝えられた。日本人は、首都がやられないと危機感を醸成しない傾向があるのかもしれない。
それで印象的だったのが、2021年にドラマ放映された『日本沈没』です。小松左京さんの原作では、まず伊豆半島から地震が発生して、そしていろいろなことが起きてから京都が突然の大地震に見舞われる。東京がやられるのはその後なんです。つまり政治経済の中心地・東京より、日本人の精神的な故郷・京都が先にやられる。こういう展開こそが関西出身であった小松さんの熱い思いでもあったとぼくは受け止めているんですが、今回の脚本では首都が最初から沈没する話になっていました。それで、省庁からエキスパートをかき集めて官僚が政治を動かすという話でした。首都が落ち着いたところで、日本全体が沈没するという話に変わっていたんです。現代的なリメイクではありますが、ああ、やっぱり日本は東京が危機に陥らないと官僚も政府も動かないんだな、と考えさせられました。
押谷: 2020年2月28日に北海道知事が独自の緊急事態宣言をしたとき、首都圏の人たちに危機感はなかったと思います。3月末になって東京が危ないという状況になって初めて、危機感が醸成されたというのはたしかでしょう。東京の感染者数が優先的に放送されていますしね。地方で大きなクラスターが出たり、死亡者が増えたりしても、全国ニュースにはなりませんでした。
瀬名: 宮城県仙台市在住のぼくがネットでYahoo!ニュースを見ても、東京の感染者数がトップに出てきました。そうしたニュースを毎日見て、東京在住以外の全国民も感情を引っ張られて一喜一憂せざるを得ない状況になってしまいましたね。
押谷: 東京を起点に流行が起こるということが繰り返されているので、東京の状況に注目することにも一理はあります。地方の知事も、東京で制御ができないので流行が繰り返されるのだと発言しています。都市部固有の問題があって、その指摘は間違っていません。COVID-19は、社会にあるひずみを狙って襲ってきます。そのひとつが都市の人口集中の問題。
明治時代と今の人口比を見ると、人口が増えている都道府県でCOVID-19の被害が広がっています。そういったところは人口が密集しているということもあるし、東京とのつながりが強いということもあるのでしょう。BSの対談でも、国立環境研究所の五箇公一さんが、閉鎖系の社会がこういう危機に対し安全なのだという話をしていました。明治以降、日本は開放系の社会になった。それまであった、社会のいろいろなバリアが取り払われ、一気に脆弱な社会になったと言えます。
瀬名: あの対談では、地産地消という話もありました。そういう強靭さというかしなやかさ、レジリエンスを維持することが大切だと。COVID-19は、発症前に他人に感染させるうえに発症が速いこともあり、都市圏での広がりが速い。そこがSARSなどとの大きな違いなのでしょうか。
押谷: 必ずしもウイルスの特性だけではありません。欧米では、COVID-19の感染は大都市から始まって地方都市に広がり、地方都市のほうが深刻な状態になっています。わりと最初の頃から、イギリスも南部やスコットランドでも厳しい状況が起きています。英米では、デルタ株でもエスニックマイノリティの被害が飛びぬけて大きい。集まって住んでいる郊外の地区のコミュニティの被害が大きい。アメリカでは、たとえばオハイオの農場でクラスターが発生したりしています。ヒスパニックの季節労働者や不法移民の死亡者数が多いのです。
過渡期にある日本でもその傾向は見られますが、そういう状態が欧米ほどは進んでいないため、被害が低く抑えられてるという側面もあります。もしかすると、20年前だったら、もっとうまく対応できていたかもしれません。一方、医療格差、貧富の差などがこのまま進んでいったとしたら、20年後にCOVID-19の流行が発生しようものならもっと大きな被害が起こることが考えられます。
瀬名: うーん、グローバル化と共に都市問題、貧困格差などの問題が、今回のパンデミックには関係しているわけですね。
押谷: 最初の流行の真の原因はわかりませんが、一帯一路参加国のイタリアやイランなどには中国人の大きなコミュニティがあるので、初期の流行拡大にはそれも関係していた可能性があります。2003年のSARSの流行は、世界30数か国に広がったものの、中国本土以外で最初に大きな流行が起きたのはカナダのトロント、ベトナムのハノイ、香港、シンガポールでした。それは、広東省の広州から人の感染者がバスに乗って香港に行き、宿泊したホテルから広がりました。それが香港、シンガポール、ハノイ、トロントに広がった。
今回は、近代的な都市である武漢でまず大きな流行が起こりました。WHOのインディペンデントパネルが2021年5月に出した報告書では、封じ込める最後のチャンスは2020年の2月だったとなっています。もっと早く流行が検知され 、世界が同じ方向に向かって協力していたら、世界的な早期の収束が達成されていた可能性もあります。実際、武漢株については、アジアではおおむね封じ込めに成功しました。それができなかったのが中東とヨーロッパで、そこからヨーロッパ株に変異して世界的に広がったのです。
瀬名: 2003年だったとしたら、グローバル化が進んでいなかったからということですね。
押谷: その当時はまだ、中国の地方都市は世界とつながっていませんでしたからね。少なくとも、春節に海外に出る旅行者の数も少なかった。
長期的な視野が必要
瀬名: 中国とWHOの関係も問題になりました。現代では「専門機関の政治化」、そして世間のしがらみに縛られてはならないないはずの「専門性の原則」、こうしたバランスが取れなくなってきているとの指摘もあります。ビル・ゲイツ財団は感染症対策に巨額な資金を提供しています。
押谷: 2003年の時点では、世界にはWHOに対する信頼感がまだありました。その後、トランプ対WHOという対立の構造もあったりして、独立した仕組みをいかに作っていくかは難しい状況です。たとえビル・ゲイツの寄付で新しい機関を作っても、うまくは機能しないと思います。政治的中立の確保が重要で、ビル・ゲイツが作った機関が、ロシアやイラン、北朝鮮に行ってパンデミックの調査をすることができるとは思えないからです。かといって、国際機関が政治と無関係でいられるかというと、そういうわけにもいかない。
WHOの緊急事態宣言が1月23日にいったん見送られ、30日に出される間に、WHOのテドロス事務局長は習近平に会いに北京に行っています。それはあってはいけないことでした。WHOは専門機関として、専門的な見地から評価しなければならないからです。WHOの矜持を失わせる行動でした。現状では、WHOが緊急事態宣言を出すにあたっては、WHO自身が緊急委員会を招集する規則になっています。これは問題だと思います。WHOとは独立した専門家が決められるシステムであるべきです。
瀬名: 話を日本に戻して、分科会の立ち位置はどうなのですか。
押谷: リスク評価をするのは厚労省のアドバイザリーボードです。いちばんの問題は、国内の感染症疫学の専門家の数が絶望的なまでに少ないことです。少ない人数なのにいろいろな仕事が降って来る。長期的な観点で検討すべきことができない状況です。イギリス政府のCOVID-19対策を策定する非常時科学諮問委員会(SAGE)には、180人くらいの専門家がいます。それにひきかえ、日本での日曜日の勉強会でも、せいぜい十数人、しかも手弁当でやっています。もう限界に近い。バッティングケージの中にいて、あちこちから飛んでくるボールをひたすら打ち返し続けてきたのがこの2年です。本来は広く議論して決めていかなければいけないことを、少人数で議論しているのは問題です。
たとえば、高齢者施設で亡くなる人たちの問題を考えるには、医療だけでなく死生観も関係してきます。少人数の数時間の議論で決められる問題ではありません。しかも、以前から目を背けてきた問題となればなおさらです。
瀬名: 奇しくもそれが、COVID-19で可視化されたわけですね。
押谷: 究極的には、COVID-19で毎日何人死ぬことを許容するのかという問題に帰着します。
オミクロン株の第六波以前の流行では、国内では1日の死者が100人を超えるような状況になると社会が許容できなくなっていました。医療がひっ迫してその一線を超えそうだというようなニュースが流れると、一気に行動変容が起こって感染者の数が減るというパターンを繰り返してきました。今は、毎日200人以上の人が亡くなっていますが、致死率が低下していることもあり、そこまでの緊迫感はありません。ただ、分母が大きくなると、必然的に死亡者は増えていきます。現在の死亡者にはさまざまな原因で死亡している人も含まれていて、COVID-19だけが直接の死因ではありませんが、毎日200人の高齢者がCOVID-19に関連して亡くなるという社会を我々は許容するのかという問題を考えないといけないということだと思います。
経済優先を唱える人たちは、対策を緩めたらどうなるかをほんとうに理解しているとは思えません。アメリカではつい最近まで毎日2000人以上が死亡していました。1月からだけでも13万人以上が死亡しています。社会を動かすことを優先して、毎日1000人以上死ぬことを許容するのか。それを決めるのは専門家ではなく政治家であるべきだと思いますが、対策を緩めた時にどういうことが起こるかをきちんと理解して判断すべきだと思います。
瀬名: 季節性インフルエンザでも、世界で毎年何十万人も死んでいました。しかしそれは見えていなかった。ほとんどの人は覚えていないようなのですが、ぼくの父が現役のウイルス研究者として頑張っていた頃、感染症研究者の人たちは「インフルエンザは風邪じゃない」というスローガンを掲げて、毎年多くの人が亡くなっているんだからインフルエンザを甘く見てはいけないと熱心に国民を啓発していました。COVID-19はインフルエンザみたいなものという言い方に対して、だから分科会メンバーの岡部信彦先生も、いや、インフルエンザはそもそも怖い病気なんだと発言なさっていて、その気持ちはよくわかるんです。なのにいま、それを叩く人もいる。しかし、何人までの死者なら許容するという議論は、何人までなら見て見ないふりをするのと同じことではないでしょうか。それは難民問題から目を背けるのと同じ。あるいは目の前にあっても見えないフィルターを自分にかけて安心してしまうのと同じ。究極的には、人間はどこまで想像力を発揮できるか、どのように適切に想像力を発揮するのか、という問題に帰着するのだと思います。どうお考えになりますか。
押谷: ぼくもそれは危険な議論だと思っています。しかしそういうところまで来てしまっているので、避けられない議論です。欧米は規制をほぼ撤廃していますが、今ヨーロッパの多くの国で感染者数は増えています。それに伴って死者数も。ワクチンを接種していないような人が死亡するのは自己責任扱いにして、高齢者の死者数と社会を動かすことを天秤にかけているという側面があります。日本でそういう議論がなじむとは思えません。むしろ避けたい話題でしょう。経済界の言う、社会を動かすということは、何万人も死ぬ可能性があるということなのに、彼らにはその実態が見えているとは思えません。
瀬名: 経済界の人たちにすれば、経済が停滞すれば失業者、自殺者の数も増えるぞと言いたいのでしょうか。
押谷: それは比較の対象が違うのです。これまでの国内の自殺者数とCOVID-19の死者数を比較するのは論理的に間違っています。本来比較対象とすべきは、何も対策をしなければ何人が亡くなるのかです。日本では、さまざまな対策を総動員し、人々の気持ちもその方向に向いて、先進国としては死者数を低く抑えてきました。今後は対策をしないという判断をしたとき、どれくらいの人が感染して死者はどうなるのかを考えるべきです。これまでぎりぎりに抑えてきたことのコストと比較するのではなく、対策をしなかった場合のコストと対比すべきなのです。
瀬名: しかしその比較をするためのデータはないですよね。
押谷: ないけれど、欧米の死者数を日本の人口に換算すると、30〜40万人規模になります。これは、現在の日本の死者数の10倍以上です。
瀬名: 規制をなくした欧米のデータが参照の対象になるわけですね。
問題の複雑化
瀬名: 先ほど、専門的知見で長期的な観点の検討ができていないとおっしゃいました。それは感染症対策の専門家の数が少なくてその余裕がないせいなのか、あるいはほかに何か理由があるのですか。
押谷: というか、そもそも感染症対策や医療公衆衛生だけでは対応できない問題なのです。社会全体を巻き込んだ問題になっており、問題が複雑化しすぎています。麻疹の対策なら、ワクチン接種をどうするかという問題で、経済の側からの文句は出ません。多くの感染症の対策は、単純に感染症対策の問題であって、他の分野の人には直接関係する問題ではありません。
そもそも、これまでの急性感染症のアウトブレイク(流行)は短期決戦でしたが、COVID-19はそうではない。不確定要素が多いなかで流行は長期化しています。世界の専門家のあいだでは、このパンデミックは数カ月では終わらない、数年は続く問題ととらえている人が多いです。
瀬名: これまでの感染症の流行は、だいたい数カ月も辛抱すれば収まっていましたものね。ですがCOVID-19は、専門家であっても2カ月ごとに見える光景がまったく違ってしまうと言われています。ワクチン2回接種が行き渡ってひと息ついたかと思った途端、今度はオミクロン株が出てきました。
押谷: ぼくは最初から、簡単には終わらないとずっと言ってきたのに、大手メディアは明るそうなニュースに飛びつくばかりで、さっぱり伝わっていません。複雑化、長期化している現状で、感染症の専門家だけでは解決できない問題になっています。誰も考えてこなかった状況ですし、考えても簡単に結果が得られるような状況でもないので。ぼくらの役割は、どんどん変わっていく状況、不確定要素が大きくて来週何が起きるかわからない中でできるだけ被害を抑えるための最適解は何かを見つけていくことなのです。
先ほども言ったように、われわれは封じ込めは最初から目指していませんでした。選択したのは、封じ込めが現実的な目標となりえないとわかった最初の頃から〝コロナと生きる〟です。こういう国は少ない、もしかしたら日本だけかもしれない。今日の最適解は明日の最適解ではないかもしれないという状況の中で、リスクマネジメントをしてきたのです。ワクチンにしても、最初は95%有効で重症化も阻止すると言われていましたが、ぼくは疑っていました。そうじゃないとわかったときと、デルタ株が出てきたときと、オミクロン株が出てきたときとでは、最適解がそれぞれ異なります。それをいかに見つけ出していくのかが、われわれ専門家の役割だと思っています。欧米では、それがどうやらできていない。
瀬名: 明日のことはわからない中で、方向性は見えているのですか。
押谷: 方向は見えていないかもしれないけれど、それを考えるのがぼくらに課せられたことだと思っています。しかしそれができないと、立ち向かっていけない。欧米は、いうなれば一本足打法でした。最初は、WHOも含めて、とにかく検査、検査、検査。それで封じ込めができると言っていた、あれは絶対間違いだと思っていた。そのうち、抗ウイルス薬、次はワクチンで解決すると楽観した。しかしいずれも問題解決につながっていません。欧米の専門家は、科学を信奉しすぎているのかもしれない。イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンもそういうことを言っています。宗教が消えて科学信仰が残ったと。フランスの哲学者ジャン・リュック・ナンシーも同じようなことを言っています。新型コロナウイルスが人間化したのだから、人間が解決しなければならなくなったと。しかし欧米は、科学信仰が過ぎたゆえに間違った側面もあると思います。
瀬名: 2020年春に押谷先生が宗教学者の木村敏明先生と電話で対話なさったのも、そういうことなのでしょうか。
押谷: そうです。フランスの人類学者レヴィ・ストロースの言う「野生の思考」の問題なのだと思っています。欧米社会は、科学の進歩と引き換えに切り捨ててきた「未開社会」の知恵を失ってきた。柔軟な考え方、柔軟な対応が必要なのに、ワクチン接種推進派と反対派に分かれてデモし合うようになっているのがその典型です。
瀬名: それについては、エビデンス(証拠)に基づいてやっていないじゃないかという批判が、いまに至るまでずっとあります。
押谷: 反復することで得られたものでなければ科学的エビデンスとは言えないはずです。自然科学で再現性が重要視されるのはそのためです。2020年4月7日を1000回繰り返せるとしたら、緊急事態宣言の効果を科学的エビデンスに基づいて検証することも可能です。しかしそれはできない相談です。何百万人もの人間の行動が関係しますから、コンピュータシミュレーションでもカバーしきれません。なのでそこに本当の意味のエビデンスは存在しません。そこにあるのは、もっともらしさだけです。もちろん、専門家もそういう状況では間違いを犯すこともあります。ならば、間違いを減らすこと、致命的な間違いをしないことが大切になります。
瀬名: ただ、ワクチンの有効性とか、海外で得られたデータはある。
押谷: もちろん、文献やデータなどは参照しています。しかし、参考にはするけれど、そこに必ずしも絶対的な真実があるわけではない。情報量が多すぎてもダメなんです。
瀬名: キャパが大きいからいいというわけでもありませんしね。
押谷: いろいろな意見を聞けばよいというわけでもありません。ぼくが積極的に目を通している医学雑誌は《ランセット》と《ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン》です。それと、CIDRAPというアメリカのサイトがすぐれています。多くの資金援助を受けて、感染症に関する的確な情報発信をしています。おそらく優秀なブレーンを雇ってやっているのだと思います。重要な情報が毎日出ている。それを見るのが朝の日課になっています。
真の学際研究を
瀬名: 東北大で「感染症共生システムデザイン 学際研究重点拠点(SDGS-ID)」を起ち上げた思いを教えていただけますか。
押谷: 事態がどんどん複雑度を増して進行しているからです。2020年の4月の初め頃、木村敏明先生に電話をした理由は、この問題は社会の様々な矛盾をあぶり出しており、そこを理解しないと解決できないと思ったことです。木村先生に聞きたかったのは、海外では宗教に関連した、非常に大きなクラスターが起き続けているけれど、この問題の本質は何なのかということでした。既成の宗教では安全装置がはたらいています。イスラム教の金曜日の礼拝は、参加できない場合の代替措置が用意されているし、ローマ法王はネット礼拝をいち早く導入した。ところが一部の原理主義的な宗教でクラスターが起きている。人が集まることに意義を見出している宗派でクラスターが起きているのはなぜなのか。それを木村先生に聞きたかったのです。
瀬名: 宗教と医療との関係では、宗教学から臨床宗教師が生まれたという事情もありますしね。
押谷: それ以外にもいろいろな問題があって、あちこちに発想が飛びました。WHOを含めてグローバルヘルスガバナンスの将来像はどうあるべきなのか、経済との両立はどう考えたらいいのかとか、いろいろな疑問があります。感染経路についても大きな問題があります。国内では飛沫感染や接触感染が感染経路の主体だと考えている専門家がいますが、それは違うと思っています。ダイヤモンドプリンセス号での感染も、飛沫感染や接触感染だけでは説明がつかず、エアゾル感染の存在を当初から疑っていました。感染経路については医学系と工学系の研究者が共同研究をしています。
これまで学際研究と言われていたものは、かけ声はいいけれど、共に社会の問題を解決するというよりも、自分の研究に足りないピースをどこからか探してくるというスタンスに立つものが多かったような気がします。必要なのは真の総合知です。
瀬名: まさにヒューマニティの問題ですね。ヒューマニティは日本語の「人道」「人間性」でもありますが、「人文知」でもあります。
押谷: 東北大は震災を機に総合知に立ち返るべきでした。今こそ、そういうことに立ち戻らないと。
瀬名: それでSDGS-IDはうまく進んでいますか。ぼくもここ1年半、渡辺政隆先生といっしょにこの対談連載をやって、SDGS-ID参加の先生に限らずいろいろな先生方にお話をうかがってきたのですが、どうもあまりうまくいっていない、本当に目指したいところまで辿り着けていないような気がするのです。
押谷: はっきり言って、必ずしもうまくいっているとは言えません。若手セミナーをきっかけにしたいと考えているのですが、若い人がまだ積極的に研究を展開できるようにはなっていません。
次の社会をどう作るか。グローバル化で開放系になって脆弱になった社会をどうするかを話し合いたいのです。ぼくはニューノーマルという言葉が嫌いです。そういう小手先の対応で何とかなる問題ではないと思います。この問題は人類にとって転換期に起きたことだと考えています。
2003年ならこうはならなかったと話したように、COVID-19は、今の時代に起こるべくして起こったのです。14世紀のペストの流行の前後も、同じようなことが起きています。ヨーロッパとアジアがモンゴル帝国でつながったり、欧州がアジアに進出したり。さらに牛疫の大規模な流行や、ヨーロッパの経済危機、火山爆発、寒冷化、戦争など、複合的な要因で起きたものです。そのことはイギリスの歴史学者のブルース・キャンベルが膨大なデータを使って論じています。そういう意味で14世紀のペストの流行も歴史の転換期に起きたことです。今回のパンデミックも歴史の転換期に起きたもので、単に偶然起きたものではないと思います。歴史に学ぶことも重要です。その意味では、これまで日本が軽視してきたリベラルアーツ(教養)の重要性をもう一度真剣に考える必要があります。
瀬名: 今回は押谷先生ご自身の思いにフォーカスを当ててお話をうかがいましたが、次はそのビッグピクチャーのお話を、今月開催(2022年3月19日)のシンポジウムでぜひ展開できればと思っています。
対談を終えて
瀬名: ぼくが今回のCOVID-19で何度も考えさせられたのは、こうした複雑な現代社会情勢の諸問題は、ひょっとしてもはやホモ・サピエンスである人間の知能の限界を超えてしまったのではないか、ヒトだけで解決するのはもう無理な状況に突入してしまったんじゃないか、ということでした。いや、そんなことはない、人間の知能にはもっともっと可能性がある、と信じたいのですが、ぼくら人間はどうしても感情に縛られる生きものです。感情を揺さぶられると右往左往してしまいますし、政治には多くの人の思惑が絡んで、純粋に自然科学の問題としてはとても対応できない場面があらゆるところで勃発します。よく言われることですが、「何とたたかっているのかわからなくなる」。もう社会問題の一部は感情を持たないAI(人工知能)の判断に任せた方がいいんじゃないかと思うこともあります。そんななか、今回押谷先生にご紹介いただいたように、がんばるでもない、たたかうでもない、明るい方へ、という考え方があるのだということには、改めてはっとさせられます。
この10年ほど自分への宿題だと思いながら果たせていないことに、アダム・スミスの『道徳感情論』をちゃんと読もう、というのがあります。経済学の父といわれるアダム・スミスは、有名な『国富論』の他にもうひとつ、『道徳感情論』という本を書いているんです。私たち人間は道徳感情によって動く社会的存在なのだから、経済を理解するには人間の感情のメカニズムを深く洞察する必要がある、と彼は考えた──そこまでは一般知識として知っているんですが、具体的にアダム・スミスがどういうことを考えていたのか、しっかり本を読んでおきたいと思っていたんです。
まだそれは果たせていないのですが、先日、堂目卓生さんの解説書『アダム・スミス―『道徳感情論』と『国富論』の世界』(中公新書、2008)をようやく読んで、これぞ異分野融合、本当の学際への道なんだと感動しました。アダム・スミスは『道徳感情論』で、人間のシンパシーsympathyについて語っているんです。彼のシンパシーは日本語で「同感」「同情」「共感」などと訳されてきたそうです。今回のCOVID-19でも、多くの人が何度も共感や思いやりの心の大切さを説いてきました。ただ、日本語の「共感」という言葉はとても曖昧で、いまひとつぼくらは問題の焦点をつかみ切れていなかったかもしれない。この本はそのもやもや感を解消してくれました。
堂目さんが示しているアダム・スミスの本質はこうです。まず「スミスは、人間本性の中に同感sympathy──他人の感情を自分の中に写しとり、それと同じ感情を自分の中に起こそうとする能力──があることを示し、この能力によって社会の秩序と繁栄が導かれることを示した」。つまり私たち人間は、社会性のある大人に成長して他人を観察するとき、自分の胸中に「公平な観察者impartial spectator」というメタ人格を作って、ふだんからその視点から物事を見て、「あなたは正しい」とか「あなたは間違っている」とか、適切性の是認や否認を行っているのだ、というのですね。その「公平な観察者」の観点から、他者に「同感」するかどうかによって、相手を称賛したり非難したりしている。それがシンパシーで、またそうした観点は自分自身に対しても同じだというのです。たとえ他人から表立って称賛されなくても、世のなかには裏方で頑張って働いている人たちがたくさんいる。そういう人たちは自分の胸中にある「公平な観察者」の視点で自分を見て、それが称賛に値する行為だとわかっているから、くじけずに頑張ることができるんだということです。
ただし世の中には偶然の産物というものもあって、意図せず結果的に他者に有益な行為となってしまう場合もある。反対にいくらその人が頑張っても結果的に益にならないこともある。そういう結果だけで世間的な評価がなされてしまうのはいつの時代も同じで、納得のいかない、不公平なことなんですが、本当は胸中にある公平な観察者の視点から、世間が正しい称賛や非難をしているのかどうか判断できるはずだ、それをちゃんとできる人が「賢人wise man」で、できない人は「弱い人weak man」なんだ、と論じているのだそうです。
だから賢人は、たまたま自分が意図せず称賛されてしまった場合でも、身の丈を超えて有頂天になったりはしない。「良心の呵責」という心のはたらきをもっている。ただし! とここで堂目さんは指摘します。スミスに拠れば、たとえ「賢人といえども根拠のない非難に対しては動揺する」というのです。なるほど、これが人間の限界性なのか、と膝を打ちました。そして実際には、「すべての人間は、程度の差はあれ、賢人の部分と弱い人の部分の両方を持っている」という。その通りだと思いました。
私たち人間は、社会的存在へと成長したとき、他人の感情や行為に関心をもち、それに同感sympathyする力をもっている。その上で他人が自分と同じ意見であるかどうかを推測して、善悪を決めている。けれどもたぶん私たちは誰しも、自分の胸中の公平な観察者が常に揺れ動いているのだ、とぼくは思いました。本来なら公平な観察者の判断によって人を称賛したり非難したりできるのに、往々にして私たちは、その「公平な観察者」というメタ視点の存在を忘れて、人間の本性としてのシンパシーが肥大してしまって、「絶対に自分は正しい」「あいつは絶対に間違っている」という「極端な正義感」に取り憑かれて、その信念に縛られてしまう。今回のCOVID-19が炙り出した問題の多くは、人命か経済かといったような二者択一問題のように思えてしまうけれども、実はそうではない。アダム・スミスが18世紀に『道徳感情論The Theory of the Mind Sentiments』と複数形で論じていたように、道徳原理を形づくる複数の諸感情によって生み出されたもので、公衆衛生と経済は私たちの人間本性によってひとつにつながっていたのだと理解できたのです。
アダム・スミスが生きた時代はアメリカ独立戦争とフランス革命が起こったときで、本には「同胞感情fellow-feeling」という言葉も出てくるようです。同感sympathyとほとんど同じ意味で使われている箇所もあるそうですが、「自分たち仲間さえよければ、他の人はどうでもいい」という狭いコミュニティ感情に陥ってしまっては、賢者になれない。賢者とは自分の中にある思いやりの心を制御できて、たとえいったん間違ったとしてもそれに固執せず、適切に自分を立て直して行動できる人のことなのだ、とぼくは思いました。国内の農業や製造業を蔑ろにして外国貿易で国がマネーを稼ぐ、偏った発展の時代でもあった、とも書かれていて、現代に通じるものを感じます。
人々の感情を無視して理想論だけで物事を拙速に動かそうとする「体系の人」はだめだ、ともスミスは論じたのだそうです。人間はチェスの駒ではない。だから個人が同感と正義感をもって行動し、経済活動できるよう、改革はゆっくりと行うのがよい、と言ったそうです。
でも私たちは人間だから、どうしても感情に動かされてしまって社会が混乱することもあるよ、そこはどうすればいいのだろう、と思いながら読んでいて、チェスの駒、という言葉で、ぼくはAIを思い出しました。感情に押し流されてはいけない一部の問題については、ひょっとしてある程度AIやロボティクスといった生死の概念を持たない別の知能の助けも借りながら、私たちは生きてゆくのもこれからは大切なのかもしれない。今後はそのバランスも見極めて未来をつくってゆくことが、私たち人間の〝人間らしさ〟ではなかろうか。
幸福とは何か、心の平静とは何か、という問題もスミスは論じていたそうです。賢明さと弱さのバランスこそが対応策への視点でもあると堂目さんは述べています。それで、この解説書の「あとがき」で、こうして述べてきたことは2006年に「脳を活かす」研究会の「脳を読む」分科会研究会で発表したのだが、そこでは脳神経科学者も多く参加していて、スミスの言う「同感」や「公平な観察者」の概念はまるで近年のミラーニューロン仮説や心の論理(セオリー・オブ・マインド)だと驚かれた、と書かれてあって、ああ、そうだったのか! と感嘆しました。
実はぼくも2006年に「脳を活かす」研究会の起ち上げシンポジウムで、ジャーナリストの立花隆さんらと並んで講演していたからです。あのころからシンパシーというキーワードで行動経済学と脳神経科学がいっしょに議論していた事実があったのに、ぼくは今日の今日までそれに気づけなかった。それを多くの読者に伝えることができていなかった。自分はいったいこの十数年、何をやっていたんだ、と衝撃を受けました。
おそらく押谷先生がお考えになっている未来のリベラルアーツのあり方は、すでにヒントがあちこちの分野で論じられてきたはずなんです。でも私たちはこれまで、それが見えていても見えなかった。見えていても気づけなかった。総合知に連結できていなかった。見えていなかったものをもう一度見る大航海時代の始まりだとぼくは思っています。
連載の最後に押谷先生からお話をうかがえてとてもよかったと思います。同時にこれが始まりでもある。押谷先生の問題提起が、新しい時代を切り拓くきっかけのひとつとなることを願っています。
*注
(1) 河合香織『分水嶺 ドキュメント コロナ対策専門家会議』(岩波書店、2021)
(2) 江戸時代に、疱瘡(天然痘)で亡くなった人を疱瘡神として祭り、守ってもらうために建てた石碑と言われている。
(3) 2020年3月19日に初回放送されたNHK BS1スペシャル「ウイルスVS人類〜未知なる敵と闘うために〜」
(4) 2020年3月22日(日)に初回放送されたNHKスペシャル「“パンデミック”との闘い~感染拡大は封じ込められるか~」
(2022年3月10日取材、3月18日記事作成)
(編集責任:東北大学広報室特任教授 渡辺政隆)
押谷 仁(おしたに ひとし)

1959年生まれ。東北大学大学院 医学系研究科 微生物学分野・教授。フィリピン、モンゴル、インドネシア、カンボジア、ザンビア等のアジア・アフリカを研究フィールドとして感染症研究を行うとともに、国の新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会の構成員等も務めている。『ウイルスVS人類 』(共著)、『パンデミックとたたかう』 (共著=瀬名秀明)、『 新型インフルエンザはなぜ恐ろしいのか』などの一般向け著書がある。
瀬名 秀明(せな ひであき)

1968年生まれ。作家。東北大学大学院薬学研究科博士課程在学中の1995年、『パラサイト・イヴ』で第2回日本ホラー小説大賞を受賞しデビュー。1998年、『BRAIN VALLEY』で第19回日本SF大賞受賞。東北大学大学院工学系研究科特任教授(2006~2009)。小説のほか、『パンデミックとたたかう』(共著=押谷仁)、『インフルエンザ21世紀』などの科学ノンフィクションもある。小説『この青い空で君をつつもう』『魔法を召し上がれ』『小説 ブラック・ジャック』などでは、新しいジャンルにも取り組んでいる。
(肖像写真 佐々木隆二氏撮影)
渡辺 政隆(わたなべ まさたか)

1955年生まれ。サイエンスライター。日本サイエンスコミュニケーション協会会長。文部科学省科学技術・学術政策研究所(2002~2008)、科学技術振興機構(2008~2011)、筑波大学広報室教授(2012~2019)を経て、2019年より東北大学広報室特任教授、2021年より同志社大学特別客員教授。進化生物学、科学史、サイエンスコミュニケーションを中心に、『一粒の柿の種』『ダーウィンの遺産』『ダーウィンの夢』『科学の歳事記』などの著作のほか、『種の起源』(ダーウィン著)、『ワンダフル・ライフ』『進化理論の構造』(グールド著)など訳書多数。