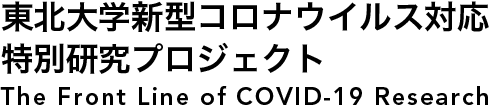PEOPLE
インタビュー
専門家が果たすべき役割―専門知の活かし方
ワクチンの効果か、新規陽性者と死亡者の数が目だって少なくなりました。とはいえ、これで終わるわけではありません。安心は禁物です。パンデミックはこれまで何度となく、ある日突如出現し、いつのまにか唐突に姿を消すということを、何度も繰り返してきました。予想しがたい相手なのです。私たちは今一度気を引き締めると同時に、将来にも備えねばなりません。そのための制度設計をどうしたらよいのか、物理学者であると同時に社会科学技術論の研究者でもある本堂毅准教授と瀬名秀明さんに語り合っていただきました。
(2021年10月8日にオンラインで収録)
瀬名: 1年前に始めたこの企画で、これまでいろいろな方にお話を伺い、未曽有の事態に対して、総合大学に何ができるのかを考えてきました。そのなかで本堂さんは、いくつかの研究分野に越境して共同研究を進めており、いささか型破りなタイプの研究者とお見受けします。そこでぜひ、斬新な視点からのお話を伺えればと思っています。よろしくお願いします。

本堂 毅准教授
本堂:はい、こちらこそよろしくお願いします。
緊急声明の背景
瀬名:本堂さんは、国立病院機構仙台医療センターの西村秀一さんたちと、8月21日にオンラインで記者会見を開かれました。ぼくも西村さんとは昔からの知り合いで、西村さんが主宰されていた「みちのくウイルス塾」にも時々参加させてもらっていました。拙著『21世紀インフルエンザ』 (注1)にも登場していただきましたし、西村さんが個人的に訳していたクロスビーの『史上最悪のインフルエンザ』(注2) 出版の話をぼくがみすず書房に橋渡ししたという縁もあります。今回、お二人を中心に緊急声明(注3) を出された経緯をお話いただけますか。最初は本堂さんが研究者仲間と話していて、西村さんに意見交換を求めた上で賛同者を集めたということのようですが。
本堂:はい、そもそもの話から言うと、私は東北大学大学院理学研究科で、安全衛生管理室副室長という立場にあり、研究科内での新型コロナウイルス感染症(以下COVID-19と略)の感染拡大を防ぐための対策に関わっていました。必要に応じて関連文献の勉強を進める中で、感染拡大を抑えるには換気が重要だということに気づきました。私はもともと医学関係の共同研究もしていますので、医学論文にも慣れていました。そこで2020年7月に雑誌「世界」でCOVID-19問題に関する、どちらかというと批判的な論考(注4)を発表しました。ちょうどその頃に、西村さんもある新聞で同じような発言をされていたので、連絡を取りたいと思い、「世界」の原稿をお送りしました。そうしたら丁寧なご返事をいただき、それ以来、意見交換を続けていました。
学内におけるCOVID-19対策だけでなく、医師の方たちと数年前から人体への電磁場の影響を調べる共同研究をしており、その研究におけるCOVID-19対策を講じなければと思っていました。さらには、法学者とも共同研究を進めていた関係で、「判例時報」という雑誌に、COVID-19対策の公平性に関する論考(注5) も寄稿していました。
去年の7月くらいから、感染制御と経済についても考え始めたことから、COVID-19対策を研究テーマの1つにしました。その最初の成果は間もなく公表される予定です(注6) 。つまりCOVID-19は、大学教員としての職務の一部でもあり、研究者としての研究テーマでもありました。
具体的な行動を起こしたきっかけは、今年の7月くらいに、政府や自治体が、感染拡大の中で実施すべき対策はやり尽くしたというような発言がなされるようになったことです。それはないだろうとの驚きの念を強くしました。

瀬名秀明さん
瀬名:たとえば宮城県知事が6月13日の緊急記者会見での発言「全国で感染が広がる中、このやり方を続けても患者が減る可能性は低いと思う。行政が今やれる限界だ」(注7)ですね。
本堂:はい、たとえば不織布マスクの励行を積極的に呼び掛けるだけでも感染は防げるし、換気の徹底という問題もあるのになぜ?と驚きました。法学者も参加している研究グループ内でも、そういう発言はおかしいと議論していました。そういうことから、何らかの声明を出したほうがいいのではと思い、何人かに相談する中で、西村さんからも賛同を得たのです。そこで西村さんらと素案を練り上げ、仲間に提案したところ、1日で31人の賛同者を得ました。
瀬名:記者会見の資料には、西村さんと意見交換をしたのが今年の8月17日とありますが、ちょうどオリンピック開催中で、感染者数が増加していた時期にあたりますね。オリンピックをやっている場合ではないよという風潮も追い風になったのですか。
本堂:それはありました。科学的に実行できる対策はまだあるのに、世間が投げ槍になってはいけない、やれることをやっていこうよ、そうすればある程度の抑制効果はあるからということを、科学者として発信しなければという強い思いがありました。西村さんとの話で、賛同者をたくさん集めるよりも、集まっている人たちだけですぐにでも声明を出したほうがいいという結論になりました。それで24時間待って集まった33人だけで声明を出すことにしたのです。
瀬名:本堂さんの行動力、実行力が実って、緊急声明がメディアで報じられました。声明文を見ると、人流を抑える対策以外にもやるべきことはあるとあります。エアロゾル (注8)に対して正しい認識を共有すべきだというのが1つ、室内の機械換気の徹底がもう1つ。
たしかこれは、空気性感染症の専門家である西村さんが以前から発言していたことで、今回のCOVID-19でもいち早くそういう発言をされていたと思います。《ダイヤモンド・プリンセス号》では空気感染が起こっていると当初から指摘され、日常生活ではマスクが不要な場面がたくさんあることや、店のビニールシートの間仕切りに有効性はないだろうといった発信をされていました。しかし専門家会議の委員でもなく、仙台の1医師ということから、あまり注目されませんでした。ぼくも、「週刊ダイヤモンド」で対談したのですが、ヤフーニュースに転載されたとき、「西村って誰だ、教授の肩書きもついていないし、整形外科医だったら笑うね」といった揶揄がコメント欄に書かれたので、西村さんは苦笑なさったことでしょう。大学研究者ではないので教授の肩書きはありませんが、臨床研究部ウイルスセンター長ですよね。西村さんは空気感染分野の第一人者ですし、地域のパンデミック対策の最前線で活躍されていることを熟知しているぼくらにすれば歯がゆい話でした。それが今回の緊急声明で西村さんの名前が全国区になり、著書も売れているようです。
それはともかく、COVID-19に関してはさまざまな情報が錯綜していて、WHOが空気感染の事実を認めるのも遅かったですよね。西村さんも含めた内外の専門家が昨年緊急声明を出し、WHOもようやく認めるに至りました。そのあたりの経緯に関して、本堂さんはどのように見ていましたか。
本堂:ウイルス学者ではないので細かいところまでは見ていないのですが、空気を通して感染するという点については、まったく驚きではありませんでした。なぜなら、私は、シックハウスの研究で有名な日本臨床環境医学会に属しています。そこは、換気の悪い環境下ではさまざまな病気が生じることに関して、いちばん多くの知見を蓄積している学会の1つです。なので、空気の悪さのせいで病気になるというのはあたりまえという認識です。そういうことから、理学研究科でCOVID-19対策にあたるに際しても、最初に考慮したのが機械換気の不具合でした。しかも物理学者ですので、エアロゾルに関しては、ある程度直感的にわかることがありました。エアロゾルの大きさにより、空気中から落下する沈降速度に違いがあることは、物理学者のほうがきちんと理解しているはずなのです。飛沫と呼ばれてきたものは、単に大きくて沈降速度が速いというだけで、細かなエアロゾルと質的な違いはないものと理解しています。飛沫であっても、ときには滞留空気の中に何十分も留まり、空気といっしょに動くということも、物理学者であればすぐにわかることです。なので、空気感染に関してなぜそんなに意見が分かれるのだろうという見方をしていました。
瀬名:2009年の新型インフルエンザのときに『21世紀インフルエンザ』という本をウイルス学者である父といっしょに出版した際、いろいろ教わりました。そのとき思ったのは、なんだそんなこともまだわかっていないのかということでした。2009年の時点では、エアロゾル感染という概念自体がなかったような気がします。というのは、飛沫感染、飛沫核感染、そしてあとは空気感染ということしか教わらなかったからです。エアロゾル感染という観点が抜け落ちていて、近くで唾が飛ぶとか、唾の核が飛ぶ、それが目に入るという感染の仕方の先は、「アウトブレイク」(注9)という映画で描かれていたような、映画館の中で誰かが咳をしたら、それが通気口を通して隣の劇場に広がるという空気感染しかないと思い込んでいました。なので、エアロゾル感染という視点はとても新鮮で、本堂さんたちの今回の声明でようやく世間に認識されたのではないかという気がしています。(注10)
本堂さんがそもそもエアロゾルに注目されたのは、今のお話にあった、シックハウスが念頭にあって、西村さんと議論する中で具体的なイメージができたということなのでしょうか。
本堂:自分では特に意識していなかったのですが、それはあると思います。感染経路としての空気感染と感染力の強さが区別されていませんでした。以前は、感染経路と感染力が一体となって語られていたからです。しかしシックハウス症候群では、揮発性化学物質が空気といっしょに流れてゆくわけですが、それは感染力の強さとは別のことです。空気には乗ってゆくけれど、量が少なければ発症しないということがあるからです。そこである程度のイメージが作られていたので、感染力の強さと、空気といっしょに流れてゆくということは別のことだということが、医学の文脈で受け入れる準備ができていたのだと思います。
瀬名:そこが重要なところですね。ウイルス学では、接触感染、飛沫と飛沫核感染、あとは未知の空気感染の世界──の3タイプに分けていて、ウイルス学の専門家にはこの区別が先入観としてあったのかなと思うと納得できそうです。そこに今回、エアロゾル感染の可能性が加わったのは、今後に向けて重要なことですね。
発想の大本になったシックハウス症候群ですが、最近の家づくりの仕方として、断熱を重視して空気の入れ替えをなるべくしない方向に進んできたことも関係していると思います。そういう動きは、換気とは逆行していると思うのですが、建築関係者のあいだではどう考えられてきたのでしょう。
本堂:おっしゃる通りで、断熱をよくして暖房や冷房の効きをよくする設計を建築家が進めてきたことで、シックハウス症候群が増えてきました。その解決策として、空気を流すことを考えた。そこで出てきたのが熱交換換気で、外の空気と中の空気の熱を交換してから外気を取り込む方式です。臨床環境医学会では、建築家と協力してシックハウス問題に取り組んできたという歴史的経緯があります。ですから今回、エアロゾル感染と換気の問題でメディアに登場している建築家の方たちは、臨床環境医学会のメンバーなんです。西村さんといっしょにエアロゾル感染に取り組んでいた建築家が、同じ臨床環境医学会の仲間だったという背景もあります。なので共通の認識、知識があるので通じ合いました。
瀬名:日本ロボット学会でもCOVID-19の問題を議論しているのですが、最近になって、そこでも換気の話が出るようになっており、流れが変わったなと感じていました。本堂さんたちの声明が効力を発揮したのではないかと思います。工学の立場からも、COVID-19に貢献できることがありそうだという気運が生じているみたいです。
その一方で、スーパーコンピュータ富岳による飛沫拡散に関するシミュレーションがテレビで報道されていましたが、シミュレーションの結果はパラメータの設定しだいなので、ミスリーディングになりかねないのではというのが、ぼく個人の印象です。本堂さんのお考えはどうですか。
本堂:シミュレーションの結果がパラメータしだいでがらりと変わるというのはおっしゃる通りです。理想化をし過ぎるということもあります。現実には、マスクのつけ方が不完全だとか、風の流れもあります。なので、それが現実の世界に合うのかどうかという点に関しては、距離を置いて見たほうがよいと思っています。
瀬名:目に見えないウイルスの感染については実感できないことばかりの中で、エアロゾル感染とか機械換気という、具体的に実行しやすい注意点に落とし込んだ声明を出されたのは画期的なことだったと思います。ところでおひざ元の理学研究科の機械換気設備はどうだったのでしょうか。
本堂:はい、臨床環境医学会会員としてずっと気になっていたので、2020年3月に業者に依頼して調査しました。まず自分の部屋をテストケースとして調べてもらったところ、建物ができてから20数年、フィルターの清掃を1回もしていなかったことがわかりました。フィルターが詰まっていて換気ができない状態になっていて驚きました。清掃したら部屋の空気が流れるようになりました。いくつかほかの部屋も同じ状態だったので、人が集まる教室などの清掃を実施しました。オンライン記者会見でお見せした換気フィルターの写真が私の部屋のものです(図1)。フィルターを清掃して計測したところ、多くの部屋で、空気が1時間に5回ほど入れ替わるという理想的な状態になりました。部屋にしっかりした換気装置があれば、十分な換気が可能なのです。
瀬名:定期的にフィルターの清掃をすればいいということなんですね。
本堂:部屋ごとに個別の換気装置がある場合はそれでいいのですが、問題は、オフィスビル全体で換気をしている中央換気装置です。外の空気と十分には入れ替えずに、中の空気を循環させているケースがあります。それだとかえってCOVID-19ウイルスを蔓延させる危険性があるという指摘があります。
瀬名:《ダイヤモンド・プリンセス号》がそうでしたね。
本堂:ええ、西村さんが指摘されていたことです。それと同じことが、一部のオフィスビルでもありうるのです。
瀬名:機械換気に関して、海外でも動きがあるのですか。
本堂:はい、2020年5月のBBCの報道では、ドイツ政府は総額5億ユーロをかけて学校を含む公共施設の換気装置、空気清浄機を整備することにしたようです。
瀬名:そういえば、換気の問題はいつの時代にあっても大切だとされてきました。ぼくは、かつて宮城大学看護学部の教員をしていたときに、フローレンス・ナイチンゲールの著作を初めて読んで驚きました。ナイチンゲールの大きな功績の1つが、換気の重要性を訴えたことだったんですね。それまでは病人を一カ所に集めて隔離するというやり方が一般的だったのを、患者間の感染を抑えるには換気が必要だという論文を初めて書いたのがナイチンゲールだったことを知りました。声明では、病院やオフィスだけではなく、小規模な飲食店における換気の重要性にも言及されていますね。
本堂:ええ、安くておいしい店にお客さんが安心して行ける社会を回復することが大切だと思っていますから。
瀬名:プラスチックシートによる間仕切りの有効性についてはいろいろ言われていますが、どうなのでしょう。
本堂:間仕切り(パーティション)が入れば入るほど、部屋全体の空気の流れは悪くなります。そのため、換気の悪い空間に間仕切りがたくさんある場合には、密室に近づいてしまいます。部屋全体の換気がとても良いなど特殊な条件下では、間仕切りは有効になる場合もあるのかもしれません。間仕切りを迂回することで、他者に届くエアロゾルの濃度が薄まる可能性自体はあるからです。しかし、最近出版された海外の論文では、生徒の机の上に感染防止目的でデスクシールドという間仕切りを入れた教室で逆に感染が起こりやすくなったというデータも出ていました。このように、間仕切りの有効性は確立されていませんし、逆効果もありうることに注意が必要と思います。
専門家会議のあり方
瀬名:雑誌「世界」に寄稿された論考で、2020年2月14日に内閣官房に設置された専門家会議は、政府に代わって行政判断を一部代行したことで、科学者、医学者の規範を逸脱したという指摘をされています。確かに、当初、専門家会議が何をしているかは外からは見えていませんでしたが、途中から尾身茂さんや西浦博さんなどがSNSを通じて発信するようになり、まるで専門家会議が政府を動かしているかのような印象を世間に与え、SNS上でのバッシングも起こりました。ジャーナリストである河合香織さんの『分水嶺』 (注11)には、当時の専門家会議内の葛藤が描かれていて、委員の方々もサイエンスコミュニケーションを実践しようとしたものの、あまりうまくいかなかったことがよくわかります。本堂さんは、今の時点から振り返って、専門家が果たすべき役割、果たすべきだったこと、果たすべきではなかったことなどについて、どうお考えですか。
本堂:重要かつ重い課題です。感染を放置しておいたら大変なことになるという科学的事実が社会に伝わったのはよかったことだったと思います。その一方で、対策の選択肢はいくつかあるはずで、専門家としてはそれぞれの長所短所を示した選択肢のリストを政府に提出して、政治家の政治判断にゆだねるのが正しいあり方だと思っています。そのプロセスが採られていたとは思えません。議事録もないので、少なくとも外からは見えません。それと、尾身さんや西浦さんの発信は、科学だけで対策が決まるかのように見える発信の仕方でした。しかし、科学だけで対策を決めるわけにはいきません。対策を決定するのは政治家で、そう判断した理由を政治家が説明しなければいけませんでした。ただ、私は政治家ではなく科学者なので、科学者の責任をまず考えます。ですので、複数の選択肢を提案することで、政治家に政治判断を迫るような提案の仕方をしていたのかどうかが問題だと思っています。
逆に、政治家にすれば、選択の責任を取りたくないなら、複数の選択肢はないほうがいい。これについては、英国サセックス大学で科学政策が専門のアンディ・スターリングが、科学者が提案をする際には、複数の提案を、それぞれの案の適用条件を明示した上で行うべきであると言っています (注12)。そして決定した対策を発表するにあたっては、科学的に絶対という保証は原理的にできない以上、その政策決定の基礎となる知識の不完全性を踏まえた上で、特定の政策オプションを選択した理由を意思決定者が説明すべきだと指摘しています。専門家会議に関わる政策判断については、そういうことがなされたのかどうかが、少なくとも私には見えませんでした。
政治的判断の責任は政治家がとるべきものです。ところが2020年の3月19日に、尾身さんがイベント主催者に対して、入場を取りやめる人への「キャンセル代についての配慮」を求めました。これは科学的助言を与える専門家の立場を踏み越えたものでした。「世界」にも書いたことですが、学術会議が東日本大震災の経験を踏まえて「科学者の行動規範」に2013年に追加した条項に忠実に従っていれば、そういうことにはならなかったはずです。専門家会議は、「客観的で科学的な根拠に基づく公正な助言」として示された規範に従っていなかったことになります。科学的知見に基づく専門的判断を踏み越えた発言をしていると、今回のCOVID-19のように科学的知見がどんどん変わってゆく中で、科学的知見の変化自体を、政策とは区別して明確に示すこともしにくくなってしまいます。科学者の側に厳しすぎると思われるかもしれませんが、同じ科学者として、そう言わざるを得ません。
瀬名:『分水嶺』には、専門家会議と厚労省の担当者とのコミュニケーションもうまくゆかず、ましてや政治家とのコミュニケーションも取れない状況が生々しく描かれています。専門家会議委員の中のサイエンスコミュニケーションの専門家としては東京大学医科学研究所の武藤香織さんがそれにあたるのだと思いますが、本来は生命倫理や生殖医療をめぐる問題が専門で感染症は専門外なのに、報告書や声明の作成などでとてもがんばっておられたようです。それでも西浦さんのように突っ走ってしまった委員がいました。もしかしたら科学者の多くは、自分の意見は絶対と思うと、後でそれを訂正することに慣れておらず、そのための訓練を受けていないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
本堂:たしかに、西浦さんの40何万人が亡くなりかねないという発言のときも、438,359人亡くなりますというような発信の仕方をしました。これは不確実性を強調することに慣れていないからだったかもしれません。少なくとも理学の人間は、有効数字を気にします。せめて、こうこうこういう仮定に基づけば40万人くらい亡くなるかもしれないということを正確に伝えていればよかったかもしれません。
もう1つ、尾身さんの、イベントチケットの発言で問題なのは、社会の公平性の問題に踏み込んだことです。公平性は科学の問題ではなく政治の問題です。あれでは、科学的な事実がこうなので、特定の人に負担が加わることは我慢してもらわねばならないと言っていることになります。これは特定の人の権利を奪う問題であり、政治がカバーすべき問題です。科学者がそんな発言をしたので、国民は怒ったわけです。これは科学者としてだけでなく、医学者としての規範も逸脱しています。医学者の倫理を規定した「ヘルシンキ宣言」では、健康面や経済面などの弱者を配慮しなさいとあるからです。臨床研究もしている私が「ヘルシンキ宣言」を読んでいるくらいですから、医学者なら熟知していて当然なはずです。あれはやってはいけないことでした。
瀬名:「判例時報」に寄稿された論考では、社会の不公平ということで、特別な犠牲が社会のひずみとして飲食業界や旅行業界に集中してしまった、一時的にパチンコ業界が叩かれたこともあったと指摘されています。そうした業界が犠牲を強いられることを専門家が強要する結果になってしまったことが問題だと論じていらっしゃいます。そのご指摘はもっともだと思うのですが、公衆衛生の考え方からすると、感染拡大防止のためのロックダウンは、少なくとも2020年3月までの時点では標準的な選択肢の1つだったはずです。あるいは、一部の人たちの暴走を食い止めるためには、規制を一律でかけるのもやむなしという考え方もあります。COVID-19をめぐる詳細がいろいろ分かってきた現在なら、公平性を重視した進言もできるような気がします。しかし、2020年の夏くらいまでの時点で専門家にそれがはたして可能だったのか、難しかったのではないかと思うのですがいかがでしょう。いつか別のパンデミックが起きた場合も見据えて、科学者、専門家はどう振舞うべきなのか、お考えをお聞かせください。
本堂:おっしゃるとおり、科学的知見が足りない段階では、ロックダウンや、特定の業界への営業自粛要請をせざるを得ないのはありうることです。ただしその場合でも、医学的、科学的に確実だというわけではない予防的な措置であることを明確に伝える必要があります。それが予防的な措置だとしたら、社会はそれを前提に、不利益を被る業界に対する補償等もきちんと配慮すべきだからです。ここで重要なのは、科学的に不確実だということは、政治家ではなく、科学者でないと分からないという点です。ところが、科学者というのは、自分の説に固執するあまり、確実と言いがちです。そう言えば感染拡大が早く抑えられると思ってそう言いたくなる気持ちは、同じ科学者としてわかります。しかし社会のための科学・医学という立場を通すためには、対策の提言を行うに際しては不確実性がある予防措置だとはっきりと断った上で、公平性に関わる論点が残ることも含めて政治家にボールを投げるべきだと思います。今回は残念ながらそれが必ずしも明確に示されていなかったために、法学的な議論にも影響を与えていると思ったので、「判例時報」で指摘しました。憲法学者のなかには、あの原稿を読んで、そのことに明確に気づいてくれた人がいて、法律的な議論が進んでいます。じつはその前に、著名な憲法学者が、科学的に「確実」なら無補償でもやむなしと発言していたのです。しかし私は科学者なので、「確実」であるわけがないことがわかっていました。だから、法律雑誌でそう指摘したのです。将来のパンデミックでは、そこがうまくゆくことを願っています。
このように、科学的な因果関係が十分に証明されていない段階で、社会に重大な不利益を及ぼす可能性があるということで規制措置を講じることを予防原則と言います。じつはこの予防原則に関する議論が、日本では不十分なのです。公衆衛生などの科学だけでなく、法学などの社会科学の領域でも予防原則に関する議論や認識が、ヨーロッパほど盛んではありません。そのあたりを整備しないと、政府が発動する予防措置に国民も納得できないでしょう。
瀬名:特措法によって地方自治体にかなりの権限が委譲されたことで、感染症予防対策に即効性、実効性が期待できるようになったと言われています。しかしその一方で、誰がどこまで決めていいのかという議論が依然としてあります。予防原則を考えると、その点がもっと問題になると思うのですが。
本堂:予防原則で特定の業界に規制をかけると、財産権に抵触してきます。日本の憲法学者や哲学者の中には、そのことに強い拒否反応を示す人たちが実際にいます。時短も、まさに財産権に係る話です。社会全体への影響を考えて、特定の業種に時短や自粛を要請する必要性がある場合もあることは否定しません。ただし、その場合にどうやって公平性を担保するかという制度設計ができていないし、そういう議論さえこれまでほとんどなされていないと思われます。そうさせている一因には、科学の不確実性ということが法学者にうまく伝わっていない現状もあると思います。
瀬名:なるほど、少しまとめると、まず科学者のあいだで議論して、感染は機械換気である程度防げるといった最新の知見から、たとえばコンサートなど、こうこうこういうやり方なら再開してもよいのではないかといった提言をする余地はあるということですね。科学者も、最初に出した自説に固執せずに柔軟な対応をとるべきだという条件つきで。
本堂:そうです。科学者の議論といってもいろいろな分野の専門家が議論する場が必要です。ときには公開の場で議論することも大切です。エアロゾル感染で言えば、医学者だけではなく、建築や空調の専門家も議論に加わらないと実りある議論にはならないでしょう。重要なのは議論する目的であって、自分の学説を主張することではありません。規制を解く範囲については、科学者の議論が活用できるでしょう。一方、社会全体の利益のために特定の人や業種に犠牲を強いる対策のオプションが出てきた場合には、それは公平性の観点に基づく別途の議論が必要であることを忘れてはならないと思います。
専門知の総合は可能か
瀬名:見解の異なる専門知を社会判断に迅速に用いる必要があると発言されています。今やまさにこの点が重要になってきていると思います。これはまさに、本対談シリーズがテーマとして掲げる総合知の課題なのですが、個別の優れた英知を総合するための工夫が未だに思い浮かびません。
それと、COVID-19がこれほど続くとは誰も予想していなかったせいで、未だに先が見えない状況に、社会全体がニヒリズムに陥っているような気がします。それで少し感染者数が減ったところで、もういいのではないかという雰囲気になっています。しかし、歴史的に見ても、パンデミックは突然消えたり発生したりします。このままでは、次のパンデミックでまた同じことを繰り返すような気がします。今回の教訓を次にどう生かしてゆくかを考えないといけない。
本堂:まさに私の研究テーマです。専門知というと科学の知識に目が行きがちですが、人文系の専門知もあります。そこでコンカレント・エビデンスという手法があります。法廷や公開の場で複数の専門家に議論させる手法です。文字どおりに訳すと「同時に起こる証言」というような意味ですね。そこでは、科学だけではなく法学のような人文系の専門知も入ってきます。法学には、コンカレント・エビデンスのほかにエクスパート・エビデンス、専門的証拠という用語もあり、裁判で専門的証拠をどう活用するかは欧米のロースクールでは専門科目の1つになっています。コンカレント・エビデンスは、病院において患者の治療方針を内科、外科、放射線科などの医師が議論し合うカンファレンスと同じことを法廷でやってみようという発想で始まったものです。専門知を使いこなす世界最大級の実践例になっています。政治家が判断を下すに際しても、同じことができるはずです。
これを社会的意思決定の場で活用するにあたって重要なことは、科学者の側から科学的知見を見るのではなく、意思決定をする側から見るということです。公平性の観点も含めて、何が社会的にベストかを考えることが肝心だからです。そのためには意思決定者が積極的に動いて専門知を使いこなしてゆく必要があります。
瀬名:コンカレント・エビデンスの有効性がよくわかりました。ただ、具体的な手法としていくつか質問があります。初期の専門家会議こそ、コンカレント・エビデンスとして機能しなければいけなかったのではないでしょうか。政府や行政には各種委員会があるけれど、専門知を戦わせて総合する場になっているとは思えません。どうしたらよいのでしょう。
本堂:まずは、委員の人選ですよね。裁判の場合は、原告と被告それぞれが推薦します。社会的意思決定に用いるなら、視点が異なる人を選ぶことでしょう。東京で開かれている医療過誤裁判では、都内の大学病院から代表を出してもらい、カンファレンス方式でやっています。議会の調査機能の一環としてやるなら、各政党が推薦する方式ですかね。従来の専門家意見聴取ではそうしていますが、それぞれの専門家が個別に意見を述べるだけで、同時に呼ばれた専門家同士の議論にはなっていない今のやり方ではだめです。いずれにしろ、学術の自立性が保てるような制度設計が必要です。
瀬名:「朝まで生テレビ」みたいでは困りますよね。
本堂:そうなんです。議論を構造化する必要があります。実際の裁判では、裁判官と弁護士の協議で決めた議題でまず専門家同士だけで話し合ってもらい、意見の一致点と相違点をレポートにして出してもらった上で、公開の法廷で議論を交わしてもらうというやり方をしています。法廷ではマイクは1本にして、マイクを持っている人だけが発言するようにもしています。
瀬名:京都大学学際融合教育研究推進センターの宮野公樹さんの著書『研究を深める5つの問い』 (注13)には、昔から言われている学際研究や異分野融合は異分野連携や協同であってほんとうの融合ではないとあります。学会ごとに世界観や自然観が異なるため、学会を越えた議論になりにくい。連携は分担であり、融合とは異なる世界観の存在を知って自分が変わることであると。西垣通さんと河島茂生さんの共著『AI倫理』 (注14)には、責任がとれないAIが異なる知のつなぎ役になればいいとあります。社会の公平性についても、AIにセカンドオピニオンを求めて公平性を図る手もあるかもしれません。コンカレント・エビデンスを活用する際にも、意見を交わす専門家が互いの世界観を認め合って、こちらの知見も活かせばこういう応用が可能ですよと言えるようになれば素敵ですよね。
本堂:AIにはブレーンストーミング的なことが期待できるかもしれませんね。異質な発想を柔軟に提案してもらえるかもしれない。そうすればメタに視野を広げられるかもしれません。異分野を融合するためには、社会の側から見るという視点が必要だと思います。自分の分野からは社会にどういう寄与ができるかを考えることで自分を相対化できれば、世界が広がるのではないでしょうか。COVID-19で言えば、公衆衛生学やウイルス学ではこうだからこれをやるべきだではなく、社会の中で公衆衛生学に何が寄与できるかという視点が大切だと思います。それは物理学でも同じで、世界を単純化して見ていることをそのまま社会に適用すべきだなどと発言したら、おかしな話になってしまいます。いうなれば市民の目線で自分の専門分野を見るということになりますが、社会にはさまざまな価値観を持った市民がいることも忘れてはいけない。だからこそ、政治的な意思決定が必要になるわけです。そのことを忘れずに、自分の専門分野が寄与できることを限界も含めて話せるようになれば、議論は良い方向に進むような気がします。
瀬名:とても参考になる意見をいただきました。われわれは、社会には多様な価値観があることを忘れがちですよね。そもそも社会はそういうものだという自覚を持った人が増えれば、多くの衝突は回避できるのではないかと信じたいです。人生観のみならず科学などの専門分野についても価値観が異なるという共通認識から話を始めることができれば、実りある議論を交わすことができるという希望をいただけたような気がします。
ところで、東北大学でCOVID-19に関して学際融合を進めてゆくにはどうしたらよいとお考えですか。
本堂:実際、現在進めている法学者との共同研究は学内のネットワークから広がったものです。COVID-19について言えば、文系と理系が集まって、公平性とか倫理といったテーマを決めて自由に議論する場が必要だと思います。それぞれが、自分の専門とは異なる視点や知見を理解した上で、考えたり発言できるようになることが重要だと思うからです。
瀬名:貴重なご意見、ありがとうございました。今回の対談がまさに、どんな人にとっても、本堂さんのおっしゃる「自分の相対化」への手がかりになるのではないかと感じました。ふたつポイントがありましたね。まず「自分の分野から社会にどういう寄与ができるかを考えることで自分を相対化できれば、世界が広がる」というお話。もうひとつは「社会的意思決定の重大な場では、意志決定する側から積極的に社会の物事を公平に見て、多くの専門知をバランスよく聞いた上で、使いこなしてゆく姿勢が大切だ」というお話でした。どちらも、人の意見をちゃんと聞いて、決定権のある人はしっかり自分で判断して、そして特別な意志決定者だけでなく、科学者であっても一般市民であっても自分自身が変わってゆくことこそが何よりも重要だ、というお話と感じました。
いくつかの本を思い出しました。まずエクスキュルとクリサートという人が書いた動物行動学の古典的名著、『生物から見た世界』です。同じ街角の風景を見るのでも、私たち人間とイヌやネコではまったく違った光景が目に映っているのだと説いて、認識の不思議さを示した本ですが、私たち人間同士でも、実はいろいろな価値観や道徳観に縛られていて、同じ光景を見ていても見え方がぜんぜん違っている。そのことを前提とした上で、それぞれの専門知を出し合わないと学際にはならない。この対談シリーズでも何度か言及したのですが、道徳哲学者のジョシュア・グリーンが「私たち人間はみな道徳部族(モラル・トライブズ)だ」と言っているように、世のなかにあるたくさんの学会もまた、それぞれ道徳部族なんですよね。だからこちらの学会では常識の知見でも、あちらの学会では思いもつかないといったことが多い。それどころか、価値観や道徳観が違うからしばしば衝突してしまう。
でもお互いにわあわあ言い合っていただけではだめで、そこで司会進行役と議長が重要になってくる。そこに就くべき人は、上がってくる意見が科学的に正確かどうかを判断できるだけではだめで、一部の知り合いや業界だけに有益になるよう配慮するといった人間関係に流される人もだめで、社会的公平性や社会倫理の観点に立つ人である必要がある、ということだと解釈しました。そういう会議が実現できれば、意志決定がなされたとき、司会進行役や議長だけでなく、実は会議に出席した全員が「自分を相対化」して、新しい見方を自分のなかに取り込んで、以前と比べて「変わって」いる。
意見を求められて参加する専門知の側からすれば、解決に向けて複数のオプションを提示できる体制を整えておくことも大切だと思いました。小松左京さんの『日本沈没』でとても印象的なくだりがあります。いよいよ日本が沈没するとわかったとき、財界最重鎮の老人が京都の山荘に〝賢人〟ともいえる学者を3人集めて、数日徹底的な議論をさせるんです。これから日本はどうすればいいか、そのプランをまとめてくれと。1973年版の映画では首相役の丹波哲郎が山荘に訪ねていって結果を聞く。賢人たちは3つの封筒を差し出すんです。ケース別に3つの案に分けたと。けれども、本当はもうひとつ意見があって、全員それに傾きかけた、というんです。
「つまり──何もせんほうがいい、という考え方です」と教授のひとりがいうんですね。一億一千万の日本民族が全部滅んでしまった方がいい、という意見です。丹波哲郎はこの言葉を自分で呟いて、つーっと熱い涙を流す。映画版では最大の見所のひとつです。
ここでは日本国民を助けるにはどうすればいいか、という課題からも飛翔して、何か人間が人間を相手に膝を割って人間そのものについて話している、あるいはどうしようもない災害を起こす大自然と私たち人間が、互いの未来の姿はわからないけれど、直接時空を超えて語り合っている、そういう一種の愛情表明のように思えてくる場面なんです。
この場面はCOVID-19を経たいま、改めて私たちの心に響くように思うんですね。賢人たちは3つのプランを用意して封筒に入れて提出した。どれを選ぶかは受け取る側にかかっている。でも、もうひとつ意見がある、何もせんことだ、と賢人たちはいうわけです。新興感染症だって、どんな対策を講じようと、たとえば第一次大戦時のスペイン・インフルエンザのように、何年か経てば自然に収まるものです。どうしてパンデミックが収まるのか、そのメカニズムはいまなおわかっていません。だから「何もせんことだ」と主張するのもありなんです。もちろん、日本以外の国ではなおも感染拡大が続いていますから、これは日本だけの問題ではない。ただ日本に限っていうと、いま現在、感染は(いったん)収まりつつあるように見えます。「ほらみろ、何も策を講じなくたって、なんとかなったじゃないか」という意見もあるでしょう。「あんなにマスクをつけて予防に励んだり、家に籠もって自粛していたのがばからしくなった」と思う人もいるかもしれません。「専門家は何も役に立たなかったじゃないか」と虚無感に駆られたり、怒りを覚えたりする人もいるでしょう。
けれども、だからといってそれを表面的に受け入れて、ニヒリズムに陥ってはいけない。丹波哲郎のように涙を流した上で、首相としてプランを受け取り3つの封筒のうちどれかを選ぶ──私たちは今後もそんな局面をきっと繰り返しながら生きてゆくのだと思います。
そのためにまず「自分を相対化」できるようにしておく。これがひょっとすると、私たちひとりひとりにできるいちばんの防疫策なのかもしれません。
*注
(1) 瀬名秀明、鈴木康夫『21世紀インフルエンザ』(文春新書、2009)
(2) アルフレッド・W・クロスビー『史上最悪のインフルエンザ』(西村秀一訳、みすず署書房、2004、2009)
(3) 2021年8月27日にオンラインで記者会見を開き、世話人2名、賛同者31名の名で「最新の知見に基づいたコロナ感染症対策を求める科学者の緊急声明」を発表した。
(4) 本堂毅「感染症専門家会議の「助言」は科学的・公平であったか―科学者・医学者の行動規範から検証する」『世界』2020年8月号、pp.75-83、2020
(5) 本堂毅「コロナ禍社会における法的問題(8)―コロナ禍での財産制限にかかわる科学的知見の不確実性」『判例時報』2464号、pp.118-120、2020
(6) T. Hondou, Economic Irreversibility in Pandemic Control Processes: Rigorous Modeling of Delayed Countermeasures and Consequential Cost Increases, J. Phys. Soc. Jpn. 90, 114007 (2021) [8 Pages]
(7) 河北新報ONLINE NEWS https://kahoku.news/articles/20210812khn000039.html
(8) 気体中に浮遊する微小な液体または固体の粒子と周囲の気体の混合体をエアロゾルという。エアロゾル粒子の形状、流形などはきわめて多様。
(9) 1995年制作のハリウッド映画。主演はダスティン・ホフマン。
(10) 毎日新聞の報道によると、厚生労働省は10月29日までにホームページを更新し、エアロゾル感染を認めた。https://mainichi.jp/articles/20211029/k00/00m/040/294000c
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
(11) 河合香織『分水嶺―ドキュメント コロナ対策専門家会議』(岩波書店、2021)
(12) Andy Stirling, “Keep it complex”, Nature, 468, 1029 (2010).
(13) 宮野公樹『研究を深める5つの問い―「科学」の転換期における研究者思考』(ブルーバックス、講談社、2015)
(14) 西垣通、河島茂生『AI倫理-人工知能は「責任」をとれるのか』 (中公ラクレ、中央公論新社、2019)
(2021年10月8日取材、11月19日記事作成)
(編集責任:東北大学広報室特任教授 渡辺政隆)
本堂 毅(ほんどう つよし)
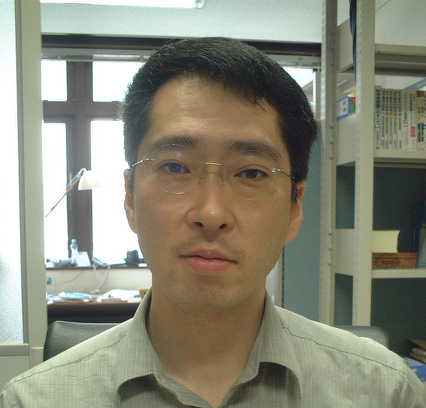
1965年生まれ。東北大学大学院理学研究科准教授。東北大学大学院情報科学研究科を修了。京都大学基礎物理学研究所研究員などを経て現職。その間、文科省在外研修員としてフランス・キュリー研究所へ留学。専門は理論物理学(統計物理)、生物物理学、科学技術社会論など。法廷には、科学と社会の「ボタンの掛け違い」が典型的に現れる場所として関心がある。音楽家、政治学者、医師、法学者など、多くの人と共同研究を楽しんできた。一番の趣味は仕事の題材でもある音楽。
瀬名 秀明(せな ひであき)

1968年生まれ。作家。東北大学大学院薬学研究科博士課程在学中の1995年、『パラサイト・イヴ』で第2回日本ホラー小説大賞を受賞しデビュー。1998年、『BRAIN VALLEY』で第19回日本SF大賞受賞。東北大学大学院工学系研究科特任教授(2006~2009)。小説のほか、『パンデミックとたたかう』(共著=押谷仁)、『インフルエンザ21世紀』などの科学ノンフィクションもある。小説『この青い空で君をつつもう』『魔法を召し上がれ』『小説 ブラック・ジャック』などでは、新しいジャンルにも取り組んでいる。
(肖像写真 佐々木隆二氏撮影)
渡辺 政隆(わたなべ まさたか)

1955年生まれ。サイエンスライター。日本サイエンスコミュニケーション協会会長。文部科学省科学技術・学術政策研究所(2002~2008)、科学技術振興機構(2008~2011)、筑波大学広報室教授(2012~2019)を経て、2019年より東北大学広報室特任教授、2021年より同志社大学特別客員教授。進化生物学、科学史、サイエンスコミュニケーションを中心に、『一粒の柿の種』『ダーウィンの遺産』『ダーウィンの夢』『科学の歳事記』などの著作のほか、『種の起源』(ダーウィン著)、『ワンダフル・ライフ』『進化理論の構造』(グールド著)など訳書多数。