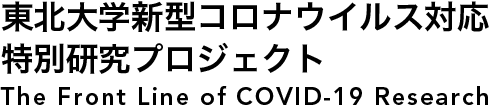PEOPLE
インタビュー
人に寄り添う――宗教人類学からのアプローチ
新型コロナウイルス感染症が収束の決め手を欠いたまま第4波の感染拡大に至り、死者の数も確実に増えています。日本で死がこれほど万人の身近に迫っているのは、第二次大戦後初めてのことではないでしょうか。看取りや、死者の尊厳という問題も深刻になっています。人々のストレスも高まると同時に、緊急事態慣れなどという言葉も聞かれます。死と向き合わざるをえない状況に、私たちはどう対処すべきなのでしょうか。今回は視点を変え、宗教人類学者の木村敏明教授と瀬名秀明さんに語り合っていただきました。
(2021年4月22日にオンラインで収録)
瀬名:宮城県・仙台市が独自の緊急事態宣言を発令し、これで3度目となりました(注1)。新型コロナ感染症は未だに収まる気配がありません。1回目の緊急事態宣言では、人流の7割減を目指した東京でその効果があったといわれました。しかし今回はさほど減っているようには見えません。街頭インタビューでも、人々は慣れや疲れを口にしています。
2回目の緊急事態宣言はいったん3月に解除されたのですが、宮城県や仙台市はちょうど東日本大震災から10年という節目だったこともあって、人の移動や接触の機会が増え、おそらくはそうしたことを含む複合的な原因から感染者数が一気に来て増大して、3月31日には新規陽性者が200名という過去最大の数になってしまいました。前回の、石井正先生(注2)との対談の後のことでした。東北の医師会からも「戦後最大の危機」という言葉まで出ました。そこで全国に先駆けて独自の緊急事態宣言が出て、「まん延防止等重点措置」も布かれたのですが、やはり最初は混乱と不安が広がりました。やがて陽性者数も減少して、「戦後最大の危機」はさすがに言いすぎだったわけですが、病床がほぼ埋まって逼迫する時期もあり、医療従事者の皆さんが置かれている緊張状態は変わっていないと思います。この連載にもご登場いただいた小坂健先生が、宮城県では医療側の情報発信者の代表となるかたちで、いまも毎日のようにテレビのニュースにリモート出演なさっています。全国的にもいくつかの変異株が確認されて、新たな局面に入ってきています(注3)。
こういう現状を鑑み、今回は宗教人類学を専門とする木村先生のお考えをお聞かせいただきたいと思い、お願いしたしだいです。先生は、東日本大震災の後、被災した東北大学関係者に学生によるインタビューを実施し、『聞き書き震災体験―東北大学 90人が語る3.11』(高倉浩樹・木村敏明監修、新泉社、2012)という本を出されていますね。それと、『不平等生成メカニズムの解明』(佐藤嘉倫・木村敏明編著、ミネルヴァ書房、2013)という本も出されている。大震災被災者へのインタビューを実施していたり、不平等生成についてもご興味をお持ちだとは知りませんでした。
それについてもお聞きしたいと思いますが、まずは今の宮城の状況、日本の状況をどう見ていますか。

木村 敏明教授
木村:私は医師でも感染症の専門家でもなく、インドネシアを中心に宗教人類学を研究してきました。ただ、以前からインドネシアでしばしば感染者が報告されていた鳥インフルエンザに関心があって、瀬名さんの『インフルエンザ21世紀』(文春新書、2009)は出版後すぐに読みました。新型インフルエンザのような感染症が社会に広がった場合にはその拡大抑制のために社会的文化的側面を考慮することも大事だと以前から考えていたからです。現状分析については、感染症専門家の話を聞くしかないわけですが、地震のように比較的短期間で破壊的影響が広がる災害と比べ、感染症はゆっくりと持続的に影響が及んでいくため、社会や個人の反応の仕方も地震の時とはだいぶ違うなと感じています。
災害は天罰?
瀬名:著書で書かれているように、先生がフィールドにしているインドネシアは多宗教の国で、しかも大地震に見舞われています。そういうインドネシアから逆に日本を見ると、どういう感慨を抱かれていますか。
木村:多様な宗教の人が暮らしていますが、国民の85%はイスラムの信者です。社会学者の世界的ネットワークがほぼ5年ごとに実施しているワールド・バリュー・サーベイ(世界価値観調査)では、70~80ほどの国が参加して同じ質問項目に答えます。その質問の1つに、「あなたの人生にとって宗教は重要ですか?」という質問があるのですが、インドネシアはイエスと答えた割合では世界2位で99%(1位はエジプト)でした。日本は下から2番目(最下位は中国)です。その意味で宗教観に関しては日本とインドネシアは対照的な国と言えます。
フィールドにしているスマトラは2004年に大地震に見舞われました。特に大きな被害を受けたアチェでは、20万を超える死者が出てしまい、大きな穴を掘って集団埋葬をせざるをえませんでした。その後集団埋葬地は記念公園となり、そこには今にも襲いかかろうとしている大きな波の形をしたモニュメントが設置されています。津波で亡くなった方々の埋葬地に津波のモニュメントを建てるという感覚は私たちにはちょっと理解しにくいのですが、アチェの人たちは、津波は神が起こしたもので、津波の大きさはアラーの偉大さの反映だと信じています。また津波の犠牲者はジハードで亡くなった戦士と同じ英雄(シャヒード)扱いをされている。いつまでも悲しんでいてもしかたない、英雄として天国に召された人たちなんだと、家族は悲しみつつも、神様の下に召されたのだからと語っています。10周年の際に訪れたら、伴侶を失った人たちの再婚ブームになっていました。そういう宗教、社会のあり方が印象的です。日本では、なんでこんな目に合わなければいけなかったのかと答のない疑問にさいなまれている被災者も少なくありません。それに対してアチェの人々の中にはこのような宗教の教えにとりあえずの心のなぐさめを得ている人が多くいるように感じます。
瀬名:津波で亡くなった方が英雄になるというのは、日本人には理解しにくいですね。2008年に中国の四川省で地震があって6万8000人が死亡しました。そのとき、女優のシャロン・ストーンさんがカンヌ国際映画祭の会場で、地震は中国政府のチベット政策の「報い」だと発言して大炎上し、中国から総スカンにあいました。日本は神風攻撃のパイロットを英雄に祭り上げましたが、今は死者を英雄扱いすることにはためらいがあるような気がします。災害を神の偉大さや天罰に繋げることはどうなんでしょう。火山噴火や地震などの自然災害を神の意思に繋げる背景は何でしょうか。
木村:自分たちの理解を超え制御できない力を何らかの超越的存在と結びつけて説明することは時代や文化に関わらず行われてきたことです。ポイントは、ご指摘の通り、そのような説明の内、社会的に受け入れられるものと受け入れられないものがあるという点です。2010年に西スマトラ州で大地震があったとき、インドネシアの新聞のコメント欄に投稿された24時間分のコメントを分析しました(注4)。そこでも、堕落した街だから天罰を与えられたという書き込みは大炎上しました。日本でも、東日本大震災の折に石原慎太郎都知事が津波は「天罰だと思う」と発言して物議を醸しました。震災直後のまだ多くの被災者が苦しみの中にいる時点で自分が神の立場に立ったかのような高所からの解釈が批判を浴びるのは、どちらの国でも同じことです。一方、一神教の伝統の下では、偉大な神は隔絶した存在です。そういう文化の下では、偉大なる神の意図は人間に理解できないものとしてブラックボックス的な扱いとなります。それに対して日本の多神教的伝統のもとでは、災厄をもたらす神が想定されて、なぜこんなことをするのか、どうすればやめてもらえるのかについて様々な解釈が生まれうる。感染症では、疱瘡(ほうそう)やはしかなどの感染症について、疱瘡神、はしか神などが信じられ祀られていました。江戸時代には、疱瘡に感染した子供の枕元に祭壇を作り、神が好きな赤いものを備えることで喜んでお引き取り願うという儀礼が行われていたことが知られています。疱瘡で亡くなった人を疱瘡神として祭って、守ってもらうという信仰もありました。神々や死者を身近に感じ、その神々との交渉の中で病に対処しようという風土が日本にはあったのです。

瀬名秀明さん
瀬名:疱瘡神の祭壇の話は驚きですね。赤い色は神様が好きな色とは知りませんでした。むしろ、追い払うための嫌がる色、厄除けの色かと思っていました、赤べこがそうであるように。今年は丑年でしたから、年賀状では赤べこの図柄が多用されましたね。実はぼくも使いました。
木村:地方によって解釈のちがいはありますが、疫病神様の好きな色で静かにお引き取りいただくという所もあります。敵対するのではなく、身近な存在としてイメージしていたのです。大島健彦の著書『災厄と信仰』(三弥井書店、2016年)を見ると、そのような疫病神の身近さがよくわかります。疫病神様が書いたという反省のお詫びの証文が遺っている例もあります。
宗教者の寄り添い
瀬名:宗教と信仰ということでは、東日本大震災がきっかけで、臨床宗教師の活動が注目を浴びるようになったそうですね。被災地である仙台に住んでいながら、うかつにもこれまで知らなかったのですが、そのことをお話しいただけますか。
木村:詳細は藤山みどりさん(『臨床宗教師―死の伴走者』高文研2020年)や鈴木岩弓先生の著作や論文にゆずりますが、東日本大震災後に仙台市の公営の火葬場で、仏教、神道、キリスト教、新宗教など特定の宗教・宗派を超えて協力して行ったボランティア活動がきっかけになっています。葬儀などをあげて死者を適切に送ることが困難な中で、希望者に読経や祈祷などの儀礼を行ったり、「心の相談室」と銘打った相談カウンターをおいて様々な困りごとの相談にのったりしていました。そういった中で、日本の宗教的風土にあった形で、欧米のチャプレンのように社会貢献や心のケアを行う枠組みを作れないかという発想が生まれたのです。ポイントは欧米のチャプレンが特定の宗教、特にキリスト教の教えを前提に信者をケアするものであったのに対し、日本の習合的な宗教風土では教義を離れてケア対象者の死生観によりそったケアが求められるということです。当時の主要メンバーであった現東北大学の谷山洋三先生(注5)を中心に、傾聴を中心としつつ、宗教的な要素を取り入れた心のケアの仕組みが作られるとともに、そのようなケアを実施する「臨床宗教師」の養成の取り組みが始まりました。
瀬名:それは東北大学を中心とした取り組みなんですか。
木村:震災の翌年に東北大学に臨床宗教師を養成する「実践宗教学寄附講座」が開設されました。特定の宗教に偏らないためにも中立的な国立大学が中心となった意義は大きかったと思います。今は他の大学にも広がっていて、臨床宗教師協会という組織もあります。臨床宗教師が常駐している病院もあって、東北大学附属病院にもいます。
瀬名:新型コロナウイルス感染症にも携わっているのでしょうか。
木村:臨床宗教師の活動は傾聴が中心で、移動傾聴喫茶「カフェデモンク」などで、心のケアを必要とする人たちに寄り添い、コミュニティの再生や孤立した人たちを繋ぐ手助けをしてきました。新型コロナウイルス感染症では、寄り添う、繋ぐという活動が難しい状況です。各地で工夫して奮闘されていますが、患者への接触ができません。ただ、医療従事者への心的ケアをしている人もいらっしゃいます。
医療従事者のケア
瀬名:新型コロナウイルス感染症の話に近づいてきました。東北大学の看護学の朝倉京子先生がされた調査でも、精神健康(メンタルヘルス)の状態が悪化して離職したいと思った看護師さんが多くなったという結果が出ています(注6)。ぼく個人としては、新型コロナウイルス感染症を抑え込むために奮闘している押谷仁先生や小坂健先生のような方々への強い風当たりを憂慮してきました。2020年の3月から5月頃にかけて、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議や分科会の委員による情報発信が逆に、感染症対策を牛耳っていると受け止められて、委員に対する人格攻撃が始まりました。そして人々の経済的困窮がそれに輪をかけました。そういう批判に慣れているはずとはいえ、やはりあの時期は感染症専門家の誰もが、心に傷を負うこともあったのではないかのではないかと心配しています。当時の専門家会議が発展的解消を遂げて分科会になった後、押谷先生はほとんどまったくといっていいほどメディアに登場しなくなってしまいました。ただ、2020年春の厳しい状況だった頃、本学の宗教学の木村先生と電話でお話をされたとうかがっていました。押谷先生とはいつ頃からのお知り合いですか。どのようなお話だったのでしょうか。
木村:2017年2月にインドネシアのバンドン工科大学で、東北大学主催の環境学シンポジウムがあり、そこでご一緒したのが最初です。東北大学のインドネシア関連の研究者が参加したシンポジウムでした。その年に、押谷先生の「ヒューマンセキュリティ特論」という授業にゲストで呼ばれ、心、死生観、宗教の観点から安全の話をしました。
それで、去年の4月初め頃、押谷先生から突然電話があったのです。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況の理解には宗教や死生観の問題が欠かせないという話でした。それ以前の印象では紳士的で穏やかな人でしたが、あの時は日本社会全体で緊張が高まっていた時期で、押谷先生も緊張しつつ、使命感に燃えているという印象でした。またそんな状況の中で、宗教が重要だ、専門家の意見が聞きたいという発想をもった視野の広さには驚きました。
瀬名:ちょうど最初の緊急事態宣言が出た直後頃ですかね。東京からの電話だったんですか。
木村:そうです。歴史に学ぶことの重要性、文化や死生観の重要性ということを押谷先生の側からおっしゃって、専門家の意見をうかがいたいということでした。押谷先生の方から疱瘡神の例をもちだして、疫病を神として祀るということの背後にどのような宗教観、死生観があるのかということを質問されました。そこで私の方では、一神教における正義の神に対して、日本の宗教伝統では神の性格が両義的なものと考えられる傾向にあるといった話をしました。
瀬名:最近出版されたばかりの、ノンフィクション作家、河合香織さんの著書『分水嶺 ドキュメント コロナ対策専門家会議』(岩波書店、2021)の冒頭に、押谷先生が出てくるんですよ。2020年の年末に仙台の東北大学に帰ったとき、医学部近くに建つ「疱瘡神」の石碑に手を合わせた、と。押谷先生は15年ほど前から講義で疱瘡神を学生にも紹介していたそうで、「日本は疫病を神として崇め受け入れることで鎮めて」きた歴史がある、と著者の河合さんにも語っています。押谷先生はここで宮﨑駿監督のアニメ『もののけ姫』も引き合いに出しているので、上面だけをぱっと見ると押谷先生が批判に耐えきれず、宗教にかぶれてしまったような印象を受ける読者もいるのではないかと思うのですが、押谷先生の思いはもう少し深いところにあったような気がするのです。
2020年5月末に開催された押谷先生の緊急オンライン学内セミナー(注7)では、宗教的な問題を話していたことが印象的でした。あのとき、日本人の心のあり方を知ることが疫学対策上重要だという思いがあったのでしょうね。それは木村先生との会話があったからなのではと思っていましたが。
木村:というよりも、押谷先生ご自身のこれまでの現場での経験から、そういう勘がはたらいていたのではないですかね。カトリック国のフィリピンをフィールドにしてきた経験があったのではないかと思います。私は、情報は提供しましたが、押谷先生も小坂先生もそれ以前から文化的な重要性を理解していました。

木村 敏明教授
瀬名:なるほど、『分水嶺』の冒頭部の読み方は、そこで変わると思いますね。国ごとの文化に合わせて最善の対策があるように、日本でクラスター対策が効力を発揮できる背景には、国民の行動に宗教的な共通基盤も一部あるからではないか、そうした分析はグローバル化が進みすぎた現代において、きっと今後のよりよい社会作りを目指す指針になるのではないか、ということだったのではないかと。たんに「withコロナ」のひと言では表現し切れない、もっと深い文化。
宗教学の観点も取り込むことで、国民へのメッセージをもっと切実に伝えられるのではないか、またそういう道を東北大学の先生といっしょに模索して確かめることで、押谷先生はひょっとすると自らも鼓舞して、壊れないよう奮い立っていたのではないか──と、これはぼくが作家であるための想像に過ぎないかもしれませんが。いつか押谷先生にうかがってみたいところです。
2009年の新型インフルエンザパンデミックでは、日本の死者は200人ほどだったのに対し、海外では数万人でした。今はもうすっかり忘れられていますが、押谷先生たちの奮闘はすごかったはずです。そのことを知らずに人格批判をする人たちがいる。医療従事者とその家族を攻撃する人たちがいる。心に大きな傷を負っている人たちがたくさんいるはずです。臨床宗教師はどういう心のケアができるのですか。
木村:私はあくまでも宗教人類学者で、宗教者でも臨床宗教師でもありませんが、攻撃されている専門家の話をきちんと聞いてくれる人の存在は重要です。専門家と社会との分断は昔からありました。私の研究室の博士研究者の朴炳道さんがこの2月に『近世日本の災害と宗教―呪術・終末・慰霊・象徴―』(吉川弘文館、2021)という本を出しました。その中ではしかの神様を描いた錦絵「はしか絵」の分析をしています。いくつかのはしか絵では、芸者、魚屋、てんぷら屋、豆腐屋、料理屋、髪結いがはしか神に怒って殴りかかろうとしている絵があります。それを、薬屋と医者がなだめている、職業による社会的分断があったようです。医者たちには同情的ではなく、金もうけをしているんじゃないかという見方があったのでしょう。感染症が拡大して不満が高まってくると、対立もおきやすい。
瀬名:そういう不満が高まると、医療従事者とその家族は汚れていると見なして拒否したがる心理が働くのでしょうねえ。専門家という立場から公衆衛生の正しい方策を実施しているのに、市民の実情、経済状況が見えていないという不満もあるのかもしれません。専門家は身近な存在ではないので、寄り添えない存在として人格攻撃につながってしまう。
木村:病や死に近い現場で働く人々をケガレた存在とする見方は現在でも見られるものです。葬儀業者や家族がそのような見方で差別をされるという話はしばしば聞かれます。感染症の場合、それに実際のウィルス感染も関係してくるので、ケガレのイメージはより鮮烈になってしまうのでしょう。問題は根が深いです。それが差別につながるのは困った問題です。また、おっしゃる通り、専門家と社会の距離というのは現代社会の大きな問題です。
コロナ疲れと心の支え
瀬名:昨年に比べて今の状況をどう思いますか。変異株が出てきて危機感を訴える国民も増え、ロックダウンに近いことをしたものの、死亡者の数もどんどん増えています。最初に述べたように、ついに第4波が到来し、一部の大都市圏でまたも緊急事態宣言が出されようとしています。個々の都市の中でも、大阪、東京、仙台など、人々の感じ方に差が出ています。大阪はたいへんな状況です。それでも街に出ている人はわりといる。そういう人にテレビの記者がインタビューすると、「(自粛や感染症対策に)疲れてしまった」といった発言があります。緊急事態であることを忘れて日常生活を送りたいという気持ちにシフトしているように見えます。地震や津波ならば、発生時に出た大きな被害で最初は混乱しつつも、ケアする見通しを立てられるわけですが、コロナではそうはいかない。先行きがよくわからないので、問題を先送りしてしまおう、なかったこと、見えないことにしてしまおうという心情になっているようにも見受けられます。そういう、社会が1つになっていない中で、宗教にはどんな役割が果たせるのか。精神性、ストレスをどう考えていけばよいかわからない状況の中で、これまでとはちがうフェイズに入ったような気がします。
木村:今回のパンデミックでは、地域による分断、個人ごとの考え方、振舞い方のちがいが顕在化しています。宗教の側も、旧来の宗教教団は、1つの教団の傘の中に信者を囲い込み、同じような教えを説き、同じような儀式や祭りを執り行うことで救われていくというやり方でした。しかし近代化が進む中で、そのような宗教のあり方はすでに存続が困難になってきていました。個々の人々が自分なりの人生を追及していくようになると、救いの姿も人ぞれぞれになっていきます。どういうふうになりたいか、何が幸せか、何が救いなのかも考え方が変わっていく。従来の宗教のあり方が人々のニーズに応えられないということが起こってきていました。その中で、宗教に代わって、欧米では、NRBS(not religious, but spiritual)という言葉が使われるようになっています。信じている宗教はありますかと問われ、そう答える人が多くなっているのです。宗教教団を超えたところに、人々のスピリチュアルなものを追求する動きが広く見られます。宗教を信じていない人でも、自分たちの心の支えとして、自分を超えた大きなもの、生命とか命、ご先祖様、かつての国家みたいなものに仮託して、生きる意味、理由を考えていくという気持ちが誰にでもあるからです。かつてはそれを宗教がすべて担っていたわけですが、今はそうではありません。人々のスピリチュアルなニーズにいかに応えていくかが問題になっているのです。
瀬名:なるほど。宗教の側も困難に直面しているわけですね。
木村:ええ、ただしその一方で、宗教には、何千年も前から人間のスピリチュアルな問題に応えてきたという長い伝統があります。昔からそういう議論をしてきた伝統の重みがある。なので、人々のスピリチュアルなニーズを教団の傘の下に収めることはできないことを前提に、宗教伝統が培ってきたさまざまな知恵を現在に活かす道がありえます。宗教教団というのは信者を囲い込む存在ではなく、対話の相手をしている存在になっているという意見もあります。スピリチュアルな問題を考えたい人が、仏教やキリスト教、イスラムの伝統に触れたり、語られてきた蓄積を読んで考えたり、宗教者と対話をすることで自分の人生を深めていく。宗教伝統は対話の相手になっているというのです。臨床宗教師は、まさにそれをやろうとしているのではないでしょうか。従来の宗教は、信者へのサービスをして見返りを得て存続してきました。そうではなく、社会に開いて、社会のさまざまなスピリチュアルなニーズや疑問に応えることが、宗教伝統にとっても、社会にとっても幸せなことなのではないかと思われるようになっているのです。それは、今回のパンデミック以前も以後も変わらないことだと思っています。
瀬名:とても示唆的なご意見でした。心の支えということでは、たまたまセネカの『人生の短さについて』(光文社古典新訳文庫、2017)という本を読みました。NHK Eテレの「100分de名著」という番組で知ったので手に取ったのですが、ローマ時代の哲学者が、よりよい生き方を説いた本ですよね。その中に、政治抗争に巻き込まれて島流しにあっていたとき、そのことを嘆いている母親を慰める手紙の話が出てきます。若い哲学者が、質素な暮らしが好きなのに政治的な問題に巻き込まれて不安でしょうがないという相談に対して、セネカは、学問に没頭しろ、虚飾にまみれた事柄で人生を浪費するのではなく、自分のほんとうの時間を取り戻せば短い人生も長くなると説いています。それって、スピリチュアルな対話として読めます。宗教ではないけれど、どこか宗教的、スピリチュアルな感じがするし、何千年も昔の哲学者であるメンターを相手に対話していると思えば、心も落ち着く気がします。
木村:なるほど、そういう読み方もできますね。
瀬名:寄り添う、繋ぐと簡単に言いますが、どうすればうまく寄り添えるのかは難しいですよね。ブレイディみかこさんは『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社、2019)という本で、寄り添うという言葉にはシンパシーとエンパシーという2つの言葉がある。シンパシーは自分と同じ立場や考えの人に寄り添うことで、エンパシーは自分とはちがう考えの人の心を推し量ってその人のためになることをすることだと言っています。この本がヒットしたので、日本ではシンパシーとエンパシーの話が近頃急速にいろいろなところで語られるようになりました。この2つのバランスが大切という意見は昔から、精神医学や動物行動学、徳倫理学などいろいろな本に書かれていて、ぼくも以前からそうした本を読んで「ああ、とても大切な視点だ」と感じて、ときどき小説にも書いてきたのです。
ただ、この問題は難しいところも孕んでいて、たとえば寄り添う側のシンパシーに行き過ぎてしまうと共感疲労に襲われてしまってストレスがたまりかねません。エンパシーの側だけにいくと、身近な人への愛情が薄れた人のように感じてしまいます。そのことを切実に感じている今日この頃なんです。その中間として、コンパッションという言葉があります。仏教学者のジョアン・ハリファックスの『Compassion(コンパッション)――状況にのみこまれずに、本当に必要な変容を導く、「共にいる」力』(英治出版、2020)という本には、共に苦しむコンパッションには、良い方にも悪い方にもころがる可能性があるが、良い方にころがせば、リーダーだけでなく一般の人たちも元気づけられると書いてあって納得しました。このバランスを、臨床宗教師や宗教学者はどうお考えなのでしょうか。
最近は編集者から、読者に寄り添ってとよく言われます。とくに若い読者は共感を求めているので、主人公に共感できる小説は評価が上がる、売り上げも上がるからというのです。実際、最近は書店に行くと、平棚の本の帯やPOPに「共感度100%」とか「共感度1位」といった宣伝文句が踊っています。しかしそれだけで本の良し悪しが判断されてしまうのは危険なのではないか。共感ばかり追い求めると、共感できない人を排除してしまいかねないからです。たとえばスマトラで地震が起こっても、遠く離れた自分には共感できない。共感の重要性を強調し過ぎると、共感できない相手に対しては、自分たちさえ安全ならいい、自分たちさえ感染しなければいいということになりかねません。
ここで思い出されるのが、2017年上半期の芥川賞の選考結果です。台湾に生まれて、ほどなくして日本へ越してきて育った作家が書いた、台湾の人々の生き方をテーマに書いた小説が候補になったのですが、ある委員が選評で「これは、当事者たちには深刻なアイデンティティーと向き合うテーマかもしれないが、日本人の読み手にとっては対岸の火事であって、同調しにくい。なるほど、そういう問題も起こるのであろうという程度で、他人事を延々と読まされて退屈だった」と書いたのです。当の候補作家はこれを読んで、やるせない怒りを表明しました。これはシンパシーである共感、同調の問題ですね。自分とはちがう他者の気持ちを想像して味わうはずの文芸の世界でも、このように「共感」できたかどうかが賞の当落に大きく関わっているのが現実です。私たちはどのように考えればよいのでしょう。
宗教学で、対話の相手との距離の取り方、共感の仕方にコツがあるなら教えてください。
木村:おもしろい問題提起です。共感とは何かという問題は、19世紀の後半に近代宗教学が成立して以来ずっと宗教学者たちを悩ませ、議論されてきたものです。信者さんたちにインタビューしていると時々「信じていないあなたに何がわかるんですか」と言われることがあります。この場合、理解することは相手と同じ宗教を信じ、一体化することを意味します。果たしてこれは研究として適切なのか。一方で、相手の宗教の世界に一切共感をもたず、それは有害であり阿片であると主張する宗教批判もあります。しかしそれで宗教をわかったことになるのか。信者とまったく同じ気持ちにはなれないし、宗教を信じる人はだまされているかわいそうな存在という見方でも、宗教の意味はわかりません。その間はありうるのか? 明瞭な答はありませんが、自覚的にその間に立つことが重要だとされています。シンパシーとエンパシーの間ということを言語化しておくことが大事なのです。オウム真理教のときのような苦い反省もあります。自分の立場を理解しつつ、周囲に批判してくれる人の存在も大事なのです。臨床宗教師にも、メンターの存在が重要で、定期的に研修会に参加して、互いに報告し合って相互チェックをしています。対象に入り込みすぎない、そこから背を向けてしまわないためには、それが大事なのです。
瀬名:宗教では、集会が重要な行為ですが、現在は集まることができないですよね。韓国の教団でクラスターが出てしまった、教会で賛美歌を歌っていてクラスターが出たなど、集会が危険を伴う行為になっています。日本人は宗教を信じていない人が多いのに、祭りやハロウィンなどが大好きです。集まらなくてもスピリチュアルなケアをすることが重要なのか、オンラインでメンターと対話するのもありなのか。これからの時代、どうなっていくのでしょう。
木村:集まることは宗教にとって本質的で重要なことです。宗教抜きでも、人間にとって重要なことです。近代化が進む中で、自分自分の幸福を追求するようになってきました。かつては地域の祭りなどが心のよりどころでしたが、そういうことが苦手な人も増えています。私自身がそうでした。その一方で、オンライン、リモートで、同じ嗜好の人が集まりやすくなっているということもあります。これまでも、交通通信技術の発達に伴い、集まり方の様態も変わってきました。この4月に大学に入学した私の娘は、サークル活動でオンラインでコーラスの練習をしています。今の若者は、高校を卒業して離れ離れになっても、ラインなどを通じてつながりを持ち続けるようになっているようです。そういうのを見ても、集まりのあり方は変わっても、集まるという本質は続いているのだと実感できます。宗教がそれにどう対応するかは、これから見ていくしかないと思っています。
死者への敬意と看取り
渡辺:ジョルジオ・アガンベンというイタリアの哲学者が、新型コロナウイルス感染症のせいで、たくさんの人が肉親に看取られることもなく、葬儀もなしに埋葬されている現状に懸念を表明し、炎上しました。現在の日本では、自宅待機で孤立したまま亡くなっている人が増えています。その一方で、そういう人をおもんばかる想像力を欠いた人が浮かれていたりします。想像力をはたらかせている人ほどストレスを抱えています。死が身近に迫っている状況をどう生きていくべきなのでしょうか。
瀬名:仙台医療センター・ウイルスセンター長の西村秀一さんも、ごく初期のころから、ご遺族が新型コロナに感染した死者と顔を合わせることもできない状況を、とても憂いていらっしゃいました。
木村:看取りと葬儀をめぐる問題は深刻です。イスラムの教義に則った正式な葬儀ができないインドネシアでは日本以上に大きな社会問題となっています。見舞いや看取り、遺体の扱い方ではどこまでが危ないのかという客観的な情報を公開して、適切な看取りや葬儀ができるようにすべきです。感染症に限らず、葬儀のあり方が問われています。かつては共同体で執り行ってきた葬儀に専門業者が入ってきて、共同体から葬儀のやり方が失われ、葬儀会社は核家族向けのサービスに特化し、共同体は参加しなくなってきました。葬送文化がやせ衰えてきたのです。無縁社会の中の葬儀のあり方が問われる中で今回の感染症が襲いました。お通夜なしの1日葬や直葬が増えています。そのことを後で気に病む人も多いのが現状です。合理主義に立った葬儀の簡素化ではなく、葬儀文化がやせ衰えた結果の簡素化で問題が出ているのです。そこに新型コロナウイルスが追い打ちをかけました。
渡辺:一人ひとりの死生観も問われているのではないでしょうか。
木村:死生観は、時代と共に変わってきました。文学研究科の佐藤弘夫先生の『死者のゆくえ』(岩田書院、2008)などの優れた研究がありますが、今日私たちがもっている家を中心とした死生観の基本は、江戸後期に始まって明治で固まったものです。明治以降は戦争で多くの戦死者が出る中、国民国家の英雄としてそれらの死者を祀るという新しい文化も生まれました。一方、戦後の高度経済成長に始まってバブル経済終了からその後までは、死者が少なかった時代です。家制度や地域社会がゆっくり解体していく中でそれまでの死生観はしだいに色褪せていきましたが、そのことが問題とはなりませんでした。それが今、高齢多死社会が到来し、日本人が再び死とは何か考えなければならない時代が来ています。新型コロナウイルス感染症がなくてもそういう時代になっていました。
不公正感と不信感
瀬名:ストレスの元ということでは、冒頭で紹介した『不平等生成メカニズムの解明』という本で、不公正感の出現のしかたが考察されていました。インドネシアでは、多様性のある文化がそれを生み出しているというご意見ですよね。いま日本でも、この不平等感、不公正感に根ざした不満が一気に噴出している状態なのではないかと思うのです。テレビの街頭インタビューでも、「どうせ政府や行政の人たちも多人数会食しているんだし、自分たちだけ真面目に自粛するのは損だ」と、不公正感に基づくコメントをする人がとても多い。『不平等生成メカニズムの解明』の終盤には、前々回の対談でご登場いただいた大渕憲一先生も論考を書かれていて、世の中のミクロな不公正感とマクロな不公正感について論じています。自粛を守っている人が、守っていない人に不公正感を感じている。ここにどう対処してゆくか。この観点からの対策や取り組みもありかなと、読んでいて思ったしだいです。
木村:ストレスフルな時代には、ちょっとしたちがいに犯人捜しをする風潮が出てきます。専門家に対する不信感にも、それがあるかもしれませんね。
瀬名:歌人の俵万智さんの歌集『未来のサイズ』(KADOKAWA、2020)に、「自己責任、非正規雇用、生産性 寅さんだったら何て言うかな」という歌が載っています。実はこの作品は、まだ新型コロナウイルスが見つかる前の2019年7月に、寅さん50年を記念して、俵万智さんが山田洋次監督に見せるためにつくった新作の歌だったんです。寅さんのテレビ特番で紹介されて、ぼくもその当時知ったのですが、新型コロナのパンデミックが続く今読むと、受ける印象がまったくちがう。非正規雇用を増やした効率化社会の不平等と新型コロナウイルスが結びついて、社会の歪みが表出している。そういうところから社会を問い直すフェイズなのかなという気がしてきました。そういう意味で、この対談シリーズにも意味があると思えます。
渡辺:寅さんを価値判断の基準に置くというのはいいですね。
木村:インドネシア人なら、そこで「アッラーなら何て言うかな」というところでしょうが、日本人にはやはり「寅さん」ですかね。
瀬名:最後に、これも冒頭で紹介した、先生がまとめた『聞き書き震災体験』という本に関連して。震災体験を記録として残すことに価値があることに異論はありませんが、それをどのように分析して次に活かしていけばよいのでしょうか。新型コロナウイルス感染症では、聞き取り調査をしなくても、SNSにすごい量の情報があふれています。人文社会系では、そういう記録の解析に具体的な考えはあるのでしょうか。
木村:あのとき記録した理由は、消えていくことを恐れたからです。激甚被害地ではない仙台で起きたことについては特に、忘れられることを懸念しました。このように記録をしておけば、テキストマイニングなど分析の技術が発達すれば、それを用いた解析が可能になります。その一方で、私が専門とする宗教人類学では、量的なテキスト解析とは別に、個々人の生き方や声に耳を傾けるミクロな視点に立った手法を重視します。あの記録で学んだのは、同じ災害でも個々人の置かれた状況によってそのインパクトの大きさやあり方、日常への復帰の仕方は全く違っているということです。それを明らかにするためにも、エスノグラフィー的手法は有効だと思っています。
瀬名:ぼく個人のことでも、この1年で感情の起伏がありました。このような対話を通じて、新しい発見や学びも現に体験しています。津波や地震のような一過性の大事件とは別に、長く続くストレスの中での気持ちの揺れを追うミクロな視点は、おっしゃるように大切なことだということがわかります。
最後に、押谷先生、小坂先生など、疫学や感染症の最前線で奮闘している人たちに、宗教学者としてできることは何か、またふつうの人たちに対してかけられる言葉もあれば教えてください。
木村:いわゆる人文社会科学の研究者として、押谷先生、小坂先生が重視されている死生観や歴史の意味を考え、社会に伝えていきたいですね。最近、人間は複数の時間の中を生きているとつくづく思います。私たちがものを考えたり、決断したりする場合、数日くらいの今すぐ成果が表れる単位の話と、数か月後、1年後、10年後、もっと先を見据えた話では自ずと違ってくるのではないでしょうか。どれを大切だと考えるかによって考えにずれが生まれ、仕事に対する評価もちがってきます。そこが難しいですね。長期的な視点で感染症を抑え込むことと、1日単位の話ではかみ合わないことも多いと思います。ストレスが強い中では、人は長期的な時間に目を向けることは難しい。ただ、感染症の問題も、私たちが過去から受け継いだ命を未来につなぐといった長いスパンのいわばスピリチュアルな時間の単位で考えることが重要だと考えています。
瀬名:たしかにセネカにも、精神的な時間と物理的な時間を使い分けることが大事だと書いてありました。札幌市立大学学長でAI研究者の中島秀之さんも、「虫の視点と鳥(神)の視点」という概念をよく引用紹介されています。川のほとりで水の流れを見ているのと、上空から川の流路を見るのでは、物事の見方が自ずとちがってくる。西欧では鳥や神の視点を重視して客観的な考え方を尊ぶことが多いようだが、日本人は虫の視点で物事を見ることが多い。AIの設計にもそうした東西の視点のちがいを応用して取り入れてはどうかというお話でした。どちらがよい、どちらが悪いではなくて、両方の視点の使い分けが大切なんですね。それが心に安らぎと余裕をもたらすこともある。たしかに、目の前のことを見ている視点とは異なる、時空間を超えた視点を持つと人生の見方が変わるかもしれないですね。「スピリチュアル」という言葉を嫌がる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回のお話は大学における知のあり方としてとても心に響き、感慨深いものでした。ありがとうございました。
*注
(1)その後、2021年4月25日から、東京、大阪、兵庫、京都に緊急事態宣言発令。
(2)石井正教授との対談「災害医療としての地域パンデミック対応」を参照
(3)2021年5月末日現在では、国内の新規陽性者数は減少しつつあるものの、重傷者数は減らず、10都道府県に緊急事態宣言を発令中。
(4)木村敏明「地震と神の啓示―西スマトラ地震の事例から」『東北宗教学』vol.5,2010年
(5)「【TOHOKU University Researcher in Focus】Vol.008 生と死を支えるスピリチュアルケア ―公共的な存在としての臨床宗教師―」を参照。
(6)
「新型コロナウイルス感染症流行下における看護職の精神健康ケアの必要性増 看護職の約4割が新型コロナによる離職意向を示す」を参照。
本対談後、東北大学災害科学国際研究所の臼倉瞳助教らが実施したアンケート調査により、COVID-19対応にあたった宮城県保健所職員も(医療従事者と同じくらい多くの割合で)不眠症や精神不調などメンタルヘルスの問題を抱えていたこと、また電話相談応対業務の中で困難を感じていたことが明らかとなり、医療従事者のみならず保健師や事務職員らへのストレスケアの重要性も示唆された。詳細は「COVID-19対応に追われる保健所職員のメンタルヘルス 新型コロナウイルス感染症に関する電話相談に対応する保健所職員の約7割に不眠症状、半数近くに精神不調」を参照。
(7)「緊急オンライン学内セミナー(講師:押谷仁教授)を開催しました」を参照
(2021年4月22日取材、6月1日記事作成)
(編集責任:東北大学広報室特任教授 渡辺政隆)
木村 敏明(きむら としあき)

1965年生まれ。東北大学大学院文学研究教授。東北大学大学院文学研究科修了。弘前大学人文学部講師、ハーヴァード・イェーンチン研究所客員研究員などを経て現職。 専門は宗教人類学、インドネシアの社会と宗教。編著書に、『聞き書き震災体験-東北大学90人が語る3.11』(監修、新泉社, 2012年)、『不平等生成メカニズムの解明―格差・階層・公正―』(編著、ミネルヴァ書房, 2013年)がある。
瀬名 秀明(せな ひであき)

1968年生まれ。作家。東北大学大学院薬学研究科博士課程在学中の1995年、『パラサイト・イヴ』で第2回日本ホラー小説大賞を受賞しデビュー。1998年、『BRAIN VALLEY』で第19回日本SF大賞受賞。東北大学大学院工学系研究科特任教授(2006~2009)。小説のほか、『パンデミックとたたかう』(共著=押谷仁)、『インフルエンザ21世紀』などの科学ノンフィクションもある。小説『この青い空で君をつつもう』『魔法を召し上がれ』『小説 ブラック・ジャック』などでは、新しいジャンルにも取り組んでいる。
(肖像写真 佐々木隆二氏撮影)
渡辺 政隆(わたなべ まさたか)

1955年生まれ。サイエンスライター。日本サイエンスコミュニケーション協会会長。文部科学省科学技術・学術政策研究所(2002~2008)、科学技術振興機構(2008~2011)、筑波大学広報室教授(2012~2019)を経て、2019年より東北大学広報室特任教授、2021年より同志社大学特別客員教授。進化生物学、科学史、サイエンスコミュニケーションを中心に、『一粒の柿の種』『ダーウィンの遺産』『ダーウィンの夢』『科学の歳事記』などの著作のほか、『種の起源』(ダーウィン著)、『ワンダフル・ライフ』(グールド著)など訳書多数。