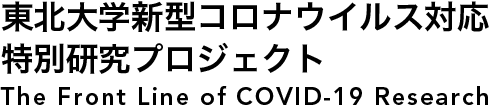PEOPLE
インタビュー
専門家の枠を壊す総合知は東北大学建学のキーワード
新型コロナウイルス感染症対策では、感染症対策の専門家と政治・行政、市民との関係のひずみが生じています。リスク管理における専門家の役割、政府のガバナンス(統治)のあり方、市民の行動はどうあるべきなのか。科学哲学、科学技術社会論が専門の野家啓一名誉教授と瀬名秀明さんに語り合っていただきました。
(2020年12月11日に安全に配慮したうえで収録)

対談風景
瀬名:今回は、東北大学が擁する多様な専門家の知を総合する作業の第3回目です。第1回は、新型コロナウイルス感染症感染防止対策にあたっている小坂健先生、第2回は、専門家や政府のみならず市民どうしでも攻撃的な言説が出ている背景について大渕憲一先生にお話を伺いました。
東京都は11月以降、過去最高の感染者数を記録し、全国的にも感染者数は急増中で、医療現場はひっ迫しています。大阪と北海道では自衛隊に看護師派遣要請が出ました。宮城県でも毎日20名あまりの感染者が出ています。
9月下旬にGo Toトラベルが始まり、東京発着のGo Toが解除されたのを皮切りに、移動が活発になったあたりから空気が変わったような気がします。勝負の3週間と言いつつ、Go Toに参加する人が増えています。政府は経済重視と言っていますが、感染拡大を憂慮する専門家との認識のずれが出ています。
9月以降、「専門家」を糾弾する論調の本も出版されました。たとえば漫画家の小林よしのりさんらの『新型コロナ―専門家を問い質す』(光文社、2020)という本などです。そのほか、「専門家」と呼ばれる人の、マスク不要を唱える本も出ています。2009年の新型インフルエンザ・パンデミックのときも、2011年の福島第一原子力発電所事故のときも、「専門家」への不信感が噴出し、信頼感が失墜しました。そういう動きについて、野家先生はどうお考えですか。日本はどう対処すればよいのでしょうか。
トランス・サイエンスの正念場
野家:第一波のときは、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の発信力が強かったように思
います。その後、新型コロナウイルス感染症対策分科会になり、経済など他分野の専門家も加わったわけですが、専門家の科学的知見と政府の政策決定とのあいだにずれ、軋轢、齟齬が出てきています。そこに、一般国民もいらだたしさを感じているように思います。
科学の専門家という存在を考える機運を呼び起こしたのは、科学技術社会論(STS)という研究領域によってです。特にSTS学会を立ち上げた小林傳司さんが2007年に出版した『トランス・サイエンスの時代―科学技術と社会をつなぐ』(NTT出版ライブラリーレゾナント)という本がひとつの節目になりました。

野家啓一名誉教授
トランス・サイエンスという概念は、アメリカの核物理学者で科学行政官でもあったアルヴィン・ワインバーグが1972年に提唱したものです。当初は「領域横断科学」と翻訳されたこともありましたが、今はそのままトランス・サイエンスと呼ばれています。
かつては、事実判断は自然科学が、価値判断は人文社会科学が受け持ち、時代状況や価値観の対立を調停しながら結論を導けばよいという状況でした。ところが、公害や原子力発電などの社会問題では、事実判断と価値判断が微妙に交錯しています。感染症予防にあたる公衆衛生の分野でもそうです。そのように、事実判断と価値判断を分離できない状況をトランス・サイエンスと呼びます。STS研究者の平川秀幸さんは、「科学なし/だけ問題」といううまい表現をしています。「科学なしでは解けないが、科学だけでも解けない問題」というわけです。さまざまな社会問題には経済格差、差別、偏見なども絡まってくるせいで板挟み状況となるような問題です。
20世紀後半から、トランス・サイエンス的な問題がどんどん増えてきています。科学者からなる専門家委員会と、政府の政策判断をどう調整すればよいのかという問題もそうです。調整するためのルールが決まっていない。そのせいで、政府は及び腰、決断が遅いなどの不満が噴出してくるのです。
瀬名:トランス・サイエンス自体、概念としては新しいものではないのに、解決策は見えていない、解決の試みが深まっていないのが現状ということでしょうか。
野家:そうです、まさにSTSの正念場といえる状況です。イギリスでは、1990年代に牛海綿状脳症(BSE)をめぐる混乱で専門家に対する信頼が揺らぎました。専門家の委員会は、BSEが人に感染する可能性はきわめて低いと提言しました。ところがその後、人への感染が判明したことで、専門家委員会と政策決定した政府の両方に批判が出たのです。しかし科学には、完全に白か黒か断言できない不確実性の部分があり、そこから引き出す結論にはさまざまな状況判断が絡んできます。人に感染する可能性はきわめて低いという提言は、不安におびえる国民にすれば畜産業界への忖度と映ります。それに追従した政府も批判の的になりました。
福島第一原子力発電所事故でもそれと同じで、当初は「原子力村」と揶揄される専門家の楽観的意見があり、政府の方針が二転三転しました。そういうことへの批判は出たのに、これを解決する方策、社会装置が整備されませんでした。専門家と政府をつなぐサイエンスコミュニケーション、リスクコミュニケーションの社会装置が日本には用意されてこなかったのです。
渡辺:イギリスでは、BSE騒動を徹底的に検証し、政府の科学顧問の役割などの見直しを行いました。今回のイギリスの新型コロナウイルス感染症対策では政策が二転三転しましたが、専門家と首相からはその都度明確なメッセージが発せられていました。

瀬名秀明さん
瀬名:そうなんですよね。日本では検証してその結果をその後の政策に反映させるということがない。それと、これは第2回の大渕先生との対話でも問題にしたことですが、日本特有の問題として、世論が弱者をスケープゴートに仕立てる傾向があります。
2005年、高病原性鳥インフルエンザが問題になったとき、発生した関西の養鶏場をマスコミが叩き、創業者のご夫妻が自殺してしまいました。2014年のSTAP細胞事件では、優秀な研究者がやはりマスコミの過熱報道に耐えきれず自殺してしまうという、あまりにも不幸な事態へと至りました。外国ではそういうことで自殺者が出たような例は聞いたことがありません。
今回、当初、政府は専門家の意見を聞きませんでした。クルーズ船で集団感染が出たことで専門家会議を立ち上げ、指針を募るようにはなりました。しかし、専門家と政治家、行政とのあいだで軋轢があり、提言がゆがめられたりした。そこで押谷仁先生たちがやむにやまれず発信するようになったわけですが、逆に批判の矢面に立たされてしまった。すべてを専門家が決めているという誤解を招く結果になったからです。それで、他の専門家も入れた分科会に発展的解消されることになりました。正直な話ぼくは、世間の攻撃もすさまじくて殺伐となった3月、4月には、専門家会議や厚生労働省クラスター班から自殺者が出るんじゃないかと心配していたほどです。
専門家会議のメンバーの方々が御用学者だったとは思いません。尾身茂さんはいまも分科会の代表としてマスコミに出て発表なさっていますが、バランスの取れた判断をする人だという印象をもっています。ただ、三密、夜の街などの言葉が独り歩きし、8割削減というキャッチコピーが先行して、まだ精緻な数理モデルではないのに、極端な政策を促しました。提言が極端な政策につながるという、メリハリのない対応を招く結果となりました。
野家:私も専門家会議が御用学者だとは思っていません。ただ、8割削減は、専門家としては踏み込んだ発言でした。政策決定は、あくまでも政府の責任です。注意を促す警告だったのに、スクリーニングにかけられず生のまま社会に出てしまったことで、それを鵜呑みにした人たちが混乱し、批判が出たのでしょう。そのあいだをつなぐ社会的仕組みがないと、とんでもないことになる好例です。
ドイツのメルケル首相は、旧東ドイツ出身で移動の自由のなかった時代を知っていることから、それを制限することに関して苦渋の決断を下した胸の内を訴え、評価されています。それに対して日本の首相は、全国一律休校を突然実施したほか、宮城県知事は9月入学まで言い出しました。前もって教員や教育問題の専門家の意見を徴(ちょう)することなしにです。専門家と政策決定のバランス、両者をうまくつなぐ回路がないのが現状です。日本の政治家が説得的なメッセージを発することもなかった。コミュニケーションがなっていません。きちんとした政策決定の道筋がないことを国民の前に露呈してしまったのです。これでは国民は納得できません。
専門家とは誰か
瀬名:専門家のあいだで方向性を決めるのが原則なはずなのに、今回に限らず、いろんな「専門家」がいろんなことを言い出しました。「この人がいま新型コロナウイルス感染症を語るのにほんとうに相応しい人物だろうか」と思ってしまうような「専門家」もテレビで繰り返しコメントしました。専門家、科学者による情報発信が重要だというのはサイエンスコミュニケーションの原則で、原発事故の頃よりもそのことは浸透していますが、新型コロナウイルス感染症では、それが裏目に出ている面もあります。たとえば、死者が42万人になると言ってしまった西浦博さん。ノーベル賞学者の山中伸弥さん、本庶佑さんも。山中さんは、感染症については素人と断っていましたが、ファクターX説をだして、世間に広めてしまいました。要因はひとつではないだろうと何度も念を押していたのは好感がもてましたし、純粋な科学的探究心の発露からの発言、指摘だったことは理解できますが、結果的に「日本人は重症化しにくいから大丈夫」という油断を人々に促してしまったように思います。本庶さんは、生きものと免疫学の専門家という自負を抱きつつ、PCR検査拡充の必要性を広めました。そのなかでやや強引と見える場面もあったように感じました。西浦さんも優れた研究者だと思いますが、「42万人」発言はさすがに行きすぎだったのでは。
科学者のあいだでコンセンサスがまったくとれていない状況はあからさまです。一般人から見ると、「専門家」の見分けはつきません。誰がその状況においてほんとうの「専門家」なのか判断できない。そのため、十把ひとからげの批判になりがちです。政策決定者も、どの専門家の意見を聞くべきか判断に迷ってしまいます。「専門家」の立ち位置について、野家先生はどのようにお考えですか。
野家:個々の専門家は、あくまでも特定の領域の専門家です。それを科学全般に通じたジェネラリストとして処遇することで齟齬が出るのです。原発事故のときは、科学者集団のワンボイス(統一見解)が必要という意見がありました。しかし、たとえば今やり玉にあげられている学術会議にしても、ワンボイスの取りまとめには即応できません。多種多様な専門家がいるわけですから、ワンボイスを出せという要望に応えるのは難しい。かといって、個々の専門家が自分独自の見解を言い出したら収拾がつかない。ほしいのは、複数の選択肢でもよいから、根拠を説明できる科学者共同体の意見の集約です。
一方、マスメディアからは、それぞれが抱え込んでいる「専門家」のワンボイスしか聞こえてきません。本来なら、複数の声を伝えるべきです。「専門家」は特殊な素人にすぎないという認識が得られていないせいです。そこのギャップが埋まっていないことが問題です。
社会的な問題を、専門家の見解を聞きながら多様な市民が論じ合うコンセンサス会議という市民参加のテクノロジー・アセスメントがあります。あるコンセンサス会議に参加した化学者が、自分はこの化学物質のミリグラム以下のレベルの振舞いでは世界有数の専門家だが、何トンもの量が社会にまき散らされたときの影響はわからないと発言するのを聞いたことがあります。
瀬名: この話題に関連する本で、『我々みんなが科学の専門家なのか?』(ハリー・コリンズ著、法政大学出版局、2017)と、その続編『専門知を再考する』(ハリー・コリンズ/ロバート・エヴァンズ著、名古屋大学出版会、2020)があります。そこでは「専門家コミュニティの中では誰が専門家かはわかる」と書いてあります。しかし、そこじゃないだろう、こっちから言わせてもらえば、外部の人間からはわからないじゃないか、だから社会は困っているんだ、と言いたいです。

渡辺政隆特任教授
移動の自由に対する意識の違い
瀬名:なるほど。ただ、難しいですね。メルケル首相はもともと物理学者なので状況判断に長けている、スピーチもすばらしい、と高く評価されていましたが、残念ながらドイツはいまも感染が抑えられていません。科学がわかるから正しい決断ができるとは限らないということなのか、あるいはスピーチがいくら見事でリーダーシップをアピールできたとしても、実際の政治の舵取りはそれ以上に難しくてうまくいかないものなのか。
メルケル首相の演説とも関係しますが、ドイツやフランスなどでは、マスクをしない自由とか移動の自由を求めるデモなどが行われているのを見て、あちらでは「自由」という概念が重要であることを改めて感じました。哲学者の國分功一郎さんと社会学者の大澤真幸さんの対談『コロナ時代の哲学』(左右社、2020)などを読むと、ロックダウンの危なさをここまで問題にするのかと思ってしまいます。
自分が行きたいと思うところにいつでも行けるのはいちばん基本の自由なんだ、そこを抑圧するロックダウン政策は自由の基本を奪うものだ、というのですが、ぼくには正直なところそこまで強くこだわる理由がうまく理解できない。公衆衛生の概念もヨーロッパ発祥ですよね。もちろん、高齢者でも自分の足で自由に街を歩ける社会はすばらしいと思いますし、歩行支援ロボットの開発や社会インフラの整備は大切ですが、感染症対策としての一時的な移動制限がほんとうにどこまで人間の「自由」を奪うものなのかわからないのです。
確かに戦前は、医学的知見が成熟していなかったため結核の患者さんを隔離し差別するという歴史もあり、差別をなくすことは大切です。しかし、いま現在、たとえ移動制限されてもほとんどの国では戦時中のように言論抑圧されているわけではないし、リモートで人と話す自由もある。心理的に塞いでしまうマイナス面とは慎重に向き合う必要がありますが、適切なカウンセリングを受けられる社会支援制度もそれなりにあるはずです。そんなに人間の「自由」とはやわなものなのか。自由への道は別の方向でいくつも残されているように思うのですが、どうして哲学では移動の自由をここまで重視するのか。公衆衛生とは相反する、そこの擦り合わせはどうやってきたのでしょうか。
野家:西ヨーロッパ諸国では、基本的人権としての移動の自由が憲法や法律で認められています。それは王権と闘って勝ち取られたものです。そのため、自粛ではなく、法律で決めないとロックダウンはできません。移動の自由の制限は立法手続きでやらなければいけないという考えが根付いているのです。それに対して日本は行政判断、いうなれば空気でやっています。日本には行動制限の法律がないし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)にもそうした条項はないからです。
瀬名:日本でも立法化したほうがよいのでしょうか。
野家:それは難しいでしょうね。感染症のようなものから社会を防衛するにあたっては、立法化ではなく、空気で済ませる風潮が根付いていますから。ただし日本の自粛は、個人判断に任せるという意味では民主的なのですが、その反面、「自粛警察」を生んでしまっているし、下手をすると戦時中の隣組のような「相互監視社会」を生み出しかねない。
瀬名:自由に関して、立法を基盤とする欧米と、空気で決めてしまう日本の違いが明確に出たということですね。しかしそのせいで、8割減のときは自粛したものの、自粛に疲れてしまい、感染拡大もさほどではなかったせいで、自粛しなくてもいいんだという空気がしだいに支配的になりました。そこにGo Toが発動され、空気を一気に変えた。自粛なんかしないぞという同調圧力に振れてしまいました。ほどほどな自粛というところでは止まらずに。
野家:100から0まである自粛のどこをとるかが曖昧だからですね。かといって、法律で自由を制限することにも問題が多い。「自由」という概念は、明治にできたものです。江戸時代までは「勝手気まま」「自由放埓」という意味だったのに、海外から入ってきたfreedomやlibertyという言葉に「自由」という訳語をあてたことで混乱が続いているのです。ヨーロッパでは王権からの「自由」、アメリカではイギリス支配からの「自由」が骨身に浸み込んでいます。フィラデルフィアにあるリバティ・ベル(自由の鐘)がその象徴です。日本では市民革命がなかったので、自由は外から与えられたものであり、譲ることのできない「自由」に対する思い入れがありません。そこが、立法化か自粛かの違いを生んでいるのかもしれません。ところが、落としどころがあいまいで、自粛の範囲を明確にしていないことが混乱を招いているのでしょう。科学者に8割削減といった警告を発せさせるのではなく、政府がきちんと判断して責任を果たすべきなのです。
リーダーシップとガバナンス
瀬名:分科会の尾身さんが11月に深夜の会見を開き、「経済を回してくれという声が強くて、政策決断の舵がそっちに切られがち」とか「中央と地方、省庁間でのガバナンスが問題になっている」と発言したのは本音だったと思います。
今回のパンデミックでは、東京がエピセンターになりました。原発事故や地震のときはそうではありませんでした。2009年の新型インフルエンザでさえ、東京は直撃を受けたわけではない。ところが今回は首都である東京がまず危機に直面した。ここがこれまでの災害と決定的に違うところだったと思います。エピセンターになった東京のメディアが最初にオタオタし出した結果、東京の恐怖感が地方に蔓延しました。ところが感染が地方に広がったときには、東京の空気はすでに冷めていました。
野家:東京や大阪への一極集中がマイナスに働いた結果ですね。東京での判断が全国に適用されてしまいました。Go Toには省益も関係しています。菅首相も政治基盤が脆弱なのでリーダーシップが取れず、ガバナンスが右往左往しています。政治システムの弱点が露わになってしまいました。この3月にフランスのマクロン大統領が、「われわれは今(ウイルスとの)戦争状態にある」と言ったことには、国民の団結を促す意味があったのでしょう。戦争にたとえると専制政治礼賛につながりかねないのでどうかと思いますが、空気に頼る日本の首相は、説明責任を果たさず、ガバナンスのなさを露呈しました。政治学者の丸山真男が言ったように、日本の政治は誰も責任をとらない「無責任の体系」なのです。総合的に判断し、経過を見ながら方針を変更していくということをしない。
瀬名:小池都知事が都庁やレインボーブリッジを赤くライトアップしたのは、まさに「空気」を作る仕掛けだったといえますね。それと、政治家が専門家の意見を隠れ蓑にするような感じは、やはり良い印象がもてません。それまでさんざん「専門家の意見を聞いて判断する」と言っておきながら、Go Toの話になった途端、「Go Toトラベルで感染拡大したというエビデンスはない」と言い出す。これでは科学が政治のアリバイ作りに利用されていると取られてもしかたがない。国民は政治への信頼を失ってしまいます。海外ではどうなんでしょう。
野家:海外では、政治・行政のリーダーが明確なメッセージを発するため、責任の所在が目に見えますよね。ニューヨーク州で感染者が初めて確認された3月初旬から感染状況が落ち着き始めた6月中旬まで連日記者会見を開いて警鐘を鳴らしたクオモ知事がよい例です。
その対極がブラジルのボルソナロ大統領です。これは科学史家の田中祐理子さんから教えてもらったことですが、自らが陽性から回復した直後、彼は「私は遺憾に思う。死ぬ人もいるだろう。彼らは死ぬ。それが人生。(I’m sorry, some people will die, they will die, that’s life)」と発言したそうです。つまり、生き延びるweと死に絶えるtheyのあいだに一線を引いて分断したのです。専制的に分断を進めるそういう国がいいのか、手間がかかっても合意形成を積み重ねる社会のほうがいいのか、そこが問われています。ガバナンスやリーダーシップを強調するのもわからないではありませんが、野党までが私権を制限する緊急事態宣言を出せという動きは理解できません。分断社会では弱者や貧困層が犠牲になります。それに拍車をかけるのは避けてほしい。民主政治には時間がかかりますが、立憲民主主義の遺産を踏まえたガバナンスが大切です。
瀬名:感染症対策か経済優先かどちらかの二分法に走るのがリーダーシップではないということですね。
小林よしのりさんは、ボルソナロ大統領と同じように、日本でコロナの死者はそれほど多くない、高齢者と基礎疾患の人に限られている、そういう人たちが死ぬのはしかたない、だから経済優先すべきだと主張なさっています。小林さんなりの正義感からの発言でしょう。ご著書も売れているので支持者も多いかもしれません。しかし日本がそういう社会に傾きすぎてしまっては困る、とぼくは思うのです。自分がweの側にいるならそれでいいかもしれないですが、いったんtheyの側に入ってしまったら、社会から助けてもらえなくなる。そういう社会にはなってほしくない。最後まで他者への思いやりを諦めない社会のほうをぼくは選びたい。21世紀の倫理観では、人の命の重さ、重傷者、軽症者に関わらず命の重さは同じだったはずです。一人ひとりの命を大切にする、バランスの取れた政策決断を期待します。

野家啓一名誉教授
瀬名さんが『ウイルスVS人類』(文春新書、2020)で書いておられる、共感(シンパシー)と感情移入(エンパシー)をめぐる意見にまったく同意します。現象学者のフッサールが、「他者の認識(他我認識)」は感情移入(アインフュールング)を基盤としており、それは身体性を通じて行われると言っています。他者を認識するにはハグとか握手とかが重要だというわけです。現象学を発展させたメルロ=ポンティはそれを「間身体性」と呼び、身体性を通じたエンパシーの大切さを強調しました。倫理の根幹にあるのが、シンパンシーとエンパシーとコンパッションです。哲学者の大橋良介さんは、コンパッションを仏教用語の「慈悲」「大悲」と呼び代えています。ところが、三密禁止とかフィジカル・ディスタンスを守らなければいけない新型コロナウイルス対策では、身体性を通じた他者理解ができません。その中でシンパシーとエンパシーをどう回復すべきかを考える必要があります。
瀬名:先ほどあげた『専門家を再考する』には、専門家にも対話型能力をもつ人が重要だという記述があります。サイエンスコミュニケーションを意識しているのかもしれません。ただ、「対話型専門知に身体は必要ない」という意見には、ロボティクスの研究者からたくさんのことを教えていただいたぼくには、どうも納得できません。「社会の身体性は、専門知を築くうえでは関係ない」というのですが、どうでしょう。
大渕先生との対話で、現在は、他者に対する想像力や痛みを感じる力が発揮できない状況なのではないかという話をしました。想像力でわかる痛みの範囲が身体性だと思うからです。
野家先生がおっしゃったアインフュールングというドイツ語は、大渕先生との対話で言及した動物行動学者フランス・ドゥ・ヴァールも自著の中で紹介していて、英語では「feel into」の意味にあたると言っています。アインフュールングはエンパシーの基本であり、それはまさに他者の心に「into」して、他者の気持ちを能動的に理解することから始まるというのです。一方、こうしたパンデミック状況下では、人と人との間のフィジカル・ディスタンスをとることが対策の原則だと言われている。物理的に他者と離れざるを得ないのだから心でつながるほかないのですが、やはり人間にはそれが難しい。想像力でわかる痛みの範囲が身体性だと思うので、他者に対する想像力や痛みを感じる力が発揮できない状況が問題です。
AIやロボットのコミュニティでは、シンパシー、エンパシーをどうするかという研究が進んでいます。いま日本ロボット学会で「ロボットの法及び倫理に関する研究専門委員会」というのが起ち上がっていて 、ぼくも作家としてメンバーに入っているのですが、その集まりで、AIで「空気」を読む(ビッグデータ解析する)仕組みができないかという話をしています。「あなたは今、空気に飲まれていますよ」と、サポートしてくれる技術があってもいいのではないかという提案です。ただこれには、工学系には賛成する人が多いのですが、倫理学など人文社会系の先生は、やはり「うーん」という感じのようです。
問われているのはバイオポリティクスの真価
瀬名:第2回の対話のとき、大渕先生からノーベル経済学者リチャード・セイラーが提唱している「ナッジ」という概念のことを教えていただきました。セイラーの共同研究者である法学者キャス・サンスティーンの『ナッジで、人を動かす』(NTT出版、2020)という本がちょうど出ていたので読み、なるほどと膝を打つ思いがしたんです。「ナッジ」とは、自発的に望ましい行動を選択するきっかけを与えてくれるものなんですね。それによって道徳的な選択が促されることもあります。保険で自動更新がデフォルトだと自動更新を容認するけれど、更新しないがデフォルトだと、自動更新をあえて選ぶ人は少ない。一種のバイアスですが、どうせ人間には心理バイアスがあるのだから、それをよいほうに使おうということだと思います。本の中で、「ナッジ」とはちょうどカーナビのようなものだと説明されていました。カーナビに目的地を入力すると、最善と思われるルートを表示してくれるわけですが、運転手はそれを参考にしつつも、自分であえてルートを変更する自由も保証されている。「ナッジ」は人間の自由や尊厳、福利の制御ではなく、自由を補助する役目を担うんだ、という考え方で、先ほどのAIサポートの話はナッジに近いと思った次第です。
野家:それは興味深い考え方ですね。
瀬名:人間の判断には時間がかかるというご意見にも納得できます。ちょうど『ナッジで、人を動かす』でも人間の無意識の即断を「システム1」、熟慮しての決断を「システム2」と区別して、ナッジは「システム2」の発揮に有効と書かれているのですが、いうなれば将棋の早指しと熟考の両方をうまく使い分けられる社会にしましょうということだと思います。そのうえで、どうしても人間という生きものはしっかり考えようとするとそれなりの時間がかかることも、前提として認める必要がある。
ぼくはプライベートパイロット免許の勉強をしたことがあるのですが、飛行機の操縦士は、飛行中に事故が生じた場合、まずは高度を維持する努力をしたうえで、どこに着陸すればいちばん安全かを見極めて決断を下すというのが鉄則です。高度があればあるほど、考慮できるオプションが増えて、より安全な対策を実行できるからです。これは感染症対策と似ているかもしれません。
クリント・イーストウッド監督の「ハドソン川の奇跡」はご存じですか。
野家:いえ、あいにく見ていません。
瀬名:実話をもとに脚色した映画なんですが、その中心テーマもそれでした。旅客機が離陸早々にバードアタックでエンジン停止してしまい、機長はハドソン川への着水を決断し、乗員全員の命を救って英雄になります。レコーダーの記録によると、事故発生から着水まで208秒。ところが航空機事故調査委員会のシミュレーションでは、208秒あったならラガーディア空港に安全に戻れたはずだと結論され、公聴会にかけられます。しかし、AIはそう判断するかもしれないが、人間の判断には時間がかかる、エンジン停止から決断を下すまでの35秒間の空白を計算に入れれば、着水の選択しかなくなるはずだという機長の主張が認められるのです。この新型コロナウイルス感染症も、なんとか高度を維持しながら、同時に少しでも早く、最善の決断していく必要があるはずです。
野家:最近では効率性や経済性ばかり言われがちですが、たしかに重大な問題になるほど即断即決はできず、最適解を見出すためには「緩み」や「遊び」が必要です。近代社会はグローバル化と新自由主義で突き進んできましたが、新型コロナウイルス感染症は、一度立ち止まって熟慮する機会を与えてくれたと考えてもいいのではないでしょうか。それで判断は遅くなっても、よりよい未来が開ける方向を目指すべきです。瀬名さんも、「別の未来を構想できたときに未来が意味を持つ」とお書きになっていますよね。
哲学者ミッシェル・フーコーがバイオポリティクス(生政治)という概念を提唱しています。封建社会では王権が人々の生殺与奪の権利をもっていた。いわば「死」の政治です。それが近代以降は、人々の「生」を維持しながら経済発展を目指す方向に進んできた。そのための社会装置が学校、監獄、兵舎だった。それらを支配の方法として政府が出生率や公衆衛生、少子社会に気を配る社会の支配体制がバイオポリティクスになります。今の新型コロナウイルス感染症の事態はこの近代以降のバイオポリティクスの真価が問われているといえます。うまくコントロールできれば互いに「生」を配慮(ケア)する社会になるし、下手をすると戦時体制下の相互監視社会になりかねない。
専門知から総合知へ

瀬名秀明さん
瀬名:そこで問題となるのが、専門知をどうやって総合知にするかですね。専門知を統合してより良い決断を下すためにはどうすればよいのか。
件の小林よしのりさんも、かなり勉強したと自著に書いていますし、「総合知」が求められているとはっきり述べています。そこまではぼくと同じなんです。ところが、社会とどうやってコミットすべきかという結論部分になると、ぼくとはまったく逆の意見に達している。ぼくにとっては興味深い点で、勉強するとは何か、専門家と語り合うとはどういうことなのかと考えさせられます。ぼくから見ると、小林さんはご自分の考えとよく似た専門家を無意識に選んで話を聞き、自分がたまたま見えた範囲の経済困窮者に共感したことなどによって、意見が偏っていってしまったのではないかと感じるのですが、ぼくを含めて誰もがバイアスに嵌まる危険をもっています。
学際が大切と言われてきたけれど、もう一歩進んだ学際が必要なのではないでしょうか。総合大学として東北大学が果たすべき役割について、お考えをお話しください。
野家:科学は17世紀にデカルトやニュートンが出たことに始まります。ニュートンは自然哲学者でした。科学者(サイエンティスト)という言葉は19世紀半ばに作られた言葉です。それ以後の歴史は、かつては総合知だった科学が細分化・専門分化されてきた歴史です(「科学」という日本語は、まさに「専門分化した学問」という意味です)。哲学ですら、ひとつの学問領域になりました。すべての学問分野が蛸壺化してきたのです。思想家の吉本隆明は「井の中の蛙」であることを自覚した蛙は(無知の知)、そのことによって世界と繋がっていると言いました。
トランス・サイエンスが問題だといいますが、事実と価値のすみわけで済む問題ではありません。 解決のためには、学問的交流を進めるしかない。自分の無知を自覚したうえでの異分野との対話の推進です。それによって、アリストテレスのいう「共通感覚(センスス・コムニス)」、コモン・センスを回復することが第一歩です。
瀬名:ぼくも以前、とても学んだとはいえない程度なのですが、アリストテレスの『心とは何か』(講談社学術文庫、1999)や、アメリカ独立革命を支えたトーマス・ペインの『コモン・センス』(岩波文庫、1976)などあれこれ読んだりしました。ですが「センス」は言葉で説明するのが難しいですよね。
野家:一般に五感といいますが、決してバラバラではなく、音を聴いて色を思い浮かべるように共通部分はあります。「海暮れて 鴨の声ほのかに白し」という芭蕉の句がそのいい例です。コモンセンス、共通感覚ないしは常識を回復することを通じて総合知を築くことです。
じつは、東北大学初代総長の澤柳政太郎がそもそも目指したのが総合知でした。東北大学は理科大学から出発したのですが、当初から総合化を目指したのです。一般教養にあたる「普通教育」を設け、随意聴講科目「科学概論」の講師に田邊元を招いたのもその一環です。「余が始めて当地の理科大学に哲学の随意講義をなすべき任務を委嘱せられたのは今より五年以前澤柳政太郎先生が総長の職に居られた時である」と田邊元自身が書いています。この科学概論とは「科学哲学」のことです。したがって、科学哲学の講義が日本で初めて行われたのが東北大学でした。1913年のことです。
この年は、御存じのように、帝国大学として初めて女子大生3名が東北帝国大学への入学を許可された年でもあります。数学専攻の牧田らくが、大学では数学以外の科目も学べたことがよかった、本多光太郎の物理学と田邊元の科学概論が特にためになったと回想しています。澤柳は、専門家として縮こまってはいけない、いろいろな科目を身につけたうえでの専門家たれという理念を説いていたのです。
余談ですが、田邊元自身も、本多光太郎や物理学者石原純の講義を聴講し、『最近の自然科学』という本を出版しました。日本で最初にノーベル物理学賞を受賞した京都大学の湯川秀樹は、最初は数学に進もうと思っていたが『最近の自然科学』を読んだことで、相対論や量子論に興味をそそられ、物理学に進路変更したと、自伝『旅人』に書いています。澤柳の理念がノーベル賞の種子をまいたわけです。
そういうわけで、東北大学は創立時から進取の気風をもった開かれた大学として、総合知を目指していたのです。
瀬名:いまのお話、とても大切と感じました。改めて、この連載対話が東北大学広報のかたちで発信できていることを嬉しく思います。田邊元さんの本はぜひ読んでみたいですね。探してみます。ありがとうございました。
野家 啓一(のえ けいいち)
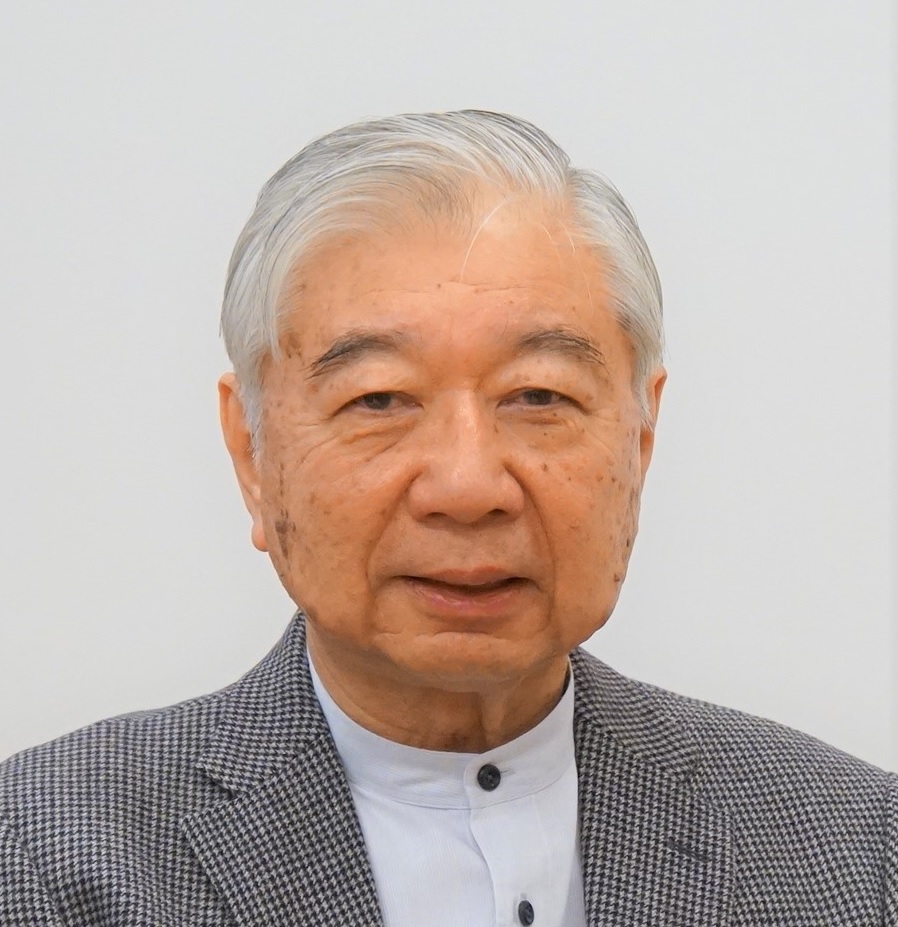
1949年仙台生まれ。哲学者、東北大学名誉教授。東北大学副学長、同大総長特命教授などを歴任。日本哲学会元会長。近代科学の成立と展開のプロセスを、科学の方法論の変遷や理論転換の構造などに焦点をあてて研究してきた。主な著書に、『言語行為の現象学』『無根拠からの出発』(勁草書房)、『物語の哲学』(岩波現代文庫)、『歴史を哲学する』(岩波書店)、『科学の解釈学』、『パラダイムとは何か』(講談社学術文庫)など多数。1994年第20回山崎賞受賞。
瀬名 秀明(せな ひであき)

1968年生まれ。作家。東北大学大学院薬学研究科博士課程在学中の1995年、『パラサイト・イヴ』で第2回日本ホラー小説大賞を受賞しデビュー。1998年、『BRAIN VALLEY』で第19回日本SF大賞受賞。東北大学大学院工学系研究科特任教授(2006~2009)。小説のほか、『パンデミックとたたかう』(共著=押谷仁)、『インフルエンザ21世紀』などの科学ノンフィクションもある。小説『この青い空で君をつつもう』『魔法を召し上がれ』『小説 ブラック・ジャック』などでは、新しいジャンルにも取り組んでいる。
(肖像写真 佐々木隆二氏撮影)
渡辺 政隆(わたなべ まさたか)

1955年生まれ。サイエンスライター。日本サイエンスコミュニケーション協会会長。文部科学省科学技術・学術政策研究所(2002~2008)、科学技術振興機構(2008~2011)、筑波大学広報室教授(2012~2019)を経て、2019年より東北大学広報室特任教授。進化生物学、科学史、サイエンスコミュニケーションを中心に、『一粒の柿の種』『ダーウィンの遺産』『ダーウィンの夢』などの著作のほか、『種の起源』(ダーウィン著)、『ワンダフル・ライフ』(グールド著)など訳書多数。