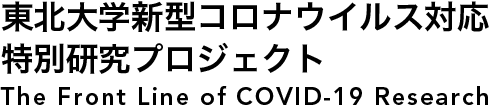PEOPLE
インタビュー
地方自治のパンデミック対応――地方行政に託される課題
新型コロナウイルス感染症は、グローバルなパンデミックであると同時に、ローカルなクラスター感染の集合体です。国の政策が迷走する中、各自治体がそれぞれに奮闘しています。今回は、行政法が専門の飯島淳子教授と瀬名秀明さんに語り合っていただきました。
(2021年7月9日にオンラインで収録)
瀬名:飯島先生が『論究ジュリスト』に書かれた論考(注1)を拝読しました。「パンデミックと公法の課題」と題した特集号で、飯島先生は「パンデミック対応における地方自治」というタイトルで寄稿されています。ぼくは薬学出身で文系には疎いのですが、今日はその関連のお話をお聞きしたいと思っています。
飯島先生は今、東北大学法学部教授と東北大学公共政策大学院院長を兼任されています。専門は行政法で、博士論文は「フランス の地方自治法研究」、今年度から公共政策ワークショップ「パンデミックをめぐる公共政策――感染症対策と地域政策」を担当されていると いう前情報だけは頭に入っています。
まず、そもそも行政法を専門にされてフランスの地方自治法を研究され、今は感染症対策と地方政策に関心をお持ちになった経緯をお 話しいただけますか。

飯島淳子教授
飯島:そこまでお調べいただいて、大変恐縮です。大学院時代は、研究者の卵として相対的な視座を獲得するために比較法研究に力を注ぎました。私が専攻する行政法は、ドイツ法の圧倒的な影響を受けていますが、行政法の母国はフランスだということもあって、フランスを選びました。フランスはナポレオン以来の中央集権国家ですが、日本に先立って1980年代から地方分権改革が進められていました。戦前の日本並みだったところがそれをはるかに追い越して分権化を進めた部分や、国地方関係において契約手法を利用するなどの独自の特徴もあります。博士論文では、こうしたフランスの1980年代改革の法理論的意義を検討し、国地方間調整法の一般理論を自分なりに描き出しました。
2003年に東北大学法学部に赴任した後、2006年から2008年にかけて、フランスのエクス・アン・プロヴァンスにあるエクス・マルセイユ第三大学で研究する機会を得ました。そこでようやく、フランスはまさに「個人と国家」なのだと肌で感じ取った気がいたします。ただ、帰国後しばらくすると、フランスで外国人として感じたヒリヒリとした痛みも薄れ、国や地方自治体の審議会などに参加する機会が増え、恥ずかしながらフランス法研究から遠のいてしまっています。
新型コロナウイルス感染症COVID-19が拡大する中で、行政法学の関与は行政学・政治学などに比べて遅れましたが、『論究ジュリスト』の特集号に地方自治法の観点から寄稿したこともあり、今年度は公共政策ワークショップで「パンデミックをめぐる公共政策――感染症対策と地域政策」に取り組むことにしました。
瀬名:COVID-19の発生は2019年暮れで、2020年から世界的な流行に至りました。日本では昨年の2月、3月に深刻な事態になり、7月には第1回目の緊急事態宣言が発せられました。現在、東京では4回目の緊急事態宣言が発せられている中でオリンピック・パラリンピック開催に突き進むという矛盾した事態の中にあります。最初に専門家会議が立ち上がった際に、東北大学と北海道大学の感染症の専門家が中心となって対策に挑みました。専門家会議は専門家分科会に姿を変えましたが、東北大学の感染症の専門家は今も感染症対策に関わっています。宮城県では、今年3月の東日本大震災10周年のときに感染が拡大しましたが、なんとか抑えられました。
公共政策大学院のワークショップ「パンデミックをめぐる公共政策――感染症対策と地域政策」は今年度からスタートしたということですが、昨年度と今年度の状況を比べてみて、昨年度すぐにではなく今年度からスタートさせた経緯と、具体的にどういうことをやっているのかを教えていただけますか。
飯島:昨年度は、4月2日に東北大学全体として、オリエンテーションや授業をオンラインで実施することが決定されたところからのスタートでした。公共政策大学院長に就任した直後から、公共政策大学院の命ともいえるワークショップをどうやって維持継続していくか、同僚とともに目の前の課題を一つ一つ乗り越えていったというのが実情です。学生間で濃密な議論を行い、現場に赴いてヒアリング調査を行うという従来のワークショップのやり方が通用しない中で、オンラインも手探りで導入していきました。
実は、ワークショップの担当者を決めるのはその前年度ですので、現実的に難しかったのも正直なところです。厚生労働省から派遣された実務家教員もいますが、昨年度は、公共政策大学院がパートナーシップ協定を結んでいる横手市のご協力を得て、地域包括ケアシステム・地域共生社会に関するワークショップを既に予定し、準備も進めていたのです。

瀬名秀明さん
瀬名:なるほど、喫緊の感染症をテーマにしたワークショップの新規立ち上げは実務的に難しかったということだったんですね。今年度の「パンデミックをめぐる公共政策」ワークショップでは、ここまでの段階でどのような議論やインタビューをされているのですか。
飯島:大きなテーマを与えたので、まず、何を問題としてどのように捉えるのかというところから始めました。学生は、グループディスカッションを通して問題意識を明確にしていく中で、広い意味での医療と経済を二本柱として課題を抽出するところから作業を進めてきました。このテーマの奥深さ、難しさと面白さを実感しているようです。そして、前期中は、仙台市の危機管理局と保健所、宮城県の保健福祉部疾病・感染症対策課、経済対策の実務担当者として仙台商工会議所にヒアリングを実施しました。中間報告会が2週間後に迫っており、学生がどういう報告をするか楽しみにしているところです。
瀬名:商工会議所のどういう方にヒアリングしたのですか。
飯島: 仙台商工会議所、みやぎ仙台商工会、仙台市が共同で実施している「仙台 感染症対策・地域経済循環プロジェクト」というものがあります。「感染防止 想いやり宣言 ST〇P!コロナ」というステッカーなどを目にしたことがあるかもしれません。このプロジェクトの担当者に話を伺いました。
瀬名:それは、繁華街の飲食店に行って安全対策のチェックをしているような方ですか。
飯島:いえ、そうではありません。店側の感染症対策だけでなく、お客さんも感染症対策をすることで、みんなで経済を動かしていこうという主旨の活動なのです。今では当然のように思われるかもしれませんが、昨年の8月という早い時期に、「地域をあげて感染症対策をする」という根本から出発し、「みんなの想いやりで経済を動かそう」という考え方に基づいてプロジェクトを進めてきたという話を聞いて、私も感銘を受けました。
瀬名:ヒアリングで主体的に質問をするのは学生だと思いますが、オブザーバーとして立ち会った飯島先生として、印象に残った質問はありましたか。
飯島:質問票を事前にお送りしてヒアリングに臨み、ご回答を受けてその場でさらに質問をするのですが、的をついた質問に対しては、かなり突っ込んだ回答をして下さることもあります。その御蔭もあって、学生は、これまで無意識のうちに国に目を向けてきたけれども、仙台市や宮城県の現実や実務を知ることで、政策を見る視点が変わったと言っています。
一歩成長した学生たちが掘り起こした課題も、私にとっては印象的でした。高齢者や基礎疾患を持つ人への感染症対策を実施すると同時に、自覚症状がないまま感染を広めかねない若者にどうやって情報を届けるかをセットにして対策を進めることが重要ではないかという課題を学生は設定したのです。同じ若者である学生がそういう問題意識を持つことには大きな意味があると思っています。
瀬名:それはいいですね。若い人たちのあいだに、ワクチン接種を躊躇する人がいたり、副反応に関する誤ったSNS情報に踊らされる人がいたりするという話を聞きますから。若者である大学院生が商工会議所の人と話す中でそういう問題意識に目覚め、仲間に情報を広げていくというのは頼もしいですね。
飯島:ありがとうございます。それはそうなのですが、別の懸念もあります。東北大学では職域接種が進んでいます。そこから漏れる人への不公平性はどうするのかという問題が1つ。もう1つは、職域内という近い距離で、ワクチン接種が事実上の強制にならないかという危惧です。特に、教員から学生への働きかけが強制につながらないように注意する必要があると思っています。接種するかどうかはあくまでも自分で決めるものですから。
瀬名:個人の権利や自由の尊重という点では、先生が研究されたフランスがすぐに思い浮かびますよね。
飯島:フランスでは、憲法上、大統領の非常事態権限と戒厳が定められていますが、新型コロナウイルス感染症対策としては、法律によって新たに衛生緊急事態に関する条項が創設されました。法律に基づいて強制的な措置がとられ、多くの訴訟も提起されているようです。対して日本では、感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)とは別に、厚生労働省が毎日のように事務連絡を発出し、その内容も融通無碍に変更していくと問題視されることがあります。日本社会に特徴的な同調圧力のようなものも、フランスにはないと思います。
瀬名:自由と権利に対する意識の違いがパンデミック対策の違いとなって表れているということはないでしょうか。あるいは、ミシェル・フーコーの言う監視社会という考え方が、市民の監視問題でよく援用されています。この対談シリーズでも、野家啓一先生が、自由に関する考え方がヨーロッパと日本では大きく異なると話されていました。自由に対する考え方が曖昧なまま輸入されたせいで、ロックダウンに関する考え方とか、過去の感染症患者の隔離政策などに表れているのではないかという提言もありました。行政法は自由平等友愛の国フランスが母国だというお話がありましたが、日本ではそれがどう反映されているのでしょう。
飯島:正面からのお答えができず、宿題にさせていただきたいのですが、瀬名さんのご指摘を伺いながら、憲法学者の樋口陽一先生のご議論を考えていました。樋口先生は、個人と国家の二極構造を描き出されました。フランスは、市民革命を通じて中間団体を徹底的に排除することで、中間団体の傘によって守られると同時にその枷によって縛られていた個人を析出し、国家と対峙させたのに対し、日本はそのような経験をくぐり抜けてこなかった。そこが、個人の尊厳に対する考え方の違いに表れているというのです。
特措法と知事への権限委譲
瀬名:話題をご専門の法律の方向に転じたいと思います。ここで、飯島先生が『論究ジュリスト』に寄稿された論文の内容について、改めて読者の皆様にご教示いただければと思うのですが、お願いできますか。
飯島:はい。この論文では、「パンデミック対応における地方自治」というテーマで、法的観点から、国地方関係、地方分権の可能性、そして地域社会・住民を視野に入れた地方自治の可能性について取り上げました。
まず、特措法上は、政府対策本部の定める基本的対処方針という一般的な基準と、政府対策本部長による総合調整という個別具体 的な関与によって、国から地方へのトップダウンのベクトルが基本になっています。ただし、特措法は、都道府県知事が実施する措置の内容を 定め切っていない、つまり知事に裁量の余地を認めています。実際、政府との交渉・調整も含めてどのような対策をとるか、各知事の力量が 試される事態が続いています。
また、地方分権の観点からは、各地方自治体が、法律の執行にとどまらず、条例、プラン・プログラム等の計画、〇〇モデルなどを作り、 独自対策を講じていることが注目されます。が同時に、地方自治体間の連携がまたしても課題として現れてしまいました。感染症対策におい ては、自然災害の場合以上に連携が難しくなることは確かですが、特に情報管理の局面で大きな問題になっています。
そして、地域社会・住民まで目を広げますと、弱者であるほど深刻な打撃を受けるという現実を前にして、福祉等の分野において共助の 実践が力を発揮している反面、誹謗中傷などの排除が深刻になっています。感染症法は、感染者の人権の尊重を基本理念として掲げ、国 民にもそれを義務付けているにもかかわらず、法律では制御できていないのです。さらに中長期的には、接触・交流・移動が抑制されるなかで 、地方創生や地域共生社会などの施策をどのように展開していくべきかについても議論していく必要があると思っています。
瀬名:ありがとうございます。最初に取り上げたいのは特措法です。ぼくも今回、初めて全文に目を通しました。この法律は、2009年に発生した新型インフルエンザ・パンデミックを教訓に、2012年に制定され(注2)、今回、一部改正が行われました。2009年のパンデミックは東北大学の押谷教授ほか多くの方々の尽力で抑えられました。この法律制定にあたっては、「緊急事態宣言」の導入など、自治体への一部権限委譲がなされ、関係者は、次はこれでだいじょうぶだろうという安心感を抱いていたと思います。しかし今回の新型コロナウイルス感染症への対応では、中央政府と地方自治体、県と市とのぎくしゃくした関係が見受けられます。特措法の制定で、地方自治体は柔軟な対策をとれるようになっていたと思っていたのですが、どうやらそうでもないらしいという気がしています。飯島先生は、行政法の専門家として、2009年以後の動きをどう見ていますか。
飯島:「2009年」以後という視点を自覚的に持つべきことを改めて教えていただき、ありがとうございます。中央政府と地方自治体との関係ということで言えば、私は、2009年の新型インフルエンザというより、2011年の東日本大震災の経験に注目していました。特措法は、危機管理のための法律をつくったというところに大きな意味があると思います。一般法である感染症法は、個々人に対する医療の提供を基本とするのに対し、特措法は、緊急事態宣言のように、社会全体に対して行動の自粛要請・制限等を行うための根拠となる法律です。 それが今回、初めて発動されました。同じ危機管理の法律である事態対処法や国民保護法と比べると、地方自治体に権限を与え、裁量の余地を認めている部分が大きいことは確かです。集団感染の発生は地域ごとに異なるので、その分、主に都道府県知事に、地域の特性に応じて裁量権限を適正に行使することが委ねられているのだろうと思います。
瀬名:地方自治体の裁量ということでは、新興感染症と自然災害では対応が異なりますよね。東日本大震災では、この対談シリーズに登場してもらった石井正先生が、石巻赤十字病院で被災し、被害者対応の陣頭指揮を執り、被害の軽かった他県などの応援を得て、一定期間で対策本部を解散させることができました。しかし新興感染症パンデミックでは、感染がいつまでもだらだらと続くうえに、他県も対策に追われています。なので特措法では自治体ごとの対策も違ってきます。そのあたりについてはどうお考えですか。
飯島:災害対策基本法は市町村中心主義、つまり、市町村がまず対応し、市町村が対応できない場合に都道府県が、都道府県も対応できない場合に国が補完していくという構造になっています。権限主体が身近な市町村であるところが特措法とは異なります。また、自然災害では被害がどちらかと言えば局所的ですので、同一レベルの市町村間の支援が効果的に働いて市町村間の連携が大きく発展したのは、地方分権の光の側面だったと言えるかと思います。それに対して、瀬名さんがおっしゃったように、COVID-19は全国的、全世界的な災疫なので、どこも自分のところで精一杯で、支援や連携が難しいという違いがあります。
瀬名:災害対策基本法では、危険な地域への立ち入りを首長が制限できますよね。それに対して特措法では、移動の制限はあくまでも要請のレベルでしかできません。同じ危機的状況なのに、地方自治体が採れる対策には、オーバーラップする部分とそうではない部分があって、そのあたりの区分けが難しいのではという印象なのですが。
飯島:おっしゃる通りだと思います。ただ、危機的状況への対応において必要とされる人的資源については、当然のことながら性格が異なる部分もあると思います。自然災害ではインフラの復旧について国が代行したり民間の土木業者に委託したりすることができますが、感染症対応では保健師や医療の専門家の比重が大きくなります。加えて、感染症については、歴史的な経緯を無視することができません。感染症法が制定される前の伝染病予防法や結核予防法の下で重大な人権侵害があったという負の歴史です。それを踏まえて感染症法が個人の人権の尊重を基本理念にしていることは、決して見失ってはならないと思います。
瀬名: 人権尊重はぼくも大賛成ですし、日本ではロックダウンのような強制は必要ないだろうと思ってはいます。ただ、3.11から10周年の行事後に宮城県で感染者が急増したのは、他県からの人流が大きな要因だったのではないかと疑っています。そういう場合、移動自粛の要請をさらに強めるような権限は知事に認められているのでしょうか。
飯島:特措法では、フェイズに応じた要請が認められているので、その範囲内での運用は知事の裁量に委ねられていると思います。
瀬名:要は、今はフェイズいくつなのかという判断しだいということでしょうか。ただ、大阪府知事のように、裁量権を発揮しすぎて批判を浴びたという例もありました。ところで、宮城県知事と仙台市長の対応については、どういう意見をお持ちですか。
飯島:東日本大震災のときは、宮城県と仙台市との関係がスムーズではなかったために対応に遅れがあったという批判もありました。今回はそれほどではないようです。やはり、石井教授のような、両者のつなぎ役が果たして下さっている役割は大きいと思います。
瀬名:確かにそうなんですが、そういうつなぎ役がいなくても、ふだんから調整をうまくやっていなければいけないのではないかというのが個人的な感想です。つなぎ役がいるからうまくいくということは、ふだんはやっていなかったのかという点が気になります。
飯島:まさにそうだと思います。平成28年の地方自治法改正によって、指定都市制度改革の一環として指定都市都道府県調整会議が設置されましたが、実際にはあまり開催されていません。よく言われることですが、互いの顔が見える関係を日常的に築いていることが危機時には特に効いてくるのだと思います。
瀬名:専門家から見た改善点があれば教えてください。
飯島:ヒアリングで伺った限りでは、やりたくないからやっていないわけではなく、感染者一人一人への対応をはじめ、目の前の差し迫ったニーズへの対応で手一杯、というのが実情のようです。データを出し惜しんでいるわけではなく、収集したデータを解析し、どのようにどこまで公表するかといったセンシティブな検討を行う態勢が整えられないのだと思います。ただ、情報管理の問題は、効率化だけではなく、情報の性質・内容やプロセス・局面に応じて切り分けて考えていく必要があるように思いますので、できれば具体的な提言につなげていきたいと思っています。
瀬名:石井先生からは、他県の情報が入ってこないという話を聞きました。何ヵ月か前の話ですが、現状はどうなのでしょうか。
飯島:それは情報の性質にもよると思います。感染者の情報がもっと分かればもっと効率的に感染状況を制御できるという専門家の焦りや憤りはもっともだと思いますが、個人情報の提供には本人の同意が必要であるとする立場についても、誹謗中傷がこれだけ深刻化している現実に照らすと、不当だとは言い切れないかもしれません。
瀬名:クラスターが発生した飲食店名は、宮城県では公表されていません。その一方で、公表している県もあります。そこは、県ごとの裁量に任されているということなのでしょうか。
飯島:確かに、厚生労働省の事務連絡では、クラスターが発生し、感染経路の追跡が困難な場合には、感染拡大防止の観点から店舗名を公表する扱いとなっていますが、これはあくまでも事務連絡にすぎませんので、県がそれぞれに適正に判断するのがむしろ本筋だとも思います。なお、特措法は、知事がまん延防止等重点措置や緊急事態宣言下で事業者や施設管理者に対して命令をしたときはその旨を公表できるとして、裁量を認めています。
瀬名:自治体にはどこまでのことができるのでしょう。たとえば、各自治体の保健所が行なっている感染者に対する聞き取り調査の情報が国に上がってこない、それがあれば有効な対策がもっと円滑に取れるのにという専門家の不満を聞きます。ほかには、今回の感染症対策では、IT活用で日本は大きく後れを取ったと思います。新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム、ハーシス(HER-SYS)を作ったものの、個々の保健所で集めている情報との整合性が悪かったり、新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAも使い物にならなかったといわれています。地方行政と中央にいる専門家とをつなぐIT技術がうまくいかないことには、何か根本的な理由があるのでしょうか。
飯島:わずかながら、地方制度調査会の委員として地方行政のデジタル化の議論に関わったことがあります。議論の最終段階でCOVID-19が発生しましたが、その前にいくつかの地方自治体の現地視察も行いました。その中で例えば、ベンダロックインと言われる問題があります。自治体クラウドの導入をするには、各自治体が運用している現行システムからのシステム移行が必要になります。ところが、現行の契約企業(ベンダー)から提示されたデータ移行見積書があまりにも高額なため、システム変更ができないというのです。
瀬名:でもそういう状況が続いていたのでは、いつまでたっても横のつながりができないと思うのですが、改善の兆しはあるのでしょうか。
飯島:そのためのデジタル改革関連法だと思うのですが、個人情報保護の観点からの懸念も出されています。情報は権力に直結するものでもありますので、強大な権力をどのように統制していくのかということも含めて、制度設計をしていく必要があります。
瀬名:スペイン風邪(スペイン・インフルエンザ)が流行った1918年ころの資料(注3)を改めて見直すと、当時はまだ保健所がなくて、県ごとに独自のアイデアで防疫対策を行なっていて、その情報を中央の衛生局が取りまとめていたようです。その後、それがきっかけとなり、地方の状況を統括する目的で都道府県庁に保健所を置くことになったのだというのが、ぼくの理解です。パンデミックが保健所制度を作ったという言い方もできるかもしれません。ところが、情報を吸い上げるために作った保健所制度が、21世紀になった今も機能していない。そこには、地方分権、地方と中央をつなぐためのデジタル化とそれを活用するためのIT化という大きな課題が横たわっているような気がします。各保健所では、ファクスで集めた情報をハーシスに手入力で入れているなんていう話も聞きます。
飯島:地方と中央をつなぐために組織面からアプローチしたという経緯はとても興味深いです。確かに、情報を集約するために作られた制度が、100年経ってもいざという時に機能しないのだとすると、途方に暮れてしまいます。ただ、情報という資源についてはやはり、利活用と保護とのバランスが問題になると思います。利活用だけでも、保護だけでもないのでしょう。瀬名さんは、全国的な情報基盤の構築が必要だというお考えですか。
瀬名:そういうふうに具体的に考えているわけではありません。ただ、世界的なパンデミックはこれからも起こると思っています。そのとき、地方自治体が果たすべき役割は大きいはずで、その土地ならではの有効な対策もあれば、他県も使える対策も見つかるはずです。そういう参考になる対策や情報を全国で共有する仕組みがあればいいなあとは思っています。
飯島:お考えはわかりました。私としては横展開に注目しています。クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号の患者受け入れの経験を基に、医療体制の骨格を構築した「神奈川モデル」や、新型コロナウイルス感染防止対策実践に対する「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」などを他の地方自治体でも取り入れるといった、中央政府の関与なしの横での連携への期待です。そこに国が関与するとしたら、横展開を促進するための情報プラットフォームを作ることかもしれません。
瀬名:そうでした。店内でのディスタンスの取り方などを定めた「山梨モデル」に他県も見習う動きがありました。ただ、東京では狭い店が多くて、そのままの適用ができないので独自のアレンジをしたみたいです。ぼくも、そういう形で地方自治体主体のパンデミック対策が広がるといいなと夢想することもあります。
飯島:私も賛成です。パンデミックに関わらず、各自治体が手探りで進めている中で、有効な政策が波及効果によって横に広まっていくのはすばらしいと思います。
瀬名:今回のパンデミックはグローバル化によってもたらされたと言われています。グローバル化は止められないにしても、ローカルの特色や独自の工夫が活かされていく仕組みができるといいですよね。経済を低迷させないということでの仙台市の特色ある取り組みはありますか。
飯島:地域経済が沈みきらないように、特に国分町の飲食店等を対象に、いわばプレミア付きの地域消費喚起割増商品券の発行の支援が行われています。飲食店は他の業種に比べて大きな打撃を受けていますが、東北地方最大の歓楽街である国分町はさらに特別の対応を必要とします。ワークショップでも学生が強い関心を抱いて調査研究を進めています。実際、時短要請をかける区域の線引きをどこにするのかをめぐって、宮城県と仙台市のあいだで激しいせめぎ合いがありました。エビデンスがない状況で区分けしなければいけないという大きな問題です。
瀬名:たしかに、宮城県における仙台という都市は特殊な存在で、面積が広く、都会を思わせる地域もあれば、田舎っぽい地域もある。その中で、あちこちでぽつぽつとクラスターが発生しています。どこで区域を分けるか難しいですね。
COVID-19を踏まえて、地方行政の今後のあり方について、行政法がご専門の立場から何かお考えはありますか。
飯島:地方公共団体内部の狭い区域を基礎とした地域社会や地域住民に対して期待しています。福祉にしても防災にしても、地域社会が拠点になるべきだと思っています。先ほどの繁華街でいえば、学生自身が、官民連携によって繁華街での感染対策の推進、さらには店舗単位を超えて街全体で「安心できる街づくり」を目指して政策提言しようとしています。ただ、現実問題として、こうした公共的事柄を担うには大きなエネルギーが必要で、それを担う人はいつも同じメンバーになってしまいがちですので、人材育成、世代交代、経済的基盤の整備などの課題もあります。地域に負担だけを押し付けることは避けなければなりません。そうした課題を解決して地域社会の自治を積み重ねていくことができたらと願っています。
地方自治を担う人材の育成が求められている
瀬名:人材育成という意味では、公共政策大学院の使命もそこにあるわけですね。
仙台医療センターの西村秀一先生は、SARSが流行した20年くらい前から、地方で専門家を育てていく必要性を力説しています。グローバル化が今後さらに進むと、新興感染症が最初に見つかるのは大都市ではなく、地方の旅館だったりするかもしれないからというのです。東北大学でも、押谷先生や小坂先生が頑張っておられる。仙台は、そういう施設や人材を抱えているという意味で、感染症対策では特異な立場にあるのではないかと思っています。行政官が勉強会に参加するなど、行政の意識も割と高かったと思います。ただ、そういう熱意や人材をつなぐ体制が、この20年のあいだにできませんでした。今回のCOVID-19を機に、何か変わる気配はありそうですか。
飯島:私自身、論文や本などを読んで、各分野がそれぞれの視角から論じているように感じていました。そして、感染症の専門家から実際にご教示をいただいた御蔭で、専門家頼みではなく、人文社会科学系の知恵も総合していく必要があると気付かされ、学際研究に真剣に挑戦したいと思っています。例えば、公衆衛生学は社会を守るという考え方をするのに対し、公法学の観点から、社会というマスで捉えることに対する率直な疑問を提起し、個人を基点にした組み換えを提示することができないかと考えています。
より実践的な意味で仙台市の取り組みとして注目しているのは、計画を立てて実行し、評価を行った上で改善し、新たな計画を立てることを繰り返していく、いわゆるPDCAサイクルを回していこうとしている点です。震災の経験も踏まえてのことだと思うのですが、他にはあまり見られない先進的な取り組みだと思います。また、まさに今、全庁を挙げて保健所機能の維持に努めているそうです。日常的業務に優先順位付けをしながら継続しつつ、突然かつ急激に増加したニーズに何としても対応していくために、組織面でも作用面でも前例のない取り組みを進めていることに敬意を表しています。
瀬名:今回、日本はクラスター潰しである程度の成果を上げてきたわけですが、2009年の新型インフルエンザ・パンデミックのときよりも、地方行政のあり方に注目が集まったと思います。2009年のときは、国際空港での水際作戦に注目が集まり、舛添要一厚生労働大臣が真夜中に記者会見を開いて大騒ぎになりました。ところが、実際に感染者が出たのは神戸で、感染経路は辿れませんでした。最初の死者が出たのは沖縄でした。東京が直撃を受けた印象はありませんでした。そしていつの間にか季節性インフルエンザに移行して収束しました。
ところが今回は、最初に東京、横浜、神奈川で感染者数が増え、東京都が中央政府と同列で語られるようになり、東京都での出来事と都知事の言動に関するものすごい量の情報がメディアから全国に発せられました。大阪の感染者数も増えると、大阪府知事がニュースを賑わわせるようになりました。それ以外の地域でも、地方自治体の長が、それぞれ独自の対策を立てられるようになったはいいけれど、批判の矢面に立たされたりしました。都と政府との間でさえ、連携がうまくいっていないことがわかってしまいました。それによって生じた政治に対する不信感が、パンデミック対策で自粛要請に従わない動きにつながりました。
パンデミックのとき、いちばんまずいケースは、こういうふうに、市民が行政リーダーを信頼できなくなってしまうことだと思うんです。リーダーの言動に信頼ができないと、緊急事態宣言が発令されても、人々はいうことを聞かなくなってしまう。政治に対する信頼感を取り戻さないと、有効な対策をとれない状況が続いてしまいかねません。
飯島:信頼を取り戻すための武器は、行政法学でいうと説明責任の概念だと思います。感染症も特措法も情報の公表やリスク・コミュニケーションについて定めています。こうした個別法に加えて、いわゆる通則法も行政スタイルの変革を目指して整備されています。行政手続法制、情報公開・個人情報保護・公文書管理法制、政策評価制度などがそうです。細かな話になりますが、例えば、基本的対処方針等の基準について、行政は、自ら定立したからにはこれに拘束され、基準に従って運用を行わなければなりませんが、機械的に基準に従っていればよいというわけではなく、個別の事情を考慮して基準を適用すべきでない場合には基準から外れなければなりません。行政は、自ら定立した基準をどのように運用するかについて、その理由を説明しなければならないのです。地味ですが地道に、行政ならではのこうした責任を一つ一つ果たしていくしかないようにも思います。
同時に、パンデミック対応では個人も責任を負うことが求められます。感染症法も特措法も国民の責務を定めています。ただ、法律で定められているからというだけではありません。「正解」は誰にも分かっていない、専門家も政治家も官僚も分かっていない。だから、ただ一人国が責任を負うとすれば足りるわけでは決してなく、地方自治体も事業者や個人も責任を分担し、自らの責任において判断し行動するのだとも考えられます。
このような考え方は、パンデミックによって、また、他ならぬパンデミック対応によって苦境に立たされている事業者や個人にとっては、受け入れ難い机上の空論かもしれません。にもかかわらず敢えてお話したのは、今年度ワークショップを始める前に、宮田光雄先生(東北大学名誉教授、ヨーロッパ思想史)にお目にかかる機会を偶然に得て、『われ反抗す、ゆえにわれら在り――カミュ『ペスト』を読む』(注4)というご本を拝読し、色々と考えさせられたからです。このご本の最後で宮田先生は、「自分自身によって、自分自身にたいして定義された価値を発見し、自分自身の決心にもとづいて、それを行動に移す一定の自由の余地は、なお残されている」と書いています。この文章の意味自体、私はまだ十分に理解できていないと白状せざるを得ません。そして、先生方の思想や実践を門外漢として語るだけでは伝わらないことも、この対談を通して痛感しました。だからこそ、実定法学者として、自らの思想・実践を模索していきたいと強く思っています。
瀬名:やはり「個人」と「国」、「自己」と「社会」、その間にあってそれらをつなぐもの、という課題に戻ってきますね。すばらしいお話をうかがえて嬉しく思います。「学際研究に真剣に挑戦したい」という先ほどのお話には、思わず胸が熱くなり、心が震えました。この対談シリーズもこれで1年ほど続いたことになりますが、通して感じるのは、東北大学にはやはり各分野にそれぞれすばらしい専門の先生がおられる。そうした先生方も、COVID-19の問題にはご自身の専門の立場から示唆に富んだご意見をお持ちで、将来や未来のことも考えていらっしゃる。けれどもやはり、横のつながりがどうしてもまだうまくいっていない。全体としての創発までに至るのが難しい、「学際」にならない。そんな印象がありました。ですが今回、先生の「横展開に注目しています」というお話をうかがったとき、ひとつの光明が差し込んだように感じました。地方自治体どうしの横展開を促進させるプラットフォーム作りは、まさに「学際」展開にも応用できるのではないか、ここから本当の「学際」が生まれてくるのではないか、そんな希望さえ抱きました。
最後に宮田先生のお名前が出ました。ぼくも今回のパンデミックで、ずっと積ん読だったカミュの『ペスト』(注5)を昨年初めて読み、関連の解説書も何冊か手に取って、偶然ですが宮田先生の『われ反抗す、ゆえにわれら在り――カミュ『ペスト』を読む』も読んでいました。お話をうかがって、ぜひ再読してみようと思っています。幸いなことに、宮田先生のこの本は、ブックレットの体裁なので読みやすく、読むのにもさほど時間はかからない。そこで思ったのは、複数の専門家が個々の専門を超えた議論をする際に、どの先生の専門分野からも外れているかのように見える文芸評論を共通の課題書に指定することで、それをきっかけに横展開──「学際」の輪が広がってゆくことが、ひょっとしたらあるかもしれないということです。カミュの『ペスト』は、発表当時はペストという疫病を世のなかの不条理の象徴として読まれていたはずですが、いまは文字通りパンデミックを己が身でもって体験する具体的指針の一つとして、多くの人に読まれています。文学という想像の産物ですが、人はそこにリアリティも感じますし、人によってはそこから現実社会における行動の手がかりやインスピレーションを受け取ります。
「自らの思想・実践を模索していきたい」という飯島先生のお言葉は、決して強要されて出てくるものではありません。ぼくたち全員がゆっくりとではあっても自発的に心の中で育み、各人が行動として表現してゆく、自分の中にある「自由」な価値なのだと改めて感じました。パンデミック宣言から1年以上が過ぎ、社会にはまだまだ多くの課題が山積していますが、今回の先生との対話はぼくたちが次のステップへと進むための重要な指針の一つになったように思います。ありがとうございました。
*注
(1)飯島淳子「パンデミック対応における地方自治」論究ジュリスト35号(2020)pp.23-29。
(2) 齋藤智也「2009年のパンデミックから10年の歩み」pp.142-155、野田博之・五十嵐久美子「新型インフルエンザ等対策特別措置法のもとでの対策の進展」pp.156-168、岡部信彦・和田耕治編集『新型インフルエンザパンデミックに日本はいかに立ち向かってきたか 1918スペインインフルエンザから現在までの歩み』南山堂(2020)所収など参照。
(3) 内務省衛生局編『流行性感冒 「スペイン風邪」大流行の記録』東洋文庫(2008)
(4) 宮田光雄『われ反抗す、ゆえにわれら在り――カミュ『ペスト』を読む』岩波書店、2014。
(5) アルベール・カミュ『ペスト』宮崎嶺雄訳、新潮文庫、1969。原著の刊行は1947年。今年になり、複数の新訳が既刊ないし出版予定。
(2021年7月9日取材、8月10日記事作成)
(編集責任:東北大学広報室特任教授 渡辺政隆)
飯島 淳子(いいじま じゅんこ)

東北大学法学研究科・法学部教授、公共政策大学院長。東京大学大学院法学政治学研究科修了。2020年より公共政策大学院長を兼任。専門は行政法、地方自治法。フランスの地方自治法研究を行った博士論文で藤田賞を受賞。第31次・第32次地方制度調査会委員、国土交通省社会資本整備審議会委員・国土審議会委員、宮城県収用委員会委員、仙台市人事委員会委員・総合計画審議会委員等を歴任。著書に、『事例から行政法を考える』(共著、有斐閣、2016)、『行政法』(共著、有斐閣、2017)、『市民のための行政法、公務員にとっての行政法』(有斐閣、2019)ほかがある。
瀬名 秀明(せな ひであき)

1968年生まれ。作家。東北大学大学院薬学研究科博士課程在学中の1995年、『パラサイト・イヴ』で第2回日本ホラー小説大賞を受賞しデビュー。1998年、『BRAIN VALLEY』で第19回日本SF大賞受賞。東北大学大学院工学系研究科特任教授(2006~2009)。小説のほか、『パンデミックとたたかう』(共著=押谷仁)、『インフルエンザ21世紀』などの科学ノンフィクションもある。小説『この青い空で君をつつもう』『魔法を召し上がれ』『小説 ブラック・ジャック』などでは、新しいジャンルにも取り組んでいる。
(肖像写真 佐々木隆二氏撮影)
渡辺 政隆(わたなべ まさたか)

1955年生まれ。サイエンスライター、日本サイエンスコミュニケーション協会会長。文部科学省科学技術・学術政策研究所(2002~2008)、科学技術振興機構(2008~2011)、筑波大学広報室教授(2012~2019)を経て、2019年より東北大学広報室特任教授、2021年より同志社大学特別客員教授。進化生物学、科学史、サイエンスコミュニケーションを中心に、『一粒の柿の種』『ダーウィンの遺産』『ダーウィンの夢』『科学の歳事記』などの著書のほか、『種の起源』(ダーウィン著)、『ワンダフル・ライフ』(グールド著)など訳書多数。