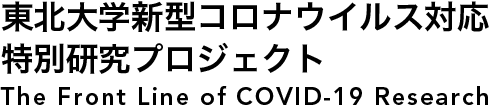PEOPLE
インタビュー
新型コロナウイルス感染症対策の現場を語る
厚生労働省クラスター対策班の一員としてCOVID-19対策の最前線で活躍されている東北大学大学院歯学研究科副研究科長の小坂健教授に瀬名秀明さんが感染症対策の現場について伺いました。(2020年9月10日収録)
瀬名:小坂先生は、国立感染研究所、厚生労働省の本省、東北大学に在職され、感染症研究者、行政官、大学教員というキャリアパスを経験されてきたわけですが、今回、厚労省のクラスター対策班に参加されたのも、そういう経緯からなのでしょうか。
小坂:そのことは大きかったと思います。声をかけられたのは、北大の西浦博先生からでした。西浦先生とは、厚労省の食品安全委員会専門家会議でご一緒したことで懇意になっていました。私のキャリアがつなぎ役として役立つと思われたのでしょう。
瀬名:押谷仁先生からではなかったのですね。

小坂健教授
瀬名:それとは別に、東北大学の新型コロナ対策にも参加されていたのですか。
小坂:最初は東京から、東北大学の対応に関する押谷先生の助言を、押谷先生に代わって私が電話で理事に伝えていました。4月5日に大学から感染者が出たことで、新型コロナ対策班が8日に設置され、毎日、11時と17時に対策会議を開いていました。大学の最初の対応としては、1月30日に「東北大学感染症対策本部」、3月3日に「東北大学新型コロナウイルス感染症対策本部」が設置されました。私もそのメンバーでした。
私自身としては、2009年の新型インフルエンザ騒動*2)の際に、学内にそういう対策室を設置したほうがよいと提言して実際に設置し、専門家を集めて情報交換をしていました。今回、その仕組みが参考になりました。新型コロナ対策班は、主催者は青木孝文理事・副学長で、理事全員、事務系幹部のほか、総長もほぼ皆勤されています。
留学生向けの寮で感染者が発生し、その対応を機能的に実施できました。寮は個室なのですが、ユニットごとにトイレと食堂が共用なので、感染者が出たユニットの寮生の避難隔離対策を実施しました。ホテルを確保し、部局長が食事を届けるほどの手厚い対応をし、感染を最小限に食い止めたことで、他大学から参考にされるほどの成果を収めました。私は、新型コロナの最新情報を共有する役割で、個々の担当理事が迅速に対応されました。現在の会議開催は、週2回+αの頻度です。
クラスター対策班での仕事
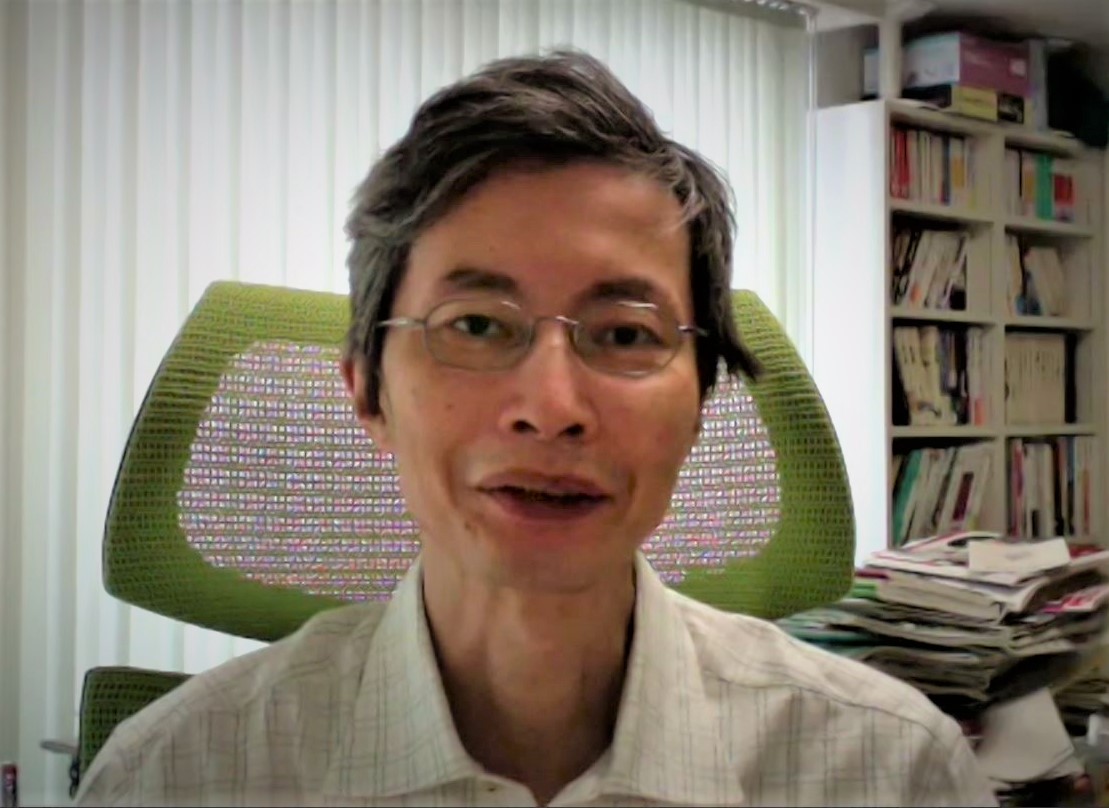
瀬名秀明さん
瀬名:クラスター対策班ではどのような対応をされていたのでしょう。
小坂:クラスターの発生を見つけるために、常時データを追跡し、マップに落とす地道な作業をしていました。クラスター班と言いつつも、情報発信やITを用いた解析やアプリの開発など、必要に迫られたことは何でもやっていました。私が最初にやったのは、東北大学の中谷友樹先生にデータを地理情報に落として解析する地理情報システム(GIS)の作業を依頼したことでした。中谷研究室の院生を派遣していただきました。北海道で最初のクラスターが発生した際には、携帯会社にデータの無償提供を依頼し、人の移動の解析を2月末だったか3月の初めに開始しました。それ以後も、人の動きの解析は続けられています。
瀬名:ぼくは2009年の新型インフルエンザ騒動を取材して2冊の本を出しました。そのときも、GISの解析ができないのかと、知り合いの工学系の専門家に聞いたのですが、当時はほとんどできていなかったと思います。昼と夜のおおよその人口動態を解析できる程度で、プライバシーの問題で限界がありました。この11年でそのあたりは変わったのでしょうか。クラスターを追えるくらいの解析ができるようになったのですか。
小坂:同じ課題は今も引きずっていて、個人情報に関わる問題はあちこちで壁になり、それでうまく進んでいないというのが実情です。無償提供してもらえたのは、個人情報が入っていない、人の動きだけの情報でした。しかも、同じ500mメッシュの情報と言っても、会社ごとに情報の中身が異なっているのです。クラスター班の解析では、携帯会社以外のIT企業にも声をかけ、いろいろなデータの提供を交渉したのですが、結局、個人情報の壁があって断られてしまいました。
アプリとしては、LINEがコールセンター用のアプリを作ってくれたほか、富士通にいる友人に頼んで専用アプリを作ってもらいました。しかし、導入するにあたってはお役所の壁にぶつかってしまった。厚労省内のどこの部署が所掌するかだけでも、たらいまわしにあってしまったのです。接触者アプリは2月中に富士通が作ってくれたのですが、その導入を各自治体に持って行ったところ、そこでも日の目を見ませんでした。たとえば東京都は、23区ごとに個人情報諮問委員会があり、年1回のその会議を通さないと実施できないといった調子です。唯一、長崎県だけが、乗員にクラスターが出たクルーズ船が寄港した際に、その対応でそのシステムを使ってくれました。
クラスターの追跡は、保健所の担当者が電話や対面で情報収集をしていてとても大変です。スマホアプリでできれば助かるはずなのです。しかし、宮城県でも、保健所長レベルではデータをエクセルに落とせるようにするという条件付きでOKが出たのですが、県庁レベルで、副知事に2回面会したものの、個人情報を理由にはじかれました。最終的には導入していただいたのですが、すべて手弁当で走り回ったのに、当初はけんもほろろでした。緊急事態なのに、そういう技術を使うことができないのです。
瀬名:日本はそんなお寒い状況なんですか。
小坂:日本の行政システムでは、みんなが普通に使っているITシステムが使えません。たとえば厚労省の役人も、自分のパソコンではオンライン会議ができません。オンライン会議専用のPCをもってきて、省内のラインには接続できないので、民間のWi-Fiにつなぎ、全員がそこに集まってオンライン会議をするといったあり様です。県庁も同じです。どんなソフトも勝手にインストールしてはいけません。インターネットで情報収集しようとしても、サイトによってはアクセスできない。一人10万円の特別定額給付金の支給も、オンラインと言いつつ、すべてプリントアウトして処理しているのが実情なのです。こういうことを根本から変えないかぎり、IT技術をいくら磨いても使えなければ意味がありません。

イメージ(本文とは関係ありません)
ITと個人情報の壁
瀬名: ITもだめ、個人情報もダメなんですね。どこから変えていけばいいのでしょうね。
小坂:がん登録など、公衆衛生上の利益になる必要な情報は個人情報保護から外されています。なので、新型コロナの感染情報も除外対象にすればそれで済んだはずなのですが、省庁間の調整が壁になりました。
瀬名:国別のPCR検査の対応の差が話題になりましたが、それ以上に顕著だったのが、IT対応の差でした。新型コロナの拡散防止には、IT対応が有効だったと思うのですが。
小坂:韓国は、感染情報がクレジットカードやスマホ決済の情報と繋げられ、全国に公開されました。その対応が効を奏したと言えます。その後に出た論文を見ても、
韓国は、5次、6次の感染まで追跡できていました。スポーツジムで感染したという内容も、ヨガ教室では感染者はおらず、激しい運動をしていた教室で感染者が出たことがわかっています。その後の解析でも圧倒的な差が出ているのです。中国では、スマホにレッド、グリーン、イエローの色分けが出て、外出が規制されています。台湾も、スマホがGPSで追跡され、外出禁止を破ったら罰金が科せられるシステムができています。それらの国は、それで抑え込んでいるのです。
日本では、そこまでやらなくてもクラスターが抑え込めたといえば聞こえはいいのですが、やりたくてもできないことがたくさんあったのです。感染症法の策定にあたっては、患者の隔離は人権を侵すということで、隔離の強制権を設定できませんでした。感染者の人権は守られても、感染させられる側の人の人権はどうなるのでしょう。新型インフルエンザでは、アメリカでさえ、患者の隔離を厳格に実施していました。日本では、人権や個人情報ということで、法的な規制ができない上に、現金支払いが多い現状では、インフラ的にもできないことが多いのです。今回の対策に関わって、改めて痛感しました。
スケープゴートと陰謀論
瀬名:最初に北海道で発生したクラスターの追跡はうまくいったのではないでしょうか。その一方で、5月25日の緊急事態宣言解除後、東京では感染が静かに拡大し、クラスターが追いにくい状況になりました。クラスターを追えない5月以降の状況と比べて、北海道の初動でうまくいった勝因はどこにあったのですか。
小坂:北海道は地方で発生したにもかかわらず、すぐに追跡できました。これには、感染研が全国の衛生研究所にPCR検査用の試薬を配布していたことが功を奏しました。PCR検査に関してはメディアが陰謀論を煽りましたが、それはありません。世界的にも類を見ない地域での検査態勢があり、信頼できる検査システムが機能した結果なのです。もちろん、検査のキャパが少ないので、検査数の限界があったことは確かです。しかし、アメリカでは、CDC*3)が配った検査試薬の信頼性に問題がありました。偽陽性が3割も出たという報告まであります。日本は、行政レベルでの検査体制という意味ではできていたのです。ただし、韓国や台湾は、SARS*4)を教訓に、民間企業による検査体制の整備を進めていたのに、日本はそれがなかったことで、PCR検査数に大きな差が出ました。それと、北海道では、知事のリーダーシップがありました。新型コロナは人の動き、特に無症状の若者の移動が感染を広めるので、大学など、若い人を多く抱える機関がリーダーシップをとって実施したこともよかったと思います。感染症対策は、国レベルよりも、自治体レベルでの地域ごとの特徴をつかんだ対応が基本です。国の役割は、自治体の側面支援です。
北海道で初めてクラスターが出たとき、大学生などの若い人たちを中心に広まった後で高齢者に感染して初めて見つかるというパターンが見えました。そこで、若い人たちが鍵だということで、若い人たちにはたらきかけることをやりました。北大の先生たちとも連携をとりましたが、北大では学部学生が啓発チームを作ってくれていました。全国の若者にも伝えるべきだということで、企業、広告代理店、コミュニケーションの専門家と相談したほか、ツイッターでの情報拡散を奨励するということもやりました。しかし、いろいろな反対もあり、結局うまくはいきませんでした。西浦先生がツイッターで流したり、クラスター班の動画を流したりしました。
瀬名:そういえば当時、渋谷の繁華街のビルの電光掲示板に、タレントが若者に自主的行動を呼び掛ける映像が流れていたのを、テレビのニュースで観ました。「きみたちの行動変容にかかっている」と。
小坂:結果的に、若者をスケープゴートにして社会を分断した結果となってしまったかもしれません。次は夜の街がスケープゴートになりましたが、クラスターを追跡していくと、そういうパターンが見えてくるのです。
瀬名:「夜の街」という言葉はどこから出たのですか。クラスター班の中からですか。
小坂:そうです。クラスター班の中で話しているうちに、どこからともなく出てきました。ただ、班内で最初に使われた「夜の街クラスター」は、都心に住む50代、60代の裕福な男性の夜遊びに関係した感染者が多いことに関してでした。
瀬名:緊急事態以宣言解除後の東京で追跡がしにくくなったのは、夜の街での個人情報の関係からデータをとりにくいということがあったのでしょうか。
小坂:ホストクラブの男性従業員は、集団生活をしていることもあって、追跡しやすかったようです。女性のほうは、歌舞伎町にこだわる必要がないので、他の地域に移動してしまうこともあるようです。追跡調査は、保健所の担当者が電話で問い合わせます。保健所からの電話で、過去2週間の行動を問われて、話しにくい人は言わずにすませたはずです。そういう場合は感染経路不明になっています。
瀬名:新宿のホストクラブなどを対象に、全員のPCR検査が行われたりしましたが。
小坂:新宿の夜の街には、以前からHIV対策で入りこんでいた行政の専門家がいたので、そういうことができたのです。夜の街に突然乗り込んでいって検査させろと言っても、ふつうは実現しないでしょう。ただ、集団生活をしているホストクラブは追えますが、女性従業員のほうは、検査を逃れて全国どこへでも移れるので、追いにくいということがあります。検査をしようにも、夜の街の一部の一部しかできないのです。そこで、検査を受ける動機付けとして、新宿区では検査を受けて感染が判明した人に10万円を出すことにしましたが、保健所の担当者が、感染者の住所確認だけで疲弊してしまいました。そういう動機付けではなく、社会の偏見とか差別とかをなくさないと、感染源を追いにくいという状況があります。
瀬名:個人情報をマスクしながら、ITでもサポートできる集め方、個人情報を話してもサポートしてもらえるような仕組みがあれば、人の心も変わるかもしれませんね。
小坂:韓国では、入店の際にスマホのQRコードをかざすだけでメールアドレスの登録ができて行動のログが採れるシステムを導入しています。ようやく日本でも導入している地域もありますが、これがあれば、聞き取り調査が正確になり楽になります。保健所が電話をかけなくても、自分でどこの店に行ったかわかるし、店のほうでもわかる。もちろんそれは個人情報を残すことになるのですが、感染症対策では有効な方策です。中国のように強制的に実施するわけにはいかないので、導入するとしたら、感染症対策にしか使わないという条件で納得してもらうしかないでしょうね。もっとも、メールやフェイズブック、ウェブ検索などでアメリカで情報が抜かれているという厳然たる事実があるのに、国がやること、国が配るアプリをスマホに入れることには抵抗があるという心理の背景には、国に対する信頼感のなさがあるのかもしれません。
リスクコミュニケーションの課題
瀬名:それは以前から話題になっていたことですね。2009年の新型インフルエンザのときはできないままやらずに来たことの弊害が今になって出てきた感じです。
スケープゴートの話では、最初は若者、次は夜の街、その次はGo To トラベルが責められることになり、地方の人が、東京からの来県に目くじらを立てるようになりました。福島在住の作家、柳美里さんが、大震災の原発事故の際は多くの人に助けられたのに、今回は、東京の人は福島に来るなということになって、複雑な思いになっていると、エッセイに書いていました。スケープゴートに仕立てられたり、感染者が出た学校や施設の関係者が、教育実習やアルバイトを断られたりするスティグマ(烙印)を貼られたりするという問題については、2009年の取材時よりはよくなった面もありますが、SNSのせいでかえって悪くなった面もありますよね。
あと、先生もおっしゃっていたコミュニケーションの問題があります。2009年の新型インフルエンザのときは、行政の人が前面に出て会見を行い、専門家はその後ろに控えていました。専門家の意見が直接聞こえることはありませんでした。今回、それはまずいという反省から、西浦先生たちは自らツイッターなどで発信したのでしょうか。生の声が聞けるのはいいのですが、8割減の言葉だけが独り歩きしました。感染症専門家によるコミュニケーションについてはどう思われますか。
小坂:私自身、原発事故の際に、コミュニケーションの重要性を痛感しました。人は、ゼロリスクを求める傾向があります。リスクゼロでなければ不安になってしまう。リスクを理解しないまま、東京からの来県に反発することになっています。宮城県内では、地方の人が、仙台から来る人には気をつけろと言っています。これは、50歩100歩の争いですよね。
現時点で、10人が集まって、その中に感染者がいる割合はほんのわずかで、0.003%程度とかです。%で言えばごくわずかだけれど、高齢者や持病を抱えていて重症化しやすいと言われている人たちは、少しでもリスクがあると、それを避けなければいけないと思ってしまいます。恐怖によってスティグマが生まれます。つまり、人々にとっては、安心と安全は違うということなのです。その中で安心を作っていくためには、正しい情報だけではだめで、身近な情報と比較した伝え方も重要だと思います。
たとえばイギリスでは、毎日の生活で突然死する確率は100万分の1だという喩えを使っています。日本の突然死は、風呂のせいでもう少し高いのですが、普通に生きることでさえ、ゼロリスクではないということをまずはっきりさせる。突然死のその確率を1マイクロモートと呼び、それと比べて、あなたの手術のリスクは、10日生きているのと同じリスクですよという伝え方をしています。ゼロリスクへの固執を排除するリスクコミュニケーションを考えていかなければいけないと思います。
そういう意味では、今回の新型コロナでもうまくいっていません。医療施設でさえ、自分たちを守るために極端に走っているところがあります。しかし、現状としては、東京と宮城のリスクにはさほど差がありません。にもかかわらず、東京から来る人に不安を感じてしまうのは当然の心理です。岩手の人にとっては、宮城の人が怖い。立場が変わればという考え方をすべきなのですが、実際には難しい。スティグマを取り払うコミュニケーションは可能なのかというジレンマをいつも感じています。
瀬名:専門家による情報発信についてはいかがですか。
小坂:西浦先生や押谷先生が積極的に発信したのは、国が動かないから仕方なしにやったという側面が強いです。私も厚労省の役人だったから言うのですが、厚労省には技官もいるのだから、役割を分担をして、研究者ではなくトップ技官が記者会見をやるべきでした。そうしないと、クラスター班が省内で変なこと、勝手なことをやっているという雰囲気になってしまいます。しかし、役人は動けなかったようにみえました。なので、国家の危機なのだからということで、研究者がやむなく発信するしかなかったというのが実情です。
瀬名:海外の事情はどうなのでしょう。
小坂:スウェーデンでは、任命された研究者がすべてを決めて、政府は口を出さない方式です。これはかなり極端な例でしょう。
日本では、政治家は、専門家がこう言ったからという言い方で専門家に責任を押し付ける発言をしながら政治判断をしていました。これは専門家にとって危険なやり方だと思っていました。西浦先生や押谷先生の責任問題になりかねないという話が出ていたのです。しかし、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議副座長の尾身茂先生などは、ルビコン川を渡ってしまったのだからこれでやっていくしかないと覚悟を決めて発言していました。一つひとつの情報発信について悩みながら、とにかく有効な対策をとっていかなければならないという思いで、その時点で最善と思われることをやっていたのです。専門家会議に対しての偏見や陰謀説、インフォデミック*5)が未だに言われていますが、陰謀論に仕立てたほうがメディアにとっては面白いのでしょう。なんともしがたいところです。そこで、専門家は議論を経た判断による提言をし、最終的には政治家が決めていくのが理想だろうということで、専門家会議の役割を見直そうということになりました。
瀬名:そんな中で、光明が見えたことはありましたか。悲観的な話ばかりですが。
小坂:ないに等しいですね。あえて言えば、東北大学だけでなく長崎大学の人も入ったチームで、誰がトップということもなくフラットな関係で、みんなが言いたいことを言い合うことで、対策が進んでいったことですかね。押谷先生がぽろっと口に出す「妄想」とでもいうべき希望的観測を形にすべく、みんなが自分にできることを捜しながら動いて行ったのがよかったことでしょうか。
それ以外のこととしては、日本で働いている外国人研修生に必要な情報が届いていないという思いから、東北大学東北メディカル・メガバンク機構の土屋菜歩先生にお願いして多言語発信をしたとか、がんばっているのに暴言の電話対応をしなければならない保健所職員のメンタルケアなど、これまでのネットワークから現場の声が届いていましたので、表に出ていないことで迅速に実行できたこともありました。

イメージ(本文とは関係ありません)
安心と安全の違い
瀬名:安心と安全の切り分けという話がありました。この問題意識は原発事故のときからありました。放射性物質の飛散に関する情報をそのまま流すと人々が恐怖でパニックを起こしかねないから抑えたという話もありました。安全だといくら言われても、安心できない。その根底には、不安感を払拭できないことがあるのではと思っています。ぼくはホラーも書く作家ですが、ハリウッドのホラー映画にあるように、ゾンビのような、形あるものが襲ってくるのが恐怖の定番描写です。ただしゾンビは噛まれると伝染するという設定も一部にはあって、つまりゾンビは目に見えない感染症のメタファーなんですね。では主人公たちはどうするかというと、ひたすら逃げるか、シェルターのなかに閉じ籠もる。相手が「恐怖」ならば、逃げて隠れることができれば安全でしょう。しかし一方で「不安」感は、この先どうなるのか、将来の計画が立てられないことから生じる感情で、心の問題ですから家に閉じこもっても逃れることはできず、安心できない。今は、社会的な閉塞感や不安感が蔓延しています。安心と安全は、恐怖と不安との関係にも似ているのではないでしょうか。
小坂:私は、以前バングラデシュで閉じ込めれて以来、エレベーターに乗るのも怖いところがあって、不安感は人より強いかもしれませんし、どうしたら克服できるのか考えて暮らしてきました。世の中の人たちがみな、新型コロナのことばかり心配するようになっています。人は、一人では不安で生きていけません。そこで、視線の方向を変えると、不安や恐怖から抜け出せるかもしれません。マスクをしても、自分の感染は防げないかもしれません。しかし、他人への感染は防げるかもしれない。不安は、自分に閉じこもることでかえって高まってしまいます。人にうつさない行動を心掛けることで、前向きになれるのではないでしょうか。
とは言っても、マスクをする、密にならない、距離をとるといった新しい生活スタイルは、人間本来の生活スタイルからかけ離れたスタイルです。アメリカの大学では、新学年を迎えるにあたり、パーティーが開かれて感染者が増えています。それに対して、懲罰を科している大学もありますが、学生のそうした行動を一概に責めるべきではないという意見が出ています。みんなで騒げない大学生生活に意味はないので、むしろ、なるべく危険を避ける騒ぎ方を奨励すべきだというのです。これはハームリダクション(harm reduction)という考え方です。
たとえば、日本では、薬物は少しでもやったらアウトですが、オランダなどでは、薬物中毒者が一定割合存在するのは避けられないことを前提に、HIV予防のために、注射針の使いまわしはやめようキャンペーンをしているのがハームリダクションです。絶対ダメと拒絶すると、それがスティグマになって立ち直れなくなる。排除ではなく、受け入れる。ともすると日本では、健康は善で病気は悪、病気になる人は生活態度が悪いという自己責任論が言われがちです。そうではなく、社会全体として受け入れていく捉え方がないと、感染症、弱者、夜の街、ドラッグユーザーなどを救うことができません。共感することが大切なのです。
瀬名:三密は危険だから、カラオケや飲み屋、パチンコ店は避けろと言われても、行く人はいますよね。西浦先生の8割削減論には、そういう人も計算に入っていたのでしょうか。
小坂:西浦先生のモデリングに関しては、クラスター班内でも自由に批判し合い、侃々諤々の議論をしました。あの8割には、そういう人も計算に入れた上での8割でした。ただ、接触を減らすといっても、接触の中身についての言及はありませんでした。三密の対策は早期にできていました。換気の重要性を入れたのは、従来の飛沫感染対策だけでは感染予防が難しいことを織り込み済みだったからです。モデリングには、ブラックボックスの部分があって、専門家会議でも叩かれていました。最悪のシナリオを考えるのは当たり前なのですが、メディアはそれに飛びつきやすいという特性も考慮したうえでコミュニケーションする必要があったのかもしれません。
瀬名:安心と安全の伝え方、コミュニケーションについて、何かお考えはありますか。
小坂:生きているのにもリスクがあります。放射線の場合でも、宇宙からの放射線に普段からさらされていますし、体内にも一定程度の放射性物質を取り込んでいます。そのことの理解がまず必要です。以前、どういう人が大きな不安を抱きやすいかという調査をしたことがあります。ハーバード大学が行った調査では、情報が伝わっていないから人々は不安になるという結論でした。しかし重要なのは、誰もが不安を感じるが、重要なのはそれで行動を変えられるかどうかです。それには、学歴や収入が関係しているという調査結果が出ました。前述したように、身近なリスクとの比較で理解してもらう伝え方が有効だと思います。頭では安全とわかっていても、飛行機に乗るたびに安定剤を内服している私としては、実体験を繰り返すことでリスクを実感していくしかないのではないかと思っています。
瀬名:一部コメンテーターから、日本人はあまり感染しないし重症化もしていない、季節性インフルエンザの死亡リスクのほうが高いのだから、新型コロナについては騒ぎすぎだという声が出てきています。そうは言っても、報道の大きさと人々の不安感は相関します。飛行機よりも自動車のほうがリスクが大きいけれど、身近なリスクには鈍感です。新型コロナで、アメリカでは数十万人亡くなっている、アフリカはもっと大変なことになるかもしれないというところには、想像力が及ばないのが実情ですよね。
小坂:2つの病気を比較するのは難しいことです。インフルエンザでは、超過死亡*6)だと1万人、子供のインフルエンザ脳症でも数十人は亡くなっています。インフルエンザには、それほど効かないけれど重症化予防のためにワクチンがあるし、抗インフルエンザ薬も、熱を早く下げるくらいの効き目しかないけれど、とにかくあります。予防や治療でできることがあるというのが救いになって安心につながっているのかもしれません。最後の切り札があることが、安心につながるのでしょう。有効なワクチンがすぐにできるかどうかは疑問ですが、ワクチンに関する過剰な報道がありますよね。あるいは、信頼できる研究者までが、アビガンなどの薬に過度の期待を寄せて、早く認可しろと言い出したのには驚きました。最後のよりどころを求める気持ちが強いのでしょう。新型コロナについても、軽く感染した人が増え、それほどでもなかったという声が広まっていったり、ワクチンや治療薬が曲がりなりにもできれば、死亡者数は変わらなくても、捉え方はインフルエンザと同じような認識になっていくかもしれません。
瀬名:その一方で、リスクを忘れてしまうということもありますよね。2009年の新型インフルエンザのことを覚えている人は、今はもうほとんどいません。つい先日の9月9日、日本も購入契約をしているアストラゼネカ社のワクチンが、「副作用が出たかもしれない」ということでいったん治験を世界中で中断したとの報道が出ました。するとメディアの人たちの間でさえ落胆が広がって、失望感につながる論調になりかかりました。その後、11日に英国で治験が再開されたと追加報道がありましたが、このことは今多くの人がワクチンの可能性にすがって生きている状況を如実に示したと思います。「ワクチンができるまでは不便な生活を我慢しよう」という心情です。でも、これでもし有効なワクチンができなかったら、そうやって期待にすがっていた人ほど、心のよりどころを失ってしまうのではないかと危惧しています。
小坂:インフルエンザのワクチンだって、あまり効かないシーズンもあるわけです。インフルエンザワクチンの効果は重症化予防であって感染を防ぐことはできないにしろ、何かあったときの車のシートベルトのような効果はあるという話はしていますが、ワクチンを打つことが、安心感につながるということはあるのでしょう。メディアは、インフルエンザの患者が出ても毎地には報道しないでしょうね。
瀬名:そうですね。ただ、さらに例を出しますと、ほとんどの人は忘れていますが、2009年の新型インフルエンザの時も「ワクチンが足らなくなる」「早くワクチンを」という世論が湧き起こりました。優先順位の決定でもかなり揉めました。ところが年末以降にいったん流行が収束すると、人々は急速に関心を失ってしまった。あのとき日本は国産ワクチンと海外からの輸入ワクチンを合わせて1000億円以上の値段で買い上げたのですが、ワクチンが出回ったときはもう流行は収まっていて、結局、輸入ワクチンのほとんどは使われず257億円分が解約。余った在庫は廃棄、返品処分になって、その作業にも多額の負担がかかることになって廃棄処分にされてしまいました。当時のワクチン卸業者の人がこのことを嘆いて本に書いています*7)。いかに私たちは忘れやすい生きものであるか。1000億円は「安心料」だったのか。多くのことを考えさせられます。
東北大学の新たな取り組み
瀬名:東北大学の学際研究重点拠点で「感染症共生システムデザイン学際研究重点拠点」が立ち上がりました。そこでの先生の役割を教えてください。
小坂:これも押谷先生のよい意味での「妄想」から出たプロジェクトです。感染症のモデリングから国際法や宗教学まで、学際的な英知を集めてやっていこうということで、押谷先生の「妄想」を文章化して図にしました*8)。私としては、地域の自治体と協力してIT技術などを社会実装して感染症と共存していきたいという思いがあります。すべての部局の研究者が参加して、この拠点を使って若い研究者が世界と繋がって自由に研究できるプラットフォームを目指したいと思っています。
瀬名:IT系の研究は、20代、30代の研究者が優れた成果を上げていますからね。ジョンズ・ホプキンス大学の新型コロナ感染症マップ*9)を作ったのも学生でしたよね。
小坂:そうなんです。中国にいる親が心配だということで、大学院生が1人で数時間で作ってしまいました。
瀬名::WHOより動きが速かった。しかも最初はデータを手打ちしていたのに、すぐにAIを使ってデータを取得するように改良しました。若い人の才能や行動力を後押しできるといいですね。具体的なプログラムは決まっているのですか。京都大学などでもやっていますが、東北大ならではの観点があれば。
小坂:京都大学では有名な先生たちがリレー講演をしていますよね。それもいいけれど、私の思いは、若い研究者が中心となって具体的な社会実装や変革につながることをやっていくことです。国の大型予算を使って、KPI(重要業績指標)や評価を気にしながらがむしゃらに働くというようなことではなくて、さまざまな分野の若い人たちが自由な発想で社会の課題に挑戦していくのを、大学や教授がサポートしていくというのが私の理想です。クラウドファンディングや企業の寄付なども含めて、新しい研究資金の獲得方法を実践していきたい。仙台市は特に、スタートアップをすごく一生懸命やっているのに、手を上げるメンバーはいつも同じだったりします。学生は授業で忙しいからと。社会にある課題を解決する研究をするためには、現場を知らなければなりません。それを見つけるには、授業を受けて勉強しているだけではだめ。教育のしかたも変えて、社会の課題を自分で見つけてチャレンジする意欲をもたせなければいけない。
1つのアイデアとしては、当事者を入れるという方法があります。その点イギリスは進んでいて、認知症の対策を進めるプロジェクトには認知症の人が入っています。新型コロナの場合でも、冬に向けた対策で、社会的弱者が出している声明を同時に公開しています。それで言うと、カリキュラムの作成に当事者である学生が入っていないのでは、魅力的なカリキュラムはできないでしょう。医学領域は、教えるべき標準は世界的に決まっているのだから、講義は世界でいちばんうまい人がネットでやればいい。大学は、学生を鼓舞することに力を入れるべきです。
瀬名:東北大学研究担当理事の小谷元子先生が、学際研究が大事と言ってきたけれど、本当に学際的なことはやってこなかったことを実感したとおっしゃっていました。私は東北大の薬学出身の作家であり、学際の巨人だった小松左京さんがやったことを継いでいきたいと思っています。なので、学際的な知をつなげるにはどうやったらいいのか、どうしたらそういう場が作れるかに興味がありました。それもあって、今回、この企画を引き受けたわけで、東北大が本気でそれをやるなら期待したいです。
クラウドファンディングについてもお聞きしたいのですが、先生が立ち上げた「新型コロナウイルス感染症:拡大防止活動基金」*10)は、さしあたっての予算がないということで始められたのでしょうか。結果的に寄付がたくさん集まりましたが、今後もうまくいけるとお思いですか。社会の関心が薄れたら下火になりそうな気がしますが。
小坂:国のお金は遅いんです。震災のとき、日赤の基金にお金が集まりましたが、被災者に電化製品が届いたのはずいぶん後のことでした。その結果、リサイクルショップに新品の電化製品がずらりと並ぶことになってしまいました。1年後に100万円もらうより、今の10万円がありがたいというのを見てきたわけです。当初、必要なところにマスクが届かないということがあった中、中国につてがあって入手できる人もいました。しかし行政には迅速な対応ができない。そういう社会的正義があったので、たくさんの寄付が集まったのでしょう。SONYは、社員が寄付したのと同額を寄付するマッチングファンドを実施しましたし、元楽天の選手で大リーガーの田中マー君も寄付してくれました。プラットフォームを提供してくれたREADYFOR(レディーフォー)CEO米良はるかさんも、本気で取り組んでくれたので、逆にこちらのノルマがたいへんでした。協賛できる研究者を3日で集めたり、ツイッターで発信したり、電通の協力を得たり。そういうことで何とかなった特殊な例だと考えています。趣旨はとてもすばらしいクラウドファンディングなのに支援があまり集まっていないものがあります。困っている人の手助けになるんだという社会的正義、良いことに参加できるという思いに共感できなければ、成功につながらないのです。人の顔が見えて自分事としてとらえられるような工夫が必要なのです。われわれも文科省からもらえる研究資金がないと嘆く暇があったら、いろいろなことに挑戦すべきなのかもしれません。
瀬名:ありがとうございました。なるほど、小坂先生はアイデアと実行の人だということがよくわかりました。
「共感」という言葉が出ましたが、みんなで共感の力をよりよい方向へ持って行ける社会づくりができたらといつも思います。共感の力については、ぼくも小説家なので、普段から考えるところがあります。小説は読者との共感の連携をどう設計するかが大きなポイントなので。最近思い出すのは、2011年の東日本大震災の時、日本学者のドナルド・キーンさんが、被災地で暴動も起こさず粛々と秩序を守る人たちや、被災地の人たちへ共感を寄せて応援する全国の人たちの姿を見て感激したという話です。キーンさんは、第二次大戦後焼け野原になった東京でも整然と列をつくって列車を待つ人々を見た詩人の高見順が「私の眼に、いつか涙が湧いていた。いとしさ、愛情で胸がいっぱいになった。私はこうした人々と共に生き、共に死にたいと思った。……私は今は罹災民ではないが、こうした人々の内のひとりなのだ」と書き綴っていたことも思い出し、日本人の持つ共感性に改めて感じ入り、震災を機に日本国籍を取得して日本への永住を決めたそうです。ぼくはキーンさんのこの気持ちを忘れたくないと思うんです。共感性はクラウドファンディングを成功させる原動力にもなりますが、逆に「東京の人は来るな」とみんなで口走ってしまう怖さも秘めている。共感のよい面を後押しして、危険な側面をうまく抑えるような仕組みはできないものか。
新型コロナは季節性インフルエンザより死亡者が少ないんだから大げさに騒ぐなという意見の人もいますが、ぼくはそう考えたくはないんです。新型コロナでの重症患者をひとりでも減らすこと、季節性インフルエンザで亡くなる人をひとりでも減らすこと、そのどちらも同じように大切だと思うんです。もし数の論理ですべてを考えるなら、希少疾患の患者さんを治す薬の開発など切り捨てて構わないことになってしまう。自動車の方が飛行機より事故が多いとはいえ、世界中の工学者、技術者は、AIを使って危険を少しでも早く予測できないか、自動運転機能で人の負担を軽減できないかと、自動車事故を少しでも減らそうと今も努力しています。どちらか一方だけを取るのではなくて、どちらのリスクも減らせるよう努力を続けることが大切なんだと思います。
お話を聞いて、2009年の新型インフルエンザ騒動の教訓を活かしてインフラを整備していれば、今回の新型コロナへの対応も違っていたかもしれないことがわかりました。そして患者や支援者への偏見やスティグマはなぜ避けられないのかも課題として心に残りました。今後、この連載で、そういうことをもっと学際的に考えていけたらと思っています。
*注
1) 岩沼プロジェクト 東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県岩沼市との共同研究により、「絆(ソーシャル・キャピタル)」が、被災地に暮らす高齢者の健康に及ぼす影響を学術的に検証したプロジェクト。
2) 新型インフルエンザ騒動 2009年4月にメキシコでの発生が確認され、日本では5月以降に兵庫県と大阪府で、高校生を中心に感染が拡大した。患者が発生した高校には心ない誹謗中傷が投げかけられた。
3) CDC 米国疾病予防管理センターの略。アトランタに本部を置き、予算人員の規模のみならず、管轄する範囲でも日本の国立感染症研究所を凌駕する組織である。
4) SARS 重症急性呼吸器症候群の略。2002年から03年にかけて世界の30近い国と地域で感染が拡大した。
5) インフォデミック ネット上などに出回る根拠のない情報や偽情報に社会が振り回される現象。
6) 超過死亡数 特定の集団において、たとえばインフルエンザ流行期に、例年同時期の死亡数をもとに推定されるインフルエンザによる死亡数のこと。
7) 鹿目広行著『パンデミック発生! その時、誰がワクチンを運ぶのか?』(ダイヤモンド・ビジネス企画、2010)
8)https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2020/09/news20200918-01.html
9)https://coronavirus.jhu.edu/map.html
10)https://readyfor.jp/projects/covid19-relief-fund
(2020年9月24日作成 編集責任:東北大学広報室特任教授 渡辺政隆)
小坂健

東北大学大学院歯学研究科教授。東京大学大学院医学系研究科修了、国立感染症研究所・主任研究官、ハーバード大学公衆衛生大学院客員研究員(タケミフェロー)の後、厚生労働省老健局老人保健課・課長補佐を経て現職。
瀬名秀明

東北大学大学院薬学研究科博士課程在学中の1995年に『パラサイト・イヴ』で第二回日本ホラー小説大賞を受賞し、作家としてデビュー。
(肖像写真 佐々木隆二氏撮影)
渡辺政隆

サイエンスライター。文部科学省科学技術・学術政策研究所、科学技術振興機構、筑波大学広報室教授を経て、2019年5月より東北大学広報室特任教授。