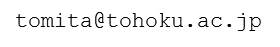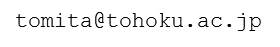
講義情報
令和7年度: 物理学入門 (1セメ水曜日3講時)
令和6年度: 物理学入門 (1セメ水曜日3講時)
令和5年度: 物理学入門 (1セメ水曜日3講時)
令和4年度: 物理学入門 (1セメ水曜日3講時)
令和7年度: フロンティア科目・ミカタの科学 (1セメ金曜日5講時)
令和6年度: フロンティア科目・ミカタの科学 (1セメ金曜日5講時)
令和5年度: フロンティア科目・ミカタの科学 (1セメ金曜日5講時)
令和4年度: フロンティア科目・ミカタの科学 (1セメ金曜日5講時)
令和3年度: 展開ゼミ・ミカタの科学 (2セメ月曜日5講時)
令和5年度: 学問論演習・科学のミカタ (2セメ月曜日2講時)
令和4年度: 学問論演習・科学のミカタ (2セメ月曜日2講時)
令和3年度: 基礎ゼミ・科学のミカタ (1クォーター月曜日3・4講時)
令和2年度: 基礎ゼミ・ミカタの科学 ※新型コロナウイルス感染症のため不開講
令和7年度: 文科系のための自然科学総合実験 (1セメ火曜日4・5講時)
令和6年度: 文科系のための自然科学総合実験 (1セメ火曜日4・5講時)
令和5年度: 文科系のための自然科学総合実験 (1セメ火曜日4・5講時)
令和4年度: 文科系のための自然科学総合実験 (1セメ火曜日4・5講時)
令和3年度: 文科系のための自然科学総合実験 (1セメ火曜日4・5講時)
令和2年度: 文科系のための自然科学総合実験 (2セメ火曜日4・5講時)※新型コロナウイルス感染症のため2セメ開講
平成31/令和1年度: 文科系のための自然科学総合実験 (1セメ火曜日4・5講時)
令和7年度: 自然科学総合実験 (1セメ木曜日運営責任者、2セメ金曜日運営責任者)
令和6年度: 自然科学総合実験 (1セメ木曜日運営責任者、2セメ金曜日運営責任者、課題12責任者)
令和5年度: 自然科学総合実験 (1セメ木曜日運営責任者、2セメ金曜日運営責任者)
令和4年度: 自然科学総合実験 (1セメ木曜日課題12実施担当者、2セメ金曜日運営責任者、課題12責任者)
令和3年度: 自然科学総合実験 (1セメ木曜日運営責任者、2セメ火曜日運営責任者)
令和2年度: 自然科学総合実験 (運営補助)
平成31/令和1年度: 自然科学総合実験 (2セメ木曜日運営副責任者)
令和7年度: 学問論 (1セメ月曜日)
令和6年度: 学問論 (1セメ月曜日)
令和5年度: 学問論 (1セメ月曜日)