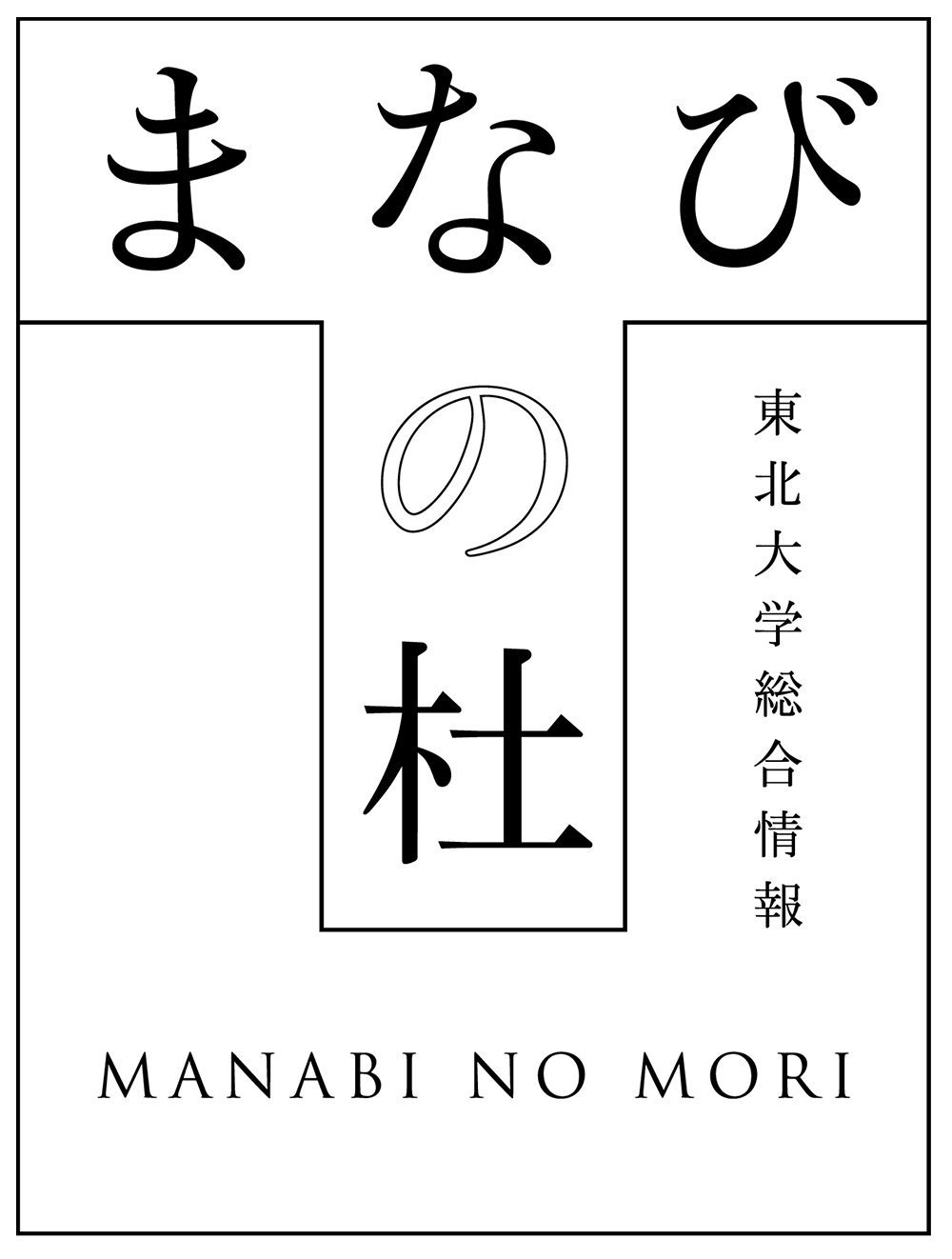#12地球科学への憧れから、命を守るための仕事へ
2025.10.28 更新
2025年4月、仙台管区気象台長に、第24代にして初めて女性として着任した鎌谷紀子さん。地球科学の専門的知見を活かして人々の命を救いたいと気象庁に就職し、地震分野の業務を長く担当してきました。2024年1月1日の能登半島地震の際は、気象庁地震津波監視課長という立場で深夜の緊急記者会見に臨んでいます。冷静かつ柔らかな口調で注意・警戒を呼び掛けたその場面をご記憶の方も多いのではないでしょうか。全国的に異例の猛暑に見舞われた今年は、日本の気象観測が始まって150年に当たります。地震や火山噴火、線状降水帯などによる気象災害も頻発するなか、仕事への使命感や東北大学で過ごした9年間についてお聞きしました。
【インタビュイー】気象庁仙台管区気象台 台長 鎌谷 紀子
的確な防災気象情報の発信を
気象庁の大きな役割は、気象や地震、津波、火山噴火を正しく観測し、的確な防災気象情報をお伝えすることです。みなさんには情報とそれに伴う危機感を理解し、最終的には自分の命を守るという行動に結びつけていただきたい、常にそんな気持ちで仕事をしてきました。
東北地方の気象・地震・津波・火山の情報を管轄する仙台管区気象台の台長としての仕事は、主に2つあります。1つは東北地方の方々に的確な防災気象情報を発表できるよう統括すること。もう1つは気象台としての最終判断を行うこと。防災気象情報は各部署の部課長が管理をしており、毎朝、夜勤から日勤の担当者に引き継ぎをすることがルーティンです。そこに私も同席し、最新の状況を把握して、地域の防災支援のための情報が的確に発表されているかを確認します。また、気象庁本庁への提案や管内の気象台への指示など、各部署から上がってくる懸案について説明を受け、ゴーサインを出す、あるいはアドバイスを加えて、仙台管区気象台としての方向性を決めて行くのです。
こうして取材にお応えすること、そして外部機関と連携することも大切な任務です。万が一、仙台管区気象台が被災して機能しなくなった場合は、東北大学災害科学国際研究所を代替庁舎として使用させていただくという協定を結んだばかり。災害研と共同で防災訓練を行うことを予定しています。

忘れえぬ新入生オリエンテーションの夜
小さい頃から地球科学に強い関心を抱いていました。台風が近づいてくるとドキドキ、ワクワクするような子どもだったのです。母は1948年の福井地震を経験しているので当時の体験を話してくれましたが、影響を受けたのはむしろ『銀河鉄道999』や『宇宙戦艦ヤマト』、『機動戦士ガンダム』など、地球や宇宙をテーマとしたアニメ。1981年のポートピア(神戸ポートアイランド博覧会)や1985年のつくば万博(国際科学技術博覧会)などが開かれ、地球科学がクローズアップされる時代でもありました。また、通っていた福井県立武生高校のそばを日野川が流れていて、そこに架かる橋に立つと視界がパーッと開けます。毎日そんな景色を見ていたことも、地球について勉強したいという思いにつながっているかもしれませんね。
東北大学は、とにかく地球科学を研究したいという理由で選びました。入試段階でめざす地学系を選べるし、研究第一主義という学風も私の目標とぴったり。さわやかな気候の「学都」で落ち着いて研究ができそうだと思ったのです。
入学直後のオリエンテーション合宿は鮮烈な思い出です。川渡(かわたび:大崎市鳴子温泉)の共同セミナーセンターで、知り合ったばかりのクラスメイトと夜の芝生に毛布を敷いて寝転び、満点の星を眺めながら「自分たちはこの壮大な宇宙の謎を解き明かしていくのだ」と熱く語り合いました。クラスは生物系や物理系なども混在していましたから、一人ひとり興味の対象が違って、しかもそれぞれが深い思いを抱いていました。今では大学教授や大企業の幹部になった人も多く、中には日本の地球惑星科学コミュニティを代表する日本地球惑星科学連合の要職を務めた研究者もいます。みなきっとあの川渡の夜のことも憶えていると思います。

教養部時代は広い学問分野に触れ、自然科学以外のテーマについて議論を交わし合うのが新鮮でした。2年生で専門の授業が始まって、夜遅くまで実験や解析をしたのも楽しい思い出です。伊豆大島の三原山が噴火したときは授業の内容が急遽変更され、専門家である先生から噴火のメカニズムをリアルタイムで解説してもらうという貴重な体験をしました。これは全島民約1万人が島外に避難するという大災害でした。
3年生になると第一志望の岩石鉱物鉱床学教室に入り、地形や地層の際立つ場所を見て回る巡検に出かけました。もちろん伊豆大島にも足を運びました。また、英語の科学雑誌から選んだ最新の論文について発表するという授業(雑誌会)は、卒業研究のテーマ選びにとても役立ちました。修士課程では月の内部を再現しようと思いつきましたが、指導教員の「火星の方がおもしろい」というアドバイスで方向転換。これが博士論文「高温高圧実験に基づく火星の内部構造の研究」につながりました。現在も大学内にある高温高圧実験装置で心ゆくまで実験させていただいたおかげです。また、国内外の研究会や学会で発表する機会を得て、著名な研究者からコメントを得たことも忘れがたい経験。論文の作成方法やプレゼンテーション技術など、当時鍛えていただいたことは、今も気象庁の仕事で役立っています。


地震災害を通して振り返る30年
大学で学んだ地球科学の専門性を活かして人々の命を救う仕事をしたいと考え、1994年4月、気象庁に就職しました。地震部門に配属されて次々と舞い込む仕事をこなすなか、翌年1月17日に阪神・淡路大震災が発生したのです。地震自体の正式名称は兵庫県南部地震といいますが、名称決裁文書を作成した瞬間を今も鮮明に覚えています。
東日本大震災、つまり東北地方太平洋沖地震が発生した2011年3月11日は、私は千葉県柏市の気象大学校で講師を務めていました。春の自主学習期間中にもかかわらず、学生たちが集まってきて「何があったのか解説してほしい」と求められたので、余震が続く教室で判明している事実を可能な限り伝えました。
そうして科学の観点から説明しながらも、感情が揺さぶられずにはいられませんでした。荒浜(あらはま)や野蒜海岸(のびるかいがん)で大勢の方が亡くなったという夜のニュースは衝撃でした。荒浜は友人とよく海水浴に行きましたし、野蒜は毎週のように地層観察に通った場所。ほかにも親しみのある場所で多くの人が命を落としたと知り、そんなことが二度と起こらないようにしなくてはとの思いを強くしました。
2024年1月1日の能登半島地震が起きたときは、気象庁地震津波監視課長という立場でした。24時間オペレーションの監視部門を統括する役職で、津波警報や津波注意報の発表の最終判断をくだす重い責務があります。最大震度5強以上の場合、平日日中は発生の1時間後、休日夜間だと2時間後に緊急記者会見を開くことになっています。
あの日もすぐ気象庁本庁に駆け付けました。東日本大震災以降初の大津波警報を発表しましたが、大津波警報の発表は、いつ津波警報や注意報に切り替えて解除できるかというシビアな判断と背中合わせです。警報が長引くとみなさんを不便な避難所に足止めしてしまいます。切り替えるべきときが来たらすぐ切り替えて安心していただきたいけれど、その判断が早すぎてはみなさんの命を危険にさらしかねず、それは絶対避けなければなりません。観測データとリアルタイムのシミュレーション結果を見比べつつ、判断を見極める作業が夜通し続きました。
緊急記者会見ではカメラの向こうに語りかけて
専門部署のスタッフはみなプロフェッショナル。大きな地震が起きても全く動じません。どれほどの津波がどのエリアに来るかを冷静に分析し、津波警報あるいは津波注意報かを判断する能力は心強いものでした。しかし、発表の最終的な判断を下すのは課長です。スタッフは話し合いの最後に決まって私を振り返り、「これで発表してよろしいですか?」と承認を求めます。私の判断一つで各紙各局の報道内容が変わり、大勢の方々の行動が変わるので、とりわけ緊張する瞬間です。
もちろん発表の仕方も大切です。ご自分の命を守ってもらうためには、その地域の方の気持ちに寄り添った方法で伝えることが重要だからです。私は2021年の福島県沖の地震以降10回程度緊急会見をしましたが、いつも80代の母をイメージしながら話すようにしていました。夜に起きた地震の後、真っ暗ななか心細い思いをしているだろう高齢者に向けて話そうという意識が、「ものが落ちて来ない安全な場所でお休みください」、「割れたものを踏んでケガをしないよう、枕元にスリッパを置いてください」と、ゆっくり語り掛けるような口調となって表れたのだと思います。
女性が緊急会見に登場するのが珍しかったのか、あちこちで話題にされたと聞きました。深夜に女性が地震の解説をしている、ということにも驚かれました。しかし、そもそも365日24時間いつでも、大きな地震があったら職場に駆け付けるのが日常です。私には娘が2人いますが、小さい頃から「地震が起きたら夜中でも出かけるのがお母さんの仕事だ」とよく理解し、協力してくれました。夜中に慌ただしく出かけるときはいつも「がんばって!」と玄関で見送ってくれたものです。
地震津波監視課長時代は住まいを気象庁本庁のそばに移し、携帯電話を手放しませんでした。お風呂に入るときも、携帯電話をビニール袋に入れて入っていました。飲酒も遠出も控えました。的確な情報を迅速に出さないといけないですし、そうしないと24時間のオペレーションで情報を上げてくるスタッフの労に報いることができないですからね。
ちなみに、2013年3月から約3年間はウィーンの在外公館勤務という珍しい業務も経験しています。国連機関である包括的核実験禁止条約機関準備委員会(CTBTO /Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)の日本政府の窓口、在ウィーン国際機関日本政府代表部です。地球のどこかで核実験が行われると、最初に地震波、そして微気圧振動や放射性核種などが捉えられます。私の任務はそれらの観測データを日本からウィーンに途切れることなく送ること。さらに、条約を発効させるための会議で日本の立場を述べたり、他国の外交官に批准を働きかけたりと、さまざまな国や地域の方たちとコミュニケーションを取りました。

「好き」という気持ちが強い突破力に
若い方には、数学や物理が苦手でも、理系のジャンルに興味を抱いたなら決してあきらめないで、と伝えたいです。その先には大きな世界が広がっています。かくいう私も数学と物理が苦手で、高校の先生に「文系の科目の方が試験の点数を取れるから理系をあきらめては」とか「世の中を動かすのは文系の人間だ」と説得されたほどです。でも、好きな地球科学をもっと勉強したいという思いを支えに進んできました。好きという気持ちさえあれば突破力は備わってくるものです。研究第一主義の東北大学には、文字どおり好きな研究をとことんできる環境があります。図書館や研究設備も整い、有益なアドバイスをしてくれる教授も揃うという恵まれた環境で、これと決めた研究テーマを存分に極めてください。
さまざまな友人と交流して多様な考えを聞き、議論をするのも学生時代にしかできないことです。卒業して10 年後、20年後に、私のようにセミナーハウスで星空を見上げながら語らったクラスメイトと、お互い思わぬ立場で再会することもあるでしょう。大学時代に切磋琢磨した仲間がそれぞれの興味や熱意のままに突き進み、それぞれの分野で成果を出していることは大きな刺激になります。そして同時に、それは自分も頑張ることができるという励みになるのです。
PROFILE
鎌谷紀子 KAMAYA Noriko

気象庁仙台管区気象台長。
1967年、福井県越前市生まれ。1985年、東北大学理学部地学系に入学。1994年、東北大学大学院理学研究科地学専攻博士後期課程を修了し、気象庁に入庁。主に地震火山部で地震活動解析や防災情報を担当。科学技術庁(地震本部担当)、東京大学地震研究所、在ウィーン国際機関日本政府代表部への出向も経て、2022年から気象庁地震津波監視課長。2025年4月から現職。