図1-1 ポリアセチレンの構造
「セレンディピティ 」
セレンディピティとは
「偶然の発見」と訳されることが多いため、何もしていないのに大きな成果が転がりこんで来たような誤解を与えがちですが、実際の意味は少し違います。
由来
ホレス・ウォルポール(Horace Walpole)の小説
『セレンディップの三王子』(Three Princes of Serendip)
あらすじ
王子たちが計画をたて航海にでたが思いがけないことが起きる。
しかし、果敢に立ち向かい予想もしなかった貴重な収穫を得た。
自然科学研究におけるセレンディピティ
偶然の意外な結果に着目し新しい成果を得る。 (偶然の発見)
重要なのは、偶然の結果をただまっているのではなく計画をたてて行動していること
です。
セレンディピティの本来の意味は、偶然の意外な結果に着目してその解決に努力
し、さらに大きな成果を得ることです。
セレンディピティの例(私の身近な例)
・ポリアセチレンの合成
白川秀樹(2000年ノーベル化学賞)
白川法以前
粉状の試料しかなく物性測定ができませんでした。
白川法の発明
触媒を1000倍まちがえる失敗で、偶然に薄膜が成長。
→
触媒濃度の常識にとらわれずに系統的な研究をし、高品質の薄膜試料の作成に成功しました。
![]()
図1-1 ポリアセチレンの構造
一次元構造をもつポリアセチレンは物理においても重要な研究対象です。
・超短パルスレーザーの開発
D.E.Spence, P.N.Kean, and W.Sibbet, Opt. Lett.
16, 42 (1991)
常識的なレーザーの調整法は、ミラーなどの光学素子の中央を使うことです(図1-2)。しかし、あるとき図1-3のような不十分な調整のときに、超短パルスが発生していることに気づきました。それに着目して、原理を明らかにすることで現在のカーレンズモード同期(図1-4)が生まれました。この方法は現在の超短パルスレーザーの標準となっています。
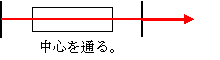
図1-2 常識的なレーザー共振器
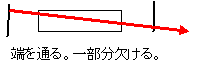
図1-3 不十分な調整状態
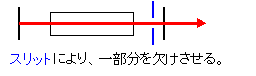
図1-4 カーレンズモード同期
・時間分解ラマン分光の開発(私自身の経験)
きっかけは、ポリジアセチレン(高分子)の研究で見られたラマン信号(物質の振動による信号)でした。最初は、他の信号に重なるじゃまな信号と考えていました。しかし、あるときこの信号をみることで振動状態を時間分解して観測することができる ことに気づきました。さらに、従来の方法では不可能とされた時間分解能と波長分解能の両立を 達成しました。図1-5は、β-カロテンの励起状態のラマン信号を時間分解測定した結果です。
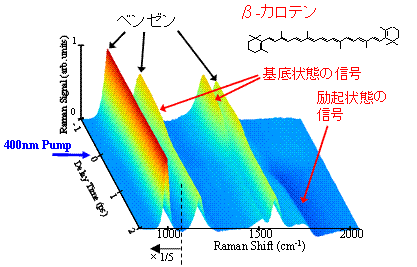
図1-5 β-カロテンの時間分解ラマン信号