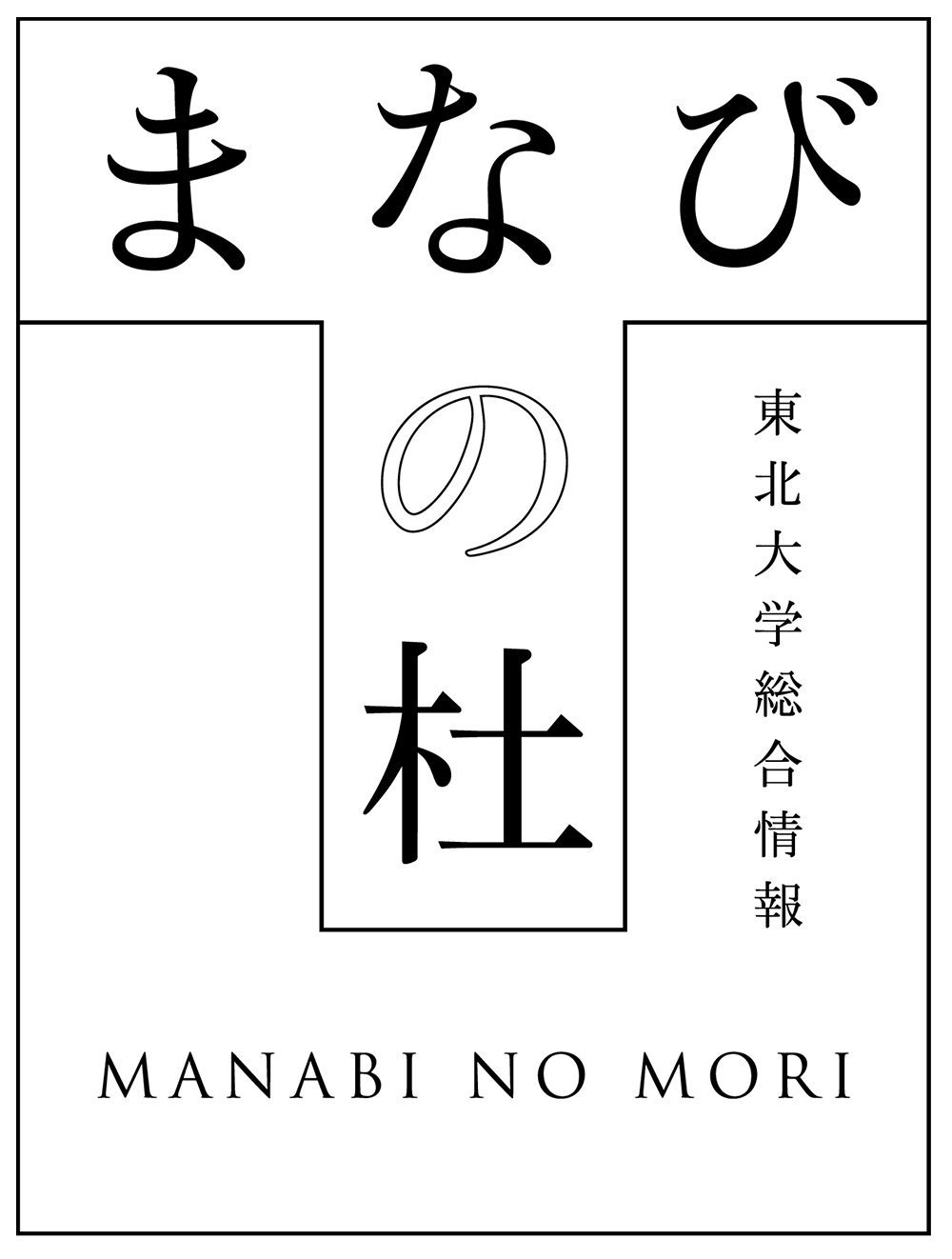#11グローバル人材育成とイノベーション創出へ
東北大学-インド工科大学ボンベイ校卓越連携機構が描く未来
2025.10.03 更新
2025年4月15日、東北大学にとって重要な意義を持つ「東北大学-インド工科大学ボンベイ校卓越連携機構(Joint Institute of Excellence : JIE)」が設立されました。これは研究第一主義を理念とする東北大学と、インド最難関大学で卒業生が世界中の研究機関・企業で活躍するインド工科大学ボンベイ校(IITB)が、教育・研究・産学共創を通してグローバル人材の養成とイノベーションエコシステムの創出に取り組む包括的な機関です。学術連携協定から長く関わってきた山口昌弘副学長に、両大学の連携の歩みとめざす姿について話を聞きました。また、一足先に短期海外特別研修「IITB-東北大学グローバルイマージョンプログラム」の1週間プログラムを体験した学生にも、現地で学んだことを聞きました。
【インタビュー】教育改革・国際戦略担当 山口昌弘副学長

インドの魅力、IITBの卓越性
インドは非常に魅力的な国です。人口は14億人と世界一、昨年のGDP は世界5 位。平均年齢は28 歳と若いエネルギーに満ち、その経済成長力は世界を動かしているといっていいでしょう。ことにアメリカの巨大企業GAFA(Google、Apple、Facebook:現Meta Platforms、Amazon)のトップエンジニアはインド出身者が占め、開発拠点もインド国内に擁するなど、ITイノベーションの最前線に立っています。しかもインド国内には10万以上のスタートアップが存在するなど、新たな価値を創造して社会貢献につなげようとするアントレプレナーシップにあふれた若い人が非常に多い。半導体、自動車、電機メーカーなどを筆頭に多様な日本企業が進出していることも、インドに国際的なビジネスチャンスのある証です。これが今回、東北大学がインド工科大学ボンベイ校(IITB)と卓越連携機構を設立した背景となっています。
政治的にもアカデミアでも両国はさまざまなパートナーシップを結んでいますが、インドから日本への正規留学生は約1600人と意外に少ないのが現状です。東北大学でもインドからの留学生はわずか43人。世界各国の約240の大学と学術交流協定を締結する東北大学では、かねてから急成長するインドとの交流は大きな可能性を秘めていると捉えていました。
実は、IITBとは2000年に大学間協定を結んでいます。IITBは国内最難関であるインド工科大学23校のなかで2番目に歴史が古く、最も優秀な学生が集まるといわれます。高い研究水準は研究第一主義の東北大学とも共通します。その後、2020年頃から本格化した人材交流や共同研究を戦略的に深めるため、2023年9月にIITBのスバシス・チョードゥリ前学長と本学の大野英男前総長がJIEの構想に着手しました。そして互いの担当幹部が6回ボンベイと仙台を往来して、2024年12月に教育・研究・産学共創という三位一体で包括的かつ持続的に取り組むJIEの構想を固め、2025年4月に正式に締結しました。他大学にはこれほど大規模な国際連携組織はないのではないでしょうか。
目指すのは、国際社会を牽引するグローバル人材の育成と共同研究の強化です。学術的インパクトのある研究成果を生み、社会実装を通じて社会的インパクトを実現する。産官学が互いに相乗効果をもたらして発展し、投資を呼び込んで好循環を生むことを期待しています。

互いが強みを持つ4分野でダブルディグリー
連携研究を先行させるのは災害科学、交通、ロボティックス、ヘルスケアの4分野。日本もそうですが、インドの国土もまた多くの災害に見舞われてきました。都市インフラが整っていないため、ひとたび災害が発生すると甚大な被害を引き起こします。それだけに、防災・減災の観点からのインフラ整備に高い関心が寄せられており、そこに東日本大震災を経験した東北大学の知見を存分に生かせます。
ロボティクスはいうまでもなく日本がリードする分野です。最近はAI駆動のロボット技術が飛躍的に進化し、両国が強みを発揮できます。また、インド14億人の健康にいかに貢献できるかもビジネスチャンスにつながるテーマです。将来的には、持続可能な社会の実現に貢献するエネルギー分野や、半導体・量子といった先端科学技術分野などと合わせ、計10 の分野で連携を強化していく方針です。
教育については、国際的な視野でイノベーションに取り組む人材の育成をめざして博士課程に共同単位プログラム(ダブルディグリー)を設けます。学生は二つの大学の指導教員のもと、ボンベイと仙台を行ったり来たりして共同研究を進め、両大学の学位を取得できます。専門分野の研究のほか、企業等でのインターンシップの機会を提供するのも特徴です。
ダブルディグリーの募集は4分野各5 人を想定して、IITBは2025 年度中に、東北大学も2026 年度に始める予定です。次の段階は修士課程で、最終的には学部でも実施する方針ですが、学部への導入には英語の授業を増やすというカリキュラム改変も必要になるので、おそらく10年単位のプロジェクトになるでしょう。
そもそも日本にインド人留学生が少ないのは、インドの学生が日本の大学に興味を持つ機会があまりないから。インドの学生に東北大学の魅力をいかに訴求するかが課題です。東北大学の研究は研究者レベルでは認知されていますから、先生たちが学生に留学先として東北大を勧めてくれる環境を醸成することが重要です。研究者同士がつながれば、学生にもその結びつきを利用してもっと研究してみたいとモチベーションが生まれるもの。ひるがえって、それがダブルディグリーの狙いでもあります。
IITBは全寮制です。学生たちはキャンパス内にある「ホステル」と呼ぶ寮で寝起きを共にします。日本には「同じ釜の飯を食う」という言い方がありますが、IITBでもまた同じホステルに住んだことによる深い信頼と絆は一生続くという文化があります。1年にわたりIITBのホステルで生活して研究をする経験は、どんな道に進むにしろ、人間としての大きな財産となるはずです。

日印の企業文化を体験するインターンシップ
インドを訪れた人は誰しもが、人と自動車、荷車や牛が縦横無尽に行き交う喧噪に圧倒されるでしょう。まさにカオス。その様相こそが巨大なエネルギーの根幹なのだろうと理解しても、個人的には、私たち日本人が現地の環境になじんで実力を発揮するのは容易ではないだろうと想像しています。インド第二の都市ボンベイももちろん、キャンパスを一歩出ると混沌が広がります。そこになんとか順応し、実力を発揮して活躍できるようなタフな若者が生まれてほしい。ある意味、そうしてインドのとてつもないエネルギーを吸収して日本に取り込んでほしいと強く思います。
ダブルディグリープログラムで産学共創によるインターンシップを重視するのも、そんな観点からです。東北大学の学生がインドで現地企業または日系企業の現場を経験することで、インドの企業、あるいは両国をつなぐ企業に就職するという可能性が開けます。逆に、IITBの学生は日本でインターンシップをすることによって、日本企業の考え方を理解し、日本社会に慣れることができる。実は、日本企業が採用したインドの若者が、環境になじめずに離職してしまった例をいくつか見聞きしています。能力も意欲もあるのに力を発揮できないのは本人にとっても企業にとっても残念なこと。東北大学がいったんインドの学生の受け皿となり、日系企業でインターンシップを経験してもらうしくみは、企業側から見ても魅力的です。それにより日本に定着する、あるいは帰国して日本との架け橋になる人材に成長してくれることを望んでいます。
JIEではダブルディグリーとは別に、異文化交流の入り口となる短期海外特別研修「IITB-東北大学グローバルイマージョンプログラム」も用意しています。機構設立直前の3 月には学部と修士・博士課程の学生を対象に1週間のプログラムを実施しました。学際的な授業をIITBの学生と共に受けたり、研究所やスタートアップ施設を訪問して議論をしたりという内容です。驚くことに、実施数日前の呼びかけにもかかわらず、10人の募集に30人も応募がありました。それほど学生がインドに、IITBに興味をもっているという表れでしょう。参加学生たちからは、目を見開かされた、人生を左右するようなインパクトを得た、という声が聞こえています。
さらにインドに関心を持つ玄関口としては、イベント「ミート・インディア」もあります。インドからの留学生や留学経験者とのワークショップや、インドと関わりのある企業・政府機関の方を招いたセミナーなどで構成します。長期滞在して研究をする学生を増加させる戦略にもとづき、段階を踏めるこうした仕掛けをさらに整えていく予定です。

日印のイノベーションのプラットフォームに
このほどIITBの700名の研究者を対象に、東北大学のどの研究者と共同研究を希望するかをというアンケートを実施しました。すると災害科学、ロボティックス、AI、半導体を中心に90件もの回答があった。10人に1人以上が具体的に関心を持ってくれているのです。これらは組織的な取り組みをして初めて顕在化することで、現在それぞれの共同研究を推進していくための準備をしています。東北大学スタートアップ事業化センターでもIITBの同等機関を訪問して互いに連携を深めていく仕組みづくりに取りかかっています。
誕生したばかりのJIEですが、やがて連携分野が10まで広がると相当数の学生が東北大学とIITBを行き来することになります。期待するのは東北大学がプラットフォームとなって産学官連携やスタートアップが盛り上がるダイナミックな展開。いずれは大学や分野の枠を超え、インドと日本をつなぐオープンなプラットフォームに成長することを目標としています。例えば民間企業がインドに進出する場合にJIEを活用してもらう、あるいは東北大学と共同で進出することができれば非常に望ましく、ひいては東北大学を中核とした産学官連携によって日本とインドのイノベーションのエコシステムを創出していきたい。これを持続可能な形で機能させるには、企業からの投資というサポートが欠かせません。いろいろな形で応援していただければ、本当にうれしく思います。
▼短期海外特別研修「IITB-東北大学グローバルイマージョンプログラム」参加
岸田麻巳子さん(大学院経済学研究科博士前期課程1年)

学部3年から4年にかけて10か月間スウェーデンに留学経験があります。次は新興国に留学したいと思っていたのと、インドのエネルギー問題や宗教・歴史に興味があるので、治安や衛生面などの不安はありながらも、貴重な機会だと思い応募しました。
毎日異なるテーマの学際的な授業を受け、ゲストハウスに戻って食事をし、夜は参加した東北大生10人で振り返りの議論をするというスケジュール。授業の内容はもちろんですが、10人は医学系、工学系などいろいろな学部・分野の学生なので、日ごろはあまり出会うことのない面々と共通のテーマについて議論するということ自体、新鮮でした。
その合間を縫って、IITBの学生が私たちをオートリキシャで広大なキャンパスのツアーに連れ出してくれたのですが、彼らはインドの最高学府にいながら勉学以外の場面でもとにかくエネルギッシュ。夜遅くまで付き合ってくれるホスピタリティと熱量には圧倒されました。また、広大なキャンパス内には寮はもちろんゲストハウスや病院もあるなど、外に出なくても暮らしていける環境が整っています。キャンパス内のヒンドゥー寺院では世界最先端のテクノロジーと宗教的価値観が共存することに驚きを感じました。また、案内してくれた学生がヒンドゥーの神話を熱心に説明するのを聞いて、彼らが東北大学を訪れたとき私は日本の文化をきちんと伝えられるだろうかと考えさせられました。
歓迎される体験をしたことで、大学間レベルで交流するイメージが具体的に描けるようになりました。IITBの学生が東北大学に来たときはその交流にぜひ関わりたいと考えています。
現在所属している環境経済学ゼミは、日本人の大学院生は私一人だけで、大多数が中国や東南アジア、アフリカからの留学生です。日本にいながら各国の専門的な話を聞けるのは刺激的です。現在は変動地球共生学卓越大学院プログラムに参加していますが、インドに行って途上国の状況への興味が高まり、また学際的な授業を通して経済学ではない多様な学問をもっと学びたいと思うようになりました。

吉本有秀さん(大学院理学研究科 博士前期課程1年)

インドは、インドプレートがユーラシアプレートの下に沈み込むことで大規模な地震が起こりやすい地域です。僕はインドの防災教育や防災システムに興味があったので、IITBでは気候変動についての授業を受けた後、先生にインタビューを試みました。すると、避難警報のシステムのない地域も多いなど、防災面の未熟な現状を知りました。
IITBの学生は短い休憩時間でもコーヒーやチャイを淹れてくれて、笑顔を絶やさず、日本のおもてなしとは異なるホスピタリティの文化を感じました。また、みんな学ぶ意欲にあふれ、夜中でも「これからみんなで勉強するよ」と元気に部屋に戻っていく姿が印象的でした。一を聞いて百を知るような聡明さを持つのはもちろん、国の将来を担っていくのだという自負と、恵まれた環境にあるからこそ国に貢献したいというマインドが浸透しています。
帰国する日の空港行のバスで、偶然にも運転手さんの隣の助手席に座ることになりました。彼は英語ができないけれど、ニコニコして片言の英語で一所懸命話しかけてくれる。その暖かい気持ちがじんわり伝わってきて、ノンバーバールコミュニケーションの大切さを実感しました。また、シティツアーの短い時間ではすれ違った少年が手を振ってくれたり、家族づれの女の子に「一緒に写真を撮って」と声を掛けられたり。バスの運転手の「暮らしが日本の技術に支えられている。感謝している」という言葉は、日本のテクノロジーが輸出先の地域の発展に役立っているという実例を示してくれて、感動しました。
この短期プログラムを通して、僕のキャリアビジョンははっきり変わりました。日本の防災技術は世界でもトップクラスです。だからこそ、日本が他国をリードしていく必要があると私は確信しています。大学構内のスタートアップのインキュベーション施設を訪問したことに感化され、それまで自分にはなかった起業マインドが沸き上がって、海外で働くことを主軸に考えるようになりました。帰国後さっそくJICA(国際協力機構)のインターンシッププログラムに応募し、秋からはニカラグアで2か月間、マナグア湖の水質改善のための環境教育プログラムの実践などを体験してきます。

取材・原稿/千葉 由佳(荒蝦夷)
写真/齋藤 太一