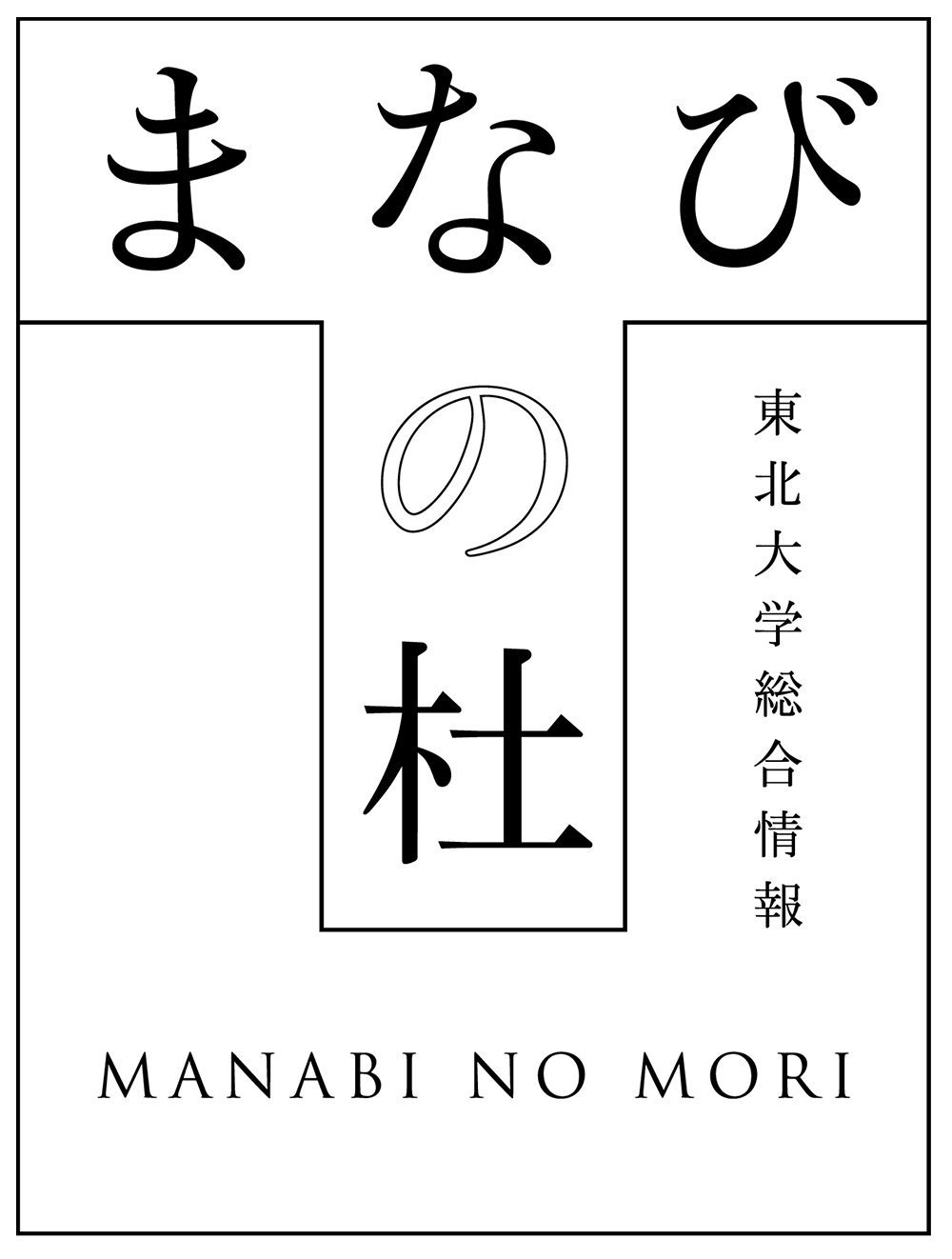#09研究者・田中耕一さんに聞く
学際融合がもたらすブレイクスルー
2025.02.03 更新
1988年に島津製作所が発売した「レーザーイオン化質量分析計(LAMS-50K)」は2024年5月、エレクトロニクス技術における重要な業績としてIEEE Milestone(アイトリプルイー マイルストーン)*に認定されました。これは、田中耕一さん(同社エグゼクティブ・リサーチ フェロー・田中耕一記念質量分析研究所所長)が2002年ノーベル化学賞を受賞した「ソフトレーザー脱離イオン化法(SLD)」を応用したもの。今回の認定を「ノーベル賞より意義深い」と語る田中さんにとって、その原点となる東北大学での学生時代はどのようなものだったのでしょうか。輝かしい業績を支えてきた信念も含め、京都の島津製作所でお伺いしました。
*IEEE Milestone/電気電子分野の国際学会であるIEEE(米国電気電子学会)が、開発から25年以上経過した重要な技術業績を表彰する活動。「東海道新幹線」や「QRコード」のほか、東北大学発の技術としては1924年に八木秀次、宇田新太郎の両教授が発明した「指向性短波アンテナ(八木・宇田アンテナ)」や、1977年に岩崎俊一名誉教授が発明した「垂直磁気記録」が認定されている。
株式会社島津製作所
エグゼクティブ・リサーチ フェロー・田中耕一記念質量分析研究所所長
田中 耕一
学生を温かく迎える街・仙台
ノーベル化学賞の受賞理由は、タンパク質などの巨大分子を壊さずにイオン化する「ソフトレーザー脱離イオン化法(SLD)」の開発でした。コバルトの粉末とグリセリンを混ぜ、直接レーザーを当てて、それまで不可能とされていたタンパク質など質量1万以上の生体高分子のイオン化に成功したのです。イオン化したタンパク質は飛行時間を計測することで質量を分析できます。この技術を取り入れた世界初の質量分析装置「レーザーイオン化質量分析計(LAMS-50K)」発売が発端となり、今ではMALDI-MSと総称される質量分析計が世界中に普及し、例えば臨床検査分野で微生物同定に広く用いられています。

今回のIEEE Milestone認定は私の発明だけでなく、チームとして取り組んだLAMS-50Kが総合的に評価されました。チームリーダーの吉田多見男さん、高分解能の質量分析器を開発した吉田佳一さん、高感度の検出器を開発した同期の井戸豊さん、その信号を記録する高速な電子回路の開発にあたった秋田智史さん、そして私。「五人衆」のチームプレーに光が当たったことは、ノーベル賞より意義深い。IEEEには東北大学のアンテナ工学の大先輩、八木先生と宇田先生が開発した八木・宇田アンテナも認定されています。その発明からちょうど100年というタイミングにも感慨を覚えます。
私は決して思いどおりの道をまっすぐ進んできたのではありません。むしろ希望とはことごとく違う道を歩んできました。「将来こうなりたい」と思った最初の記憶は小学生の頃。卒業文集に「電車の運転手になりたい」と書きました。今でも鉄道ファンのはしくれです。中学高校では理科が好きでしたので工学部をめざしました。
なぜ東北大だったか。それは富山で生まれ育った私にとって東京や大阪は大都市すぎてちょっと怖かったから(笑)。北海道は寒いし、九州は遠い。仙台はどうかなと、高校3年の夏に富山から電車に乗って東北大学まで行きました。それで、この街だったら暮らせそうだな、大学の雰囲気も自分に合っているなと思いました。同じ高校から東北大に二十数人が進学するという安心感もありました。住んでみると、仙台は全国から集まる学生を温かく迎え、学生を大事にしてくれる街だと肌で感じました。

世界をリードする研究者の教えを受けて
実は入学したばかりの頃は志望校に合格できた達成感に安住して、あまり勉強しませんでした。ドイツ語の単位を落として留年です。一念発起して勉強するようになったものの、3年生の終わり、研究室配属の段階でまたつまずきました。
当時の日本は半導体製造で世界のシェアの約半分を占めるほど勢いがありました。東北大には半導体や光通信の研究で世界をリードする西澤潤一先生もいらっしゃった。私も半導体の研究室に行きたかったけれど、研究室は当然高倍率です。あみだくじで負け、結果、アンテナ工学に進み安達三郎先生の研究室に入りました。
とはいえ、専門課程では勉強に身が入りました。なにせ目の前には雑誌やテレビで見たことのある、そうそうたる先生方がいらっしゃる。とりわけ岩崎俊一先生の授業は鮮明に覚えています。先生の「垂直磁気記録方式」はいまや世界の情報通信インフラを支えるハードディスク装置(HDD)のデータ記録技術ですが、ある日、その中枢をなすフェライトの薄膜を持って教室に来られた。エポキシ樹脂で固めた1㎜もない薄い板を手にして、「これを使った記録方式は世の中で必ず役に立つ。君たちが学んだことが社会に貢献するという一例だ」と私たちに語りかけました。それは東北大学の研究第一、実学重視の哲学そのもの。大学院に進学せずに就職することを「都落ち」とか「邪道」と言われていた時代ですが、こうした鮮烈な体験から私は企業の研究職を選びました。
しかし、就職活動は難航しました。家電メーカーを数社受けましたが不採用。がっくりきて安達先生に相談したら、「島津製作所はどうかな。選抜もさほど競争率が高くないようだし」と勧められました。面接試験では「医療機器の開発をしてみたい」と答えましたね。

偶然の発見から巨大分子の質量分析が可能に
島津製作所では試料にレーザーを当てて質量を分析するプロジェクトチームに配属されました。でも担当は化学。思ってもみない分野だけに葛藤しましたが、実験は好きでしたので、気を取り直してこつこつと取り組みました。
SLD発見の鍵はコバルト(金属)の粉末にグリセリンを混ぜたことにあります。理論的に導き出したのではなく、ひょんな間違いからでした。でも思いつきでレーザーを当て、測定器で測っていたら、タンパク質がまるごとイオン化する信号のようなものが見えたのです。2つの偶然が重なった。化学の専門家だったらタンパク質にレーザーを当ててイオン化させようなんて、はなから「できるわけがない」と考えるでしょう。レーザーは強いパワーを持つのだからタンパク質が壊れないわけがない、と。専門外の私はそんな常識に囚われなかった結果、波形が単なるノイズではないと確信しました。

しかし、このSLDを生かした質量分析装置LAMS-50Kは1台しか売れませんでした。1992年にはイギリスのクレイトスグループに出向して小型の後継機を開発し、1997年には再び渡英。さらなる後継機を手掛けて仕事に心からやりがいを感じ、さあ販売するぞと帰国したところでノーベル賞の騒動となりました。
応用分野が広がるとそれに関連する学術も広がります。さまざまな要望が私たちのところに舞い込み、質量分析装置も高性能化していくのです。技術と学術がコミュニケーションして、高め合いながらより高度なことが可能になっています。具体的には、体を構成するタンパク質などの質量分析が高度化するにつれ、体内のメカニズムの解明が進みます。臨床検査の時間が短縮されて体への負担を抑えつつ迅速に診断がつき、感染症であればさらなる感染リスクが抑えられる。どの抗生物質が適合するかもいち早く判断できるので、薬の投与も早まり、命を救うことができます。世界中の医療機器メーカーがしのぎを削る分野ですが、誰よりも早く取り掛かったという自負があります。
現在はMALDI-MS(マトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析法)をコア技術として、生体分子の構造解析手法や次世代質量分析システムの開発などに取り組んでいます。入社面接で「医療機器の開発をしてみたい」と言ってからだいぶ遠回りしましたね。
イノベーションは異分野融合から

たとえば、ビルの壁面から反射する不要な電波に着目した私の卒業論文とノーベル賞を受賞したSLDには共通点があります。学生時代は超高層ビルが建ち始め、テレビ局(もちろんアナログ放送です)のアンテナから発せられた電波がビルの壁にぶつかって跳ね返ることが課題となっていました。そこで、壁面に金属の棒を格子状に並べ、電波を吸収して跳ね返りを減少させるという研究に取り組みました。そしてその2年後にタンパク質の質量分析で大きな発見をしたわけです。前者は電気工学分野で金属の棒、後者は化学分野で金属(コバルト)の粉。分野の壁を超えた発想は、専門以外の道を歩んだ経験があったからこそ。専門家の場合は常識が邪魔をして起こせなかったブレイクスルーです。大きいと思われていた壁は意外と簡単に壊せた。門外漢だからこそ吹き込める風があるのです。
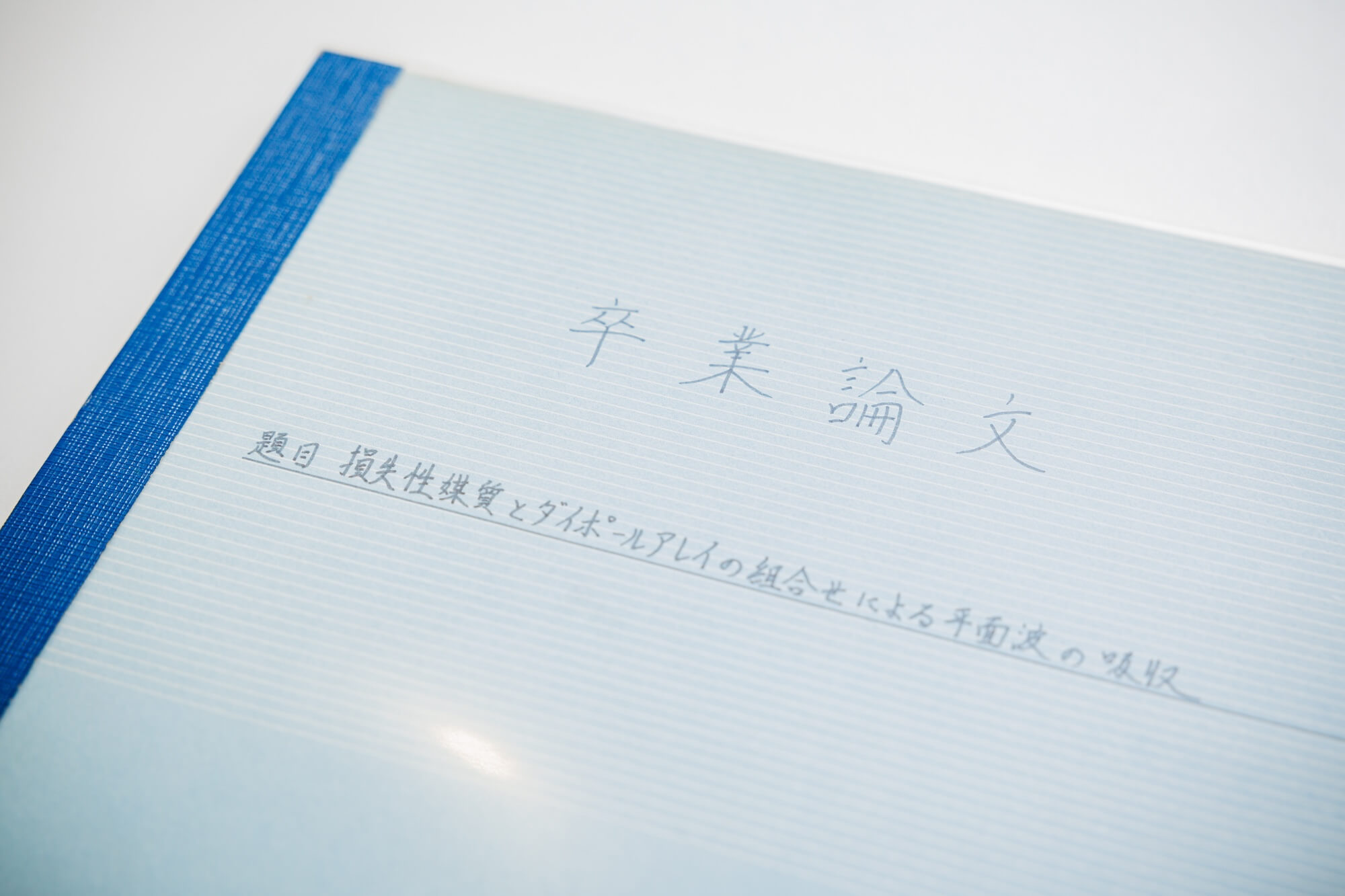

「イノベーション」という言葉は20世紀初めの経済学者シュンペーターの造語です。一般的に「技術革新」と訳されますが、本当の意味はもっと広い。新たな経済活動を生み出すために何かと何かを結びつけること、すなわち「異質なものを結合する」という意です。技術開発と新しい市場、制度、異分野を組み合わせた新しいエコシステムの創造もまさにイノベーションです。
漫画を思い浮かべてください。複雑な要素を模式図のように簡略化し、ストーリーをつなぎ合わせることは日本の文化として浸透しています。私の狭い研究分野に置き換えても、過去と現在の自分の知識を繋ぎ合わせ、「うまくいくかもしれない」と想像したことがイノベーションを生みました。もちろん脳内の融合だけではなく、自分の知識や発想とは異なる分野の人と話し合うこともアイデアの種になります。その点、もしかしたら専門が細分化された理工系よりも、文系の人の方がものごとを柔軟につなげる能力に長けているかもしれません。さらに重要なのは、自分の考えや意図を異なる文化を持つ人にも理解してもらえるよう説明する力です。私たちのチームでも毎月お互いの進捗を報告し合いました。私は口下手でしたから、どうしたら理解してもらえるか、いかにわかりやすく伝えられるか、常にコミュニケーションの訓練を重ねていたようなものです。これが結果的に世界的な技術開発を支えました。
どんな場所にいようと、道は必ず開かれる
東北大学は学際融合を積極的に進めています。農学部が青葉山キャンパスに移転して学部間の物理的な距離が縮まったことも可能性を予感させます。異分野の交流から生まれるブレイクスルーがあるでしょうし、ランチを食べているその隣で、買い物をするその横でなされている誰かと誰かの会話が発想の刺激になることもあり得ます。
仕事をする上では、個人的な趣味を生かす面白さも感じてきました。私はカメラ小僧だったんです。住宅地だった追廻(青葉区:現在の青葉山公園)に暮らした学生時代は、フィギュアスケート発祥の五色沼や広瀬川といった身近な場所を撮ったり、松島や山寺へといそいそと出かけてはシャッターを切ったりしていました。レンズやミラー、絞り、焦点距離への関心は、レーザー照射にも繋がっています。
こう話していると、追廻から青葉山キャンパスへと通った日々を思い出します。実験で帰りが真夜中になった日は、真っ暗な扇坂をてくてく歩いて下ったものです。冬は橋が通行止めになったり、車がスリップして事故を起こしていたり。あの寒さも含めて懐かしいですね。
学生時代を振り返って今思うのは、自分の希望通りの場にいなくても、迷いがあっても、道は閉ざされないということ。学んだことを活かせないか、発想の転換ができないかと可能性を探ることならいくらでもできるし、それこそが重要です。どんな経験でも決して無駄にはなりません。情報量という点でいえば、今は、私の学生時代とは比べ物にならないほど豊かな環境にあります。でも、あふれる情報に囚われ過ぎない方がいい。ブレイクスルーは自分の視線からそれたところにあるかもしれないと、ぜひ気付いてほしいのです。

PROFILE
田中 耕一 TANAKA Koichi

株式会社島津製作所エグゼクティブ・リサーチ フェロー・田中耕一記念質量分析研究所所長。
1959年、富山市生まれ。1978年、東北大学入学。工学部電気工学科でアンテナ工学を学ぶ。1983年、同大を卒業し、株式会社島津製作所に入社。技術研究本部中央研究所に配属。ソフトレーザー脱離イオン化法(SLD)の確立後、イギリスのクレイトスグループなどに出向を経て、2002年、ノーベル化学賞を受賞。2024年5月にはチームで開発した製品レーザーイオン化質量分析計(LAMS-50K)」がIEEE Milestoneに認定された。専門分野は、質量分析を用いた生体関連物質の構造解析手法等の研究。
取材・原稿/千葉 由香(荒蝦夷)
写真/齋藤 太一