
まず初めに自己紹介をお願いします
安達多元物質科学研究所に所属しております。研究テーマは大きく2つありまして、1つは今回のインタビューの研究テーマにもなっている高温融体の熱物性値の計測です。浮遊法を用いて、融けた状態の熱物性値を測定しています。非接触の浮遊法を用いて測定を行うと、るつぼとの反応がなく正しい物性値を測定できるという点を強みとして研究を行っています。もう1つは窒化アルミニウムという半導体の結晶成長です。金属融体から成長させるという方法で、高温融体に近いですが、その手法の開発に関する研究を行っています。
石原未来科学技術共同研究センターに所属しております。専門はもともと数値シミュレーションを活用したプロセス工学でした。材料を作るプロセス、例えば粒子や流体の混合、粉砕といった工程を解析し、より優れたものづくりのプロセスにする目的で、最適化や装置設計に数値解析を活用していく研究をしていました。2023年に異動し、現在はリンのリサイクルのプロジェクトに携わっています。ラボスケールの装置は既にありましたが、それをさらに大きくしていく業務に携わっています。数値解析を活かし、より大規模なプラント設計にすることに取り組んでいます。
阿部流体科学研究所に所属しております。研究テーマは大きく括ると数値シミュレーションになります。これを「応用」と「基礎」の2つに分けているのですが、「応用」は航空機設計に関する研究です。例えば、みなさんが乗るような大きな旅客機を対象に、数値シミュレーションを用いることで、壊れず、安全性の高い、優れた性能を持つ先進的な機体を実現すべく、航空重工のみなさんと一緒に協力しながら研究しています。
もう1つの「基礎」は、シミュレーションを活用するにあたり、その基盤となる技術の研究になります。元々私は数値流体力学、圧縮性流体が専門で、いわゆるCFD(Computational Fluid Dynamics)と呼ばれるコンピュータを用いた流体力学のシミュレーションの専門家でしたが、その計算手法や、それとは異なる物理分野、例えば構造力学や運動解析などと連携させるシミュレーション技術の研究を進めています。
齋藤情報科学研究科に所属しており、災害科学国際研究所も兼務させていただいております。専門を一言で説明するのが難しいのですが、心理学、認知科学、そして教育実践学を専門にしております。博士課程までのトレーニングでは人間の学び方や教え方に関する研究を行っていました。より効果的な方法を探るために、また効果的な方法のメカニズムを明らかにするために、眼球運動実験や教室実験(いわゆる準実験)などを行ってきました。就職をきっかけに、防災や災害に関する研究に取り組むようになりましたが、私のメインのフィールドは基本的に学校なので、いかに震災を伝承していくかとか、どう命を守るかの知識技能や、態度の育成について研究と実践に取り組んでいます。また、研究と実践のフィールドは、日本だけでなく、国外(例えば、インドネシア、トルコ)にも及びます。
アンサンブルプロジェクトを知ったきっかけは?
安達私は2016年にアンサンブルグラントに参加し、採択されているのですが、それは当時のアンサンブルプロジェクトワーキンググループメンバーの笘居先生からアナウンスいただき、ワークショップに参加したのがきっかけでした。
石原私も笘居先生がきっかけでした。笘居先生から、お誘いいただいてワークショップに何回か参加しました。
阿部私は2018年の秋に流体科学研究所に着任したのですが、その半年後に委員になり、当時の流体研のWG担当の早川先生から引き継ぎを受けました。
私は東北大学卒業ではなく周りに友人もいなかったので、最初は友達作りの意味合いが強かったです。「研究所間で、他の研究者と仲良くなれる」と聞いてはいましたが、まずは委員としてプロジェクトの運営に携わるところからのスタートでした。そのため最初の1年目は、自分が直接参加しているわけではなかったので、言い方は悪いですが「仲良しグループあるんだな」と外から眺めている状態でした。正直なところ、少し羨ましさも感じながら見ていた、というのが当時の心境でしたね。
この後の話になると思うんですが、石原さんとは学内関係者のバドミントンサークルをきっかけに知り合ったんです。
石原そうですね、最初に知り合ったのはバドミントンを通してでした。その後、アンサンブルプロジェクトのワークショップで初めて仕事をされている様子を拝見しました(笑)
安達さんとは研究所が同じなので、お互い存在は知っていました。アンサンブルプロジェクトの趣旨を考えた時に、「これなら一緒に研究できるのでは?」と思ったのが最初のきっかけだったと記憶しています。
齋藤僕の場合は、メールで案内が送られてきたのがきっかけでした。2022年に災害科学国際研究所に着任したのですが、当時は研究費が潤沢にあったわけではなかったため、応募させていただきました。そこからワークショップで阿部先生と知り合いました。
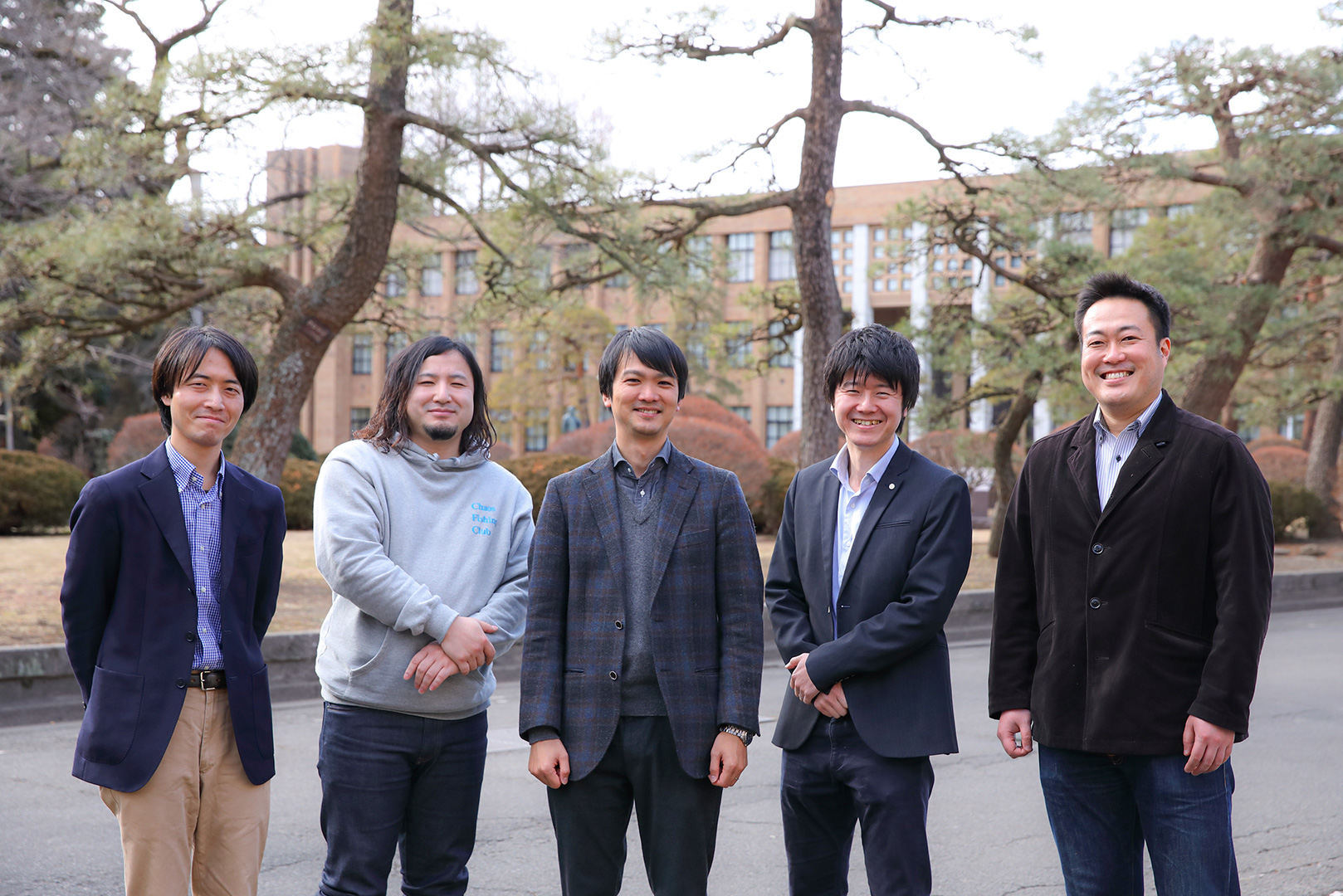
今回は2つのチームの皆さんにお集まりいただいておりますが、それぞれのチーム編成について教えてください
石原きっかけは私と安達さんが「面白そうだね」と話をしていたことでした。通常ならそこで話が終わるところでしたが、その場に阿部さんもいたんです。阿部さんは非常にエネルギッシュで、そのおかげで話が具体化し、今の形へとつながりました。リーダーも阿部さんで、その後科研費の申請などにもつながっていきますが、中心となって引っ張ってくれる人がいたからこそ、実現できたのではないかと思います。
阿部でも、最初に繋いでくださったのは石原さんでした。私も当時はシミュレーションが専門でしたし、石原さんも同じくシミュレーションをされて、安達さんは実験を中心にされていて。はっきりと記憶していないのですが、私は流体を研究していますと紹介させていただいて、安達先生はガスの流れの方でというお話をされて「面白そうですね」という話だったかと思います。
神田2020年度に採択された新規課題が「ガス浮遊融体のマルチフィジックス解析とその熱物性測定に向けた検討」ですが、テーマとしては安達先生の研究対象に対して石原先生と阿部先生の数値シミュレーションを融合させたという感じでしょうか。
安達そうですね。実験は実験なりに条件を与えて丁寧に進めますが、実験条件を詳細に設定することはやはり限界があります。実験だと再現が難しいこと、例えば、わざと平衡の位置から球の位置を動かして流体の挙動を確認するようなことは、実験ではそのような設定は困難ですが、そういった部分をシミュレーションで可視化して解析していただきました。私が調べたいことに対応いただいた形になります。
神田対象とする現象の数値シミュレーションは熱流動解析など色々な現象が含まれていると思いますが、阿部先生が流体、石原先生が化学の観点からアプローチされたのでしょうか。
阿部なんとなく最初から棲み分けができていて、私はどちらかというと気体の流れで、例えば圧縮性流体とか空気の流れの専門で、石原さんは溶融金属とか液滴の方ですね。表面張力なんかを専門にされていたんですが、今回の研究テーマのガス浮遊は両方の要素があって、例えば外側のガスの流れがどうなっているとか、安定に浮遊するにはどうすればいいのかという点はあんまり注目されて来なかったということをお聞きし、「それは面白いですね」と研究を始めたのが私の記憶です。
安達熱物性測定の観点から見て、私は浮遊液滴の変形に興味がありました。液滴が師乳から変形すると測定値が真値からずれていく可能性があります。そのずれを定量化できたり、補正式を立てることができれば、私の研究のニーズとしては非常に嬉しいことでした。
変形を評価するためには、流体が液滴の表面に及ぼす力がわからければならない、その表面に及ぼす力を用いて形状を推測しますので、それぞれの成果が互いの研究のニーズにうまくマッチしていました。
阿部人間カップリングですね(笑)
神田阿部先生、安達先生、石原先生のそれぞれの技術がないと成立しない研究ですね。
次に阿部先生と齋藤先生のチーム編成の経緯を教えてください。
阿部僕からの一方的なラブコールです。「ガス浮遊融体のマルチフィジックス解析とその熱物性測定に向けた検討」の成果を講演させていただいた時に齋藤先生のグラントの発表を聞いて、ラブコールを送りました。
齋藤心理学と認知科学では、人の心を対象にして、その状態を測定するので、そこの測定というところにピンときていただいたのかなと思います。
阿部僕は子どもの頃から飛行機が好きで、「かっこいい飛行機とは何だろう」とずっと考えていました。ただ、それを研究にするまでには至らず、何とかならないものかと漠然と思っていました。そんな中で齋藤先生の発表を聞き、「何か一緒にできないでしょうか」と相談したのが始まりでした。
齋藤心理学や認知科学の分野では、製品のユーザビリティや感性評価などを得意としていますので、「(たぶん)やれると思います。やりましょう。」と一緒に始めさせていただきました。
神田阿部先生と齋藤先生の研究は、運営側の立場で見ても非常に学際的で、まさに「若手アンサンブル」の趣旨のもとで生まれた研究テーマだと思っています。
共同研究の成果や進捗、展望を教えてください
阿部「ガス浮遊融体のマルチフィジックス解析とその熱物性測定に向けた検討」にいついては、現在も研究を継続中ですが、若手アンサンブルのグラントに応募してから約2年後に、科研費や財団に予算申請を申し込んだり、他のプロジェクトに応募できるようになりました。安達先生や石原先生の分野の科研費に僕が代表で申請しましたので、その分野の方からは「誰、お前?」という状態でしたが(笑)、無事採択されました。その後は石原さんが特許を1つ出願しましたし、また学会などでの発表も通じて、似たようなアプローチを試みている研究者がちょこちょこいるような感じを受けたんですが、全体の経緯を含めて取り組んでいたのは我々が先駆的だったのではないかと思います。
安達学会に参加すると、我々のグループ以外にも「ガス浮遊での物性測定」をテーマにした研究が増えてきています。フランスやアメリカのグループや日本のグループで研究結果が報告されています。今回のような成果のインパクトは強くなってきているので、頑張っていきたいですね。
神田先生たちは先駆的に取り組まれてきたんですね。
安達そうですね。計算の部分が他のチームと異なりますね。
阿部そうですね。他チームの先生から計算について質問されることもありますね。現在進行形ですごく面白いテーマでご相談いただいている話もありますので、早く進めましょう。
神田齋藤先生とのチームは今どのような状況ですか。
阿部当初は齋藤先生と2人で取り組んでいたんですが、その後私の知り合いのロボティクスの先生をお誘いしました。ロボットの分野では、機械工学よりも人間側に寄った視点があり、「かっこいい」や「美しい」といった要素も重視されます。もちろんガッツリ理工系の先生なんですが参加いただいて、流体研の公募共同研究の予算に応募して採択され、現在継続研究しているところです。
その後齋藤先生が名古屋大の高野先生をお誘いして4名で進めているところです。
齋藤高野先生は心理学者(特に実験心理学)ですが、生理指標の扱いにも明るい先生です。
阿部私は生体のノウハウについては専門ではないのですが、認知心理学系の先生に参加いただけて、去年科研費に応募させていただきました。まだ結果は出ていないのですが、良い提案ができているのではないかと思っています。
神田阿部先生の興味からスタートして、どんどん人が増えて、新たな大きい研究グループとして活動を始めたということですね。
齋藤ビューティー研究というような研究はありますが、「かっこいい」を突き詰めるテーマの研究は僕と阿部先生が調べた限りではほとんどないことが分かったので、新しいテーマで開拓を進めていきます。
若手アンサンブルプロジェクトに対する感想やご意見をお聞かせください
安達運営側からの視点になってしまいますが、グラントへの応募が増えるといいなと思っています。そのためにはグラント応募の敷居が高くならないことが重要ですし、申請書類に記載する量を減らしたのは正しかったと思います。手続きが煩雑だと応募をためらう人も多いため、できるだけ負担を軽減することが大切だと思いますね。
神田研究者をもっと若手アンサンブルの活動に引き込みたいですね。
安達引き込みたいですね。「こういう道もあるのか」と視野が広がり、関心を持つ人も多いと思います。そのような機会を設けつつ、研究の話もできる場があると理想的だと思います。
石原知り合いを作るという意味では非常にいいプロジェクトだと思います。特に着任したばかりの時は知り合いが少ないので、様々な人とお話をする中で異分野の研究にも触れられるのは、とても面白いことだと思います。自分の研究が別の分野でどのように活用できるかといった新たなアイデアを得られる点も非常に良いと思います。
グラントについては、資金を受け取る以上、成果を求められるのは当然ですが、なるべく成果に対するプレッシャーが少ない方が、のびのびと研究に取り組めると思います。もちろん、成果を出さなくてもいいと言っているわけではありませんが、私自身、この研究は趣味のような感覚で進めていたので、新しい試みにトライして、ダメでもそれでも良いじゃないという気持ちで、続けていけるグラントであって欲しいと思います。
阿部私は2018年から運営側でプロジェクトに参加してきて、コロナ禍での制限がある中でどう運営していくかというなど議論をたくさんしてきましたが、やっぱり共通して、敷居を下げてたくさんの人に参加してもらうという理念はあっていいのかなと思います。
実際のところ、最初の課題がランダムに決まるというのは大きな特徴ですよね。スクリーニングの仕組み自体が画期的だと感じており、そうしたアプローチが研究の進め方にも影響を与えていると思いますし、簡単に試せる運営は非常に良いと思います。研究所は、大学の専攻や研究科と比べると、どうしても個々の結束力が弱く、横のつながりがあまりないので異分野の先生方と知り合う機会が少ないと感じています。もちろん研究所同士で循環するのは良いことですが、そこに限らず、「アンサンブルプロジェクトが面白そうなことしている」と、専攻や研究科からも参加してもらえるようなそんな仕組みがあってもいいのかなっていうのをちょっと追加で思いました。
齋藤人文社会系の立場としてですが、人文社会系の先生方の参画をもっと盛り上げられればと思います。これが第一点で、それと付随して人文社会系の先生は単著文化が強くて、コラボして取り組むのになじみのない方もいるので、そこを突破できるような仕組みや仕掛けができると、きっと人文社会系の先生にとってもプラスになるし新しいフロンティアを切り開いていくきっかけづくりになるのかなって思っています。
安達先ほど石原さんから「趣味のような感覚で進めてられた」とありました。メインの研究では目先の成果に追われて忙しくて仕方がないということもあると思うんですけど、それとは別で「趣味のような研究」を持てるといいですよね。自分が好きで取り組んでいる研究でも、プレッシャーで辛くなることもあると思うので、それとは別の「趣味のような研究」を持っていると研究も楽しくなると思います。
石原最近は、自分の専門だけに偏るのはいいとは思っていなくて、専門を広げる意味で共同研究や、思い切って異動も含めて、別のところにチャレンジするのも自分にとって非常に良いと思います。他の若手のみなさんにも様々な分野に参加したり、自分の研究を広げていくことが次のステップに繋がっていくと感じているので、そういうことを自分も含めて挑戦していきたいなと思います。
阿部「趣味の研究」って、良い表現だと私も思います。いい加減に取り組むという意味ではなく、肩の力を抜いて、打算的になりすぎず、「来るもの拒まず」といった気持ちで、とりあえず参加してみることから生まれるものは意外に面白いことが多いと思います。異分野交流をしろと言われて自分の強みや弱みを強調してアピールするような会も、最近では少なくないように感じますね。でもそうやって無理に作られた共同研究より、アンサンブルでの研究は本当に楽しいと感じますし、そういう場を上手く若手アンサンブルは2つの課題に種類分けして参画しやすくしてくださっているので、ぜひ活用して欲しいです。
齋藤趣味のような、遊びのような共同研究で、集まってワイガヤできるところで、そしてそれがアウトプットに繋がればいいと思います。
今日の生成AI時代、AIも思いつかないようなテーマに繋がるのは、きっと個々人の自由な発想に基づく遊びや趣味なのかもしれません。そういったところを突き詰められればなとは思います。
また、さっき自分の専門に閉じずにというお話をしましたが、いま、学校教育では「見方・考え方(思考様式ともいえる)」をかなり重要視していて、小中高とずっとそういった学び方をしてきた子が、今後、大学生、大学院生となってきます。若手研究者も、それに負けまいと、その「見方・考え方」を多様に持つことを率先していければ、もっと世界がよりよくなっていくのかなとは思ったりもしています。



