助教

まず初めに自己紹介をおねがいします
椋平流体科学研究所に所属しており、専門は資源工学です。資源工学の中でも地震に関連する分野を研究しており、吉田さんと親しくさせていただいております。また資源工学という立場から、同じ環境科学研究科の宇野さんとも親しくさせていただいております。アンサンブルグラントは異なる分野の研究者との共同研究を目的としていますので、分野が異なる、地震学専門の吉田さん、地質学専門の宇野さんと一緒に研究しようということでこのメンバー構成になりました。
宇野環境科学研究科に所属しており、専門は地質学です。様々なフィールドに行き、過去に地震を起こしたと考えられる岩石を観察しています。地震は地震波を使って観測されますが、それが実際に地球の内部で、モノとしてどのような現象が起きているかを観察しています。
吉田理学研究科の地球物理学専攻の地震・噴火予知研究観測センターに所属しています。専門は地震学で、地震全般について研究していますが、その中でも特に内陸の地震発生において流体が大きな影響を与えていることが、かなり確度が上がってきているというところから、流体に非常に詳しい椋平先生と宇野先生と共同研究させていただいています。
アンサンブルプロジェクトを知ったきっかけ/チーム編成の経緯を教えてください
椋平もう完全に僕の悪ノリから始まりました(笑) 人工地震とか資源工学での地震についてアメリカでのポスドク時代に得た知見がありましたが、日本に帰国して資源の地震が少ない時に、じゃあ自然の地震にも使えるのではないかと思っていました。その際、吉田さんと調べてみるのも価値がありそうだねという話になり、じゃあ宇野さんも誘って、解釈のところで助けていただこうというところから始まりました。なので、基本的には僕の悪ノリにガチ勢を2人巻き込んでいるという感じです。特に吉田さんがずっとある地域の内陸でよく見られる群発地震っていう長期に続く能登での地震のような地震の研究をされていて、特にそのフィールドにデータを活用させてもらっています。近いところにそういった専門家がいてくれてとても良かったです。
神田椋平先生はどちらかというとフィールドというよりも実験やラボスケールに重点を置いている印象ですがいかがでしょうか。
椋平僕もフィールドでとってきた地震の情報を解析したりします。ただ僕のフィールドは地熱とかシェールガスとか人間が水を入れて資源をとるというようなフィールドで、吉田さんは本当の地震で、例えば能登で発生した地震などのような自然地震を対象にしていますので、フィールド感は僕の方がだいぶ小さく、浅くはあります。
神田そういった違いがあるのですね。宇野先生はどういった形でこの共同研究に参加されたのでしょうか。
椋平あるモデルを使って吉田さんのデータに適応した結果、流体がこれだけあったとか、定量的なことをさせてもらって、それを宇野さんに地質学的に解釈していただきました。
宇野地震で関与した水の量を椋平さんと吉田さんで求めたのに対して、バックグラウンドで、どの位の速度で流体が蓄積するかを地質学的な知見から計算していました。両者を比較して、「何年ぐらいかかったらこのぐらい水が貯まるね」というのを見積っていました。
椋平我々の資源工学のモデルは結構ざっくりしていて、本当にこれが、海のものなのか山のものなのか分からないので、ちゃんと地質学的な観点でそこそこリーズナブルなのか、また解釈可能なのか解釈不可能なのかを、まずあたりをつけてもらっています。そしてその先に色々考えたら金鉱脈とかもあります。
宇野そうですね、地質学的には水が流れると鉱物が沈殿するので、地震に関与した水の量から、金鉱床で見えているような鉱物脈がどのぐらいの量できるかが見積もれます。地質学の方は普段は金鉱脈とかを見てもどのぐらいの時間でできたか見積もるのが結構難しいのですが、それをリアルタイムで起きている地震学と結びつけることができました。
神田なるほど。やはり3人がいないと成り立たない研究だったのですね。
椋平間違いないですね。
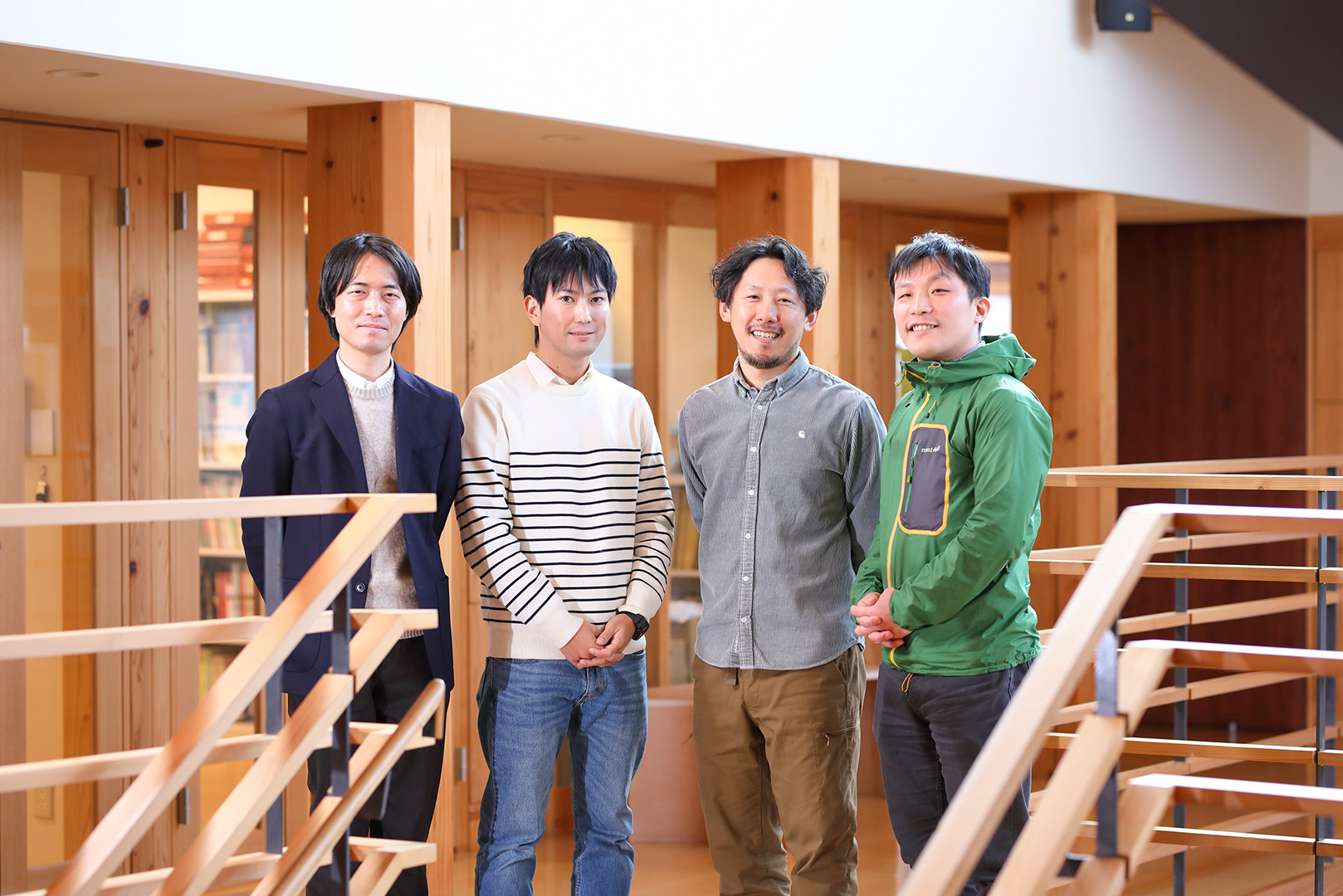
共同研究の成果や進捗を教えてください
椋平水の量を求められたということは、たぶん新しい成果かなと思います。
神田地震に関係する水の量ですね。
椋平はい、地震に関係する水の量です。批判もあったのですが、それでもデータとして値が出てきたというのは、たぶん面白いことだと思うので、学会などで発表しましたし、論文も書けました。「面白いね」と言ってくれた方もいましたので、そこで色々な議論が始まった事は、サイエンスとして価値があることだと思いました。まだ僕ができてないですけど、それこそ能登の地震とかでもやってみたりプレート境界でもやってみたり、他の手法と比べたりとか、そういうこともできるんじゃないかなとは思ってはいます。
吉田水っていうのは沈み込んだプレートという、かなり深いところの地殻にある大きなスケールからきた謎の流体なんですが、それはずっと地震学では存在すると思われていたんですが、実はそんなによく分かっていないんです。起源は海洋プレートで、地震が発生した領域と相当離れているんですが長いスケールで上がってきて、たぶん火山の下とか断層の下にあるのではないかと思われていたもので、それがM7の地震とか、そういうレベルのものにかなり影響を与えているんじゃないかと言われつつも、よく分からないでいるんです。力学的とか化学的にどう影響しているかっていうのが難しいんです。
そういった状況の中で、そもそも量も分からないということから、椋平さんは、あるモデルで、水の量を推定することに成功しました。宇野さんは沈み込んでいるスラブっていう、さっき言ったすごく離れているところからのモデルケースを結びつけたので、なかなか面白いポイントだと思います。
椋平沈み込んだ海の水が石の中に取り込まれて脱水反応が起きて、下に行ってもう1回脱水してマグマになるんですよね。
宇野そうです、マグマになってマグマが固結する時に水がまた分離して、それが火山の下に供給されて、さっき言っていた水になります。
椋平恐らく一般の人は知らない仕組みですよね。私も詳しく聞くまでは知りませんでした。そもそも水が石になるなんて、何で?という感じですよね(笑)
吉田それぞれちょっと分からないところがあっても、チームの中でお互いそれを補い合うことができます。
宇野確かにそう思いますよね。海底で水と石が反応して粘土鉱物という水を沢山含む鉱物ができるんです。粘土鉱物は結晶の中にOH基として水を取り込んで、それがプレートの年間10cmくらいの沈み込みによって地球の中に入っていって、地球の中はマントルで1400℃ぐらいあるので、だんだん沈み込むと熱くなって、OH基を含んだような粘土鉱物とか水を含む鉱物が分解して、それで水が発生します。
椋平それが流れると、
吉田地震が起こる。
宇野出てきた量も多く、10の6乗から10の8乗立方メートルとかっていう量なんですよね。それがだからだいたい10の6乗だと思うと100メートル立法ぐらいですよね。
神田想像がつかないですね。。。
宇野すごい量なんです。それが3.11の地震に誘発されたような地震なんですけど、8日後に発生しました。地下の中の石って全然空隙がないんですが、緻密な石の中にどうやって10の6乗立方メートルの水があって、それがたったの7日間で集まってきて地震を起こすっていうのに、また次の疑問を抱きました。じゃあその水はどこに貯留されていたんだろうとか、それがいきなり動き出すっていうのはどんなメカニズムだとか、次の研究に繋がるような疑問が出てきます。
神田当時のNatureの様な、インパクトは大きい雑誌に論文を出そうとされたと伺いましたが,そう思ったきっかけは何ですか?
椋平我々の業界の研究者や同い歳の研究者の方がどんどん出すので、何か僕も出したいと思い、宇野先生と吉田先生にご協力いただきました。
神田情報発信する際、どういった形で発信することがモチベーションアップになりますか?
吉田やっぱり論文が1番かなと思っています。
椋平うんうん。そして自動的に論文の前に学会がありますよね。その際「全く違う分野の3人でやりましたって」と、僕は言おうとはしています。そっちの方が面白いかなと。
宇野僕もやっぱり論文と学会発表かなと思います。この3人でやっているっていうのは業界的にも結構評価されているというのも、肌感覚として感じます。
吉田3人っていうのはちょうどいいと思います。あまり多いと一人一人の責任感が薄くなってしまったりしますので。3人とも専門分野が違っていたので、論文以外でも関係することで相談しやすい人ができたっていうのは大変よかったです。
宇野僕はこのプロジェクトについてはとても感謝しています。吉田さんのことは学生の頃から「凄い人がいる」って知っていたんですが、直接話したことが数回しかなくて、それをこのグラントをきっかけに椋平さんが結びつけてくれたので、とてもありがたいです。
椋平それ書いといてください(笑)
共同研究の今後の展望をお聞かせください
椋平皆さん独立して、哲学を持って専門を持って研究しているので、過度に干渉して共同研究を進めないというのが僕のポリシーです。なので、もし僕が「これすごいやりたい!」ってなった時に2人が同意してくれたらまた続けるし、そうじゃなかったらあえてそれを絶対やるということはないです。時と場合によってしなければならない研究は変わるので、それをまずは優先したいです。
吉田僕も、前回やったテーマをそのまま継続するかはまた別ですけども、何か学際的にといいますか、自分の分野だけでは処理できないことって結構地球科学であるので、それを相談したい時にまずこの2人を思い出しますね。そういうかたちで共同研究にできればと思います。
宇野このグラントの研究は地震の方から水を見るっていうのがメインなんですけど、一方で地質学の方からも流体を見て、その2つがどう合わさるかを見られたらいいなと思っています。そういう意味で地質学の方から水を見た時に、じゃあ地震学ではどう見えるかなという時に相談ができたらいいなと思っています。
神田若手アンサンブルプロジェクトがきっかけでできたグループがこれからも発展を続けるのはとてもワクワクしますね。
若手アンサンブルプロジェクトに対する感想やご意見をお聞かせください
椋平とても面白いプロジェクトだと思います。「まずは友達から」というテーマもとてもいいと思います。吉田さんのお話にもありましたが、「この人これやっていたな」とか「これ計測お願いできるかな」とか、「応用数学やっているな」とか「機械学習強いな」とか、知らない分野の人と知り合えるきっかけになるので、ぜひこのプロジェクトは残して欲しいで。また敷居も低いので、若手もどんどん参加してほしいです。
神田敷居が低いと共同研究を始めやすいですね。
椋平特に若手でお金ない人とかどんどん参加していけばいいと思います。もちろんお金だけでなく色々な分野の方と一緒にできる機会というのが大きいと思うので、是非活用してほしいです。
宇野私もあまり科研費がなかった時にアンサンブルグラントがあって若手としても助かった時もありましたし、色々な分野の方と一緒に研究できる機会があったので良かったと思います。
吉田僕自身は椋平さんが応募されるまでこのグラントのこと知らなかったんですけれども、あってすごくよかったので続けて欲しいと思います。
やっぱり異なる機関の東北大内でも、人と共同研究する時に何か拘束力があった方がいいと思うので、論文書くっていうのもありますけどちょっと頓挫するかもしれないので、何かプロジェクトが始まるっていうのは、しかも自分たちだけで完全には閉じないというのがすごく重要だと思うので、ぜひ続けてください。
宇野たぶんドクターをとってからの数年間は、自分のメソッドがある意味強みになって、それを突き詰めるフェーズがあると思いますが、その中で、自分のメソッドだけでなく、それが他の分野の人にどんなインプリケーションができるかを意識できると、すごく広がりが出ると思います。たぶん椋平さんもそういうことができそうな人に声をかけたのかなという気もしました。
椋平いや、そんな深く考えてなかったけど(笑)
神田宇野先生の突き詰められた専門と椋平先生の専門がミックスされて新しいものが生まれたと。
宇野そうですね。なので、そういう興味があるよっていうスタンスがあることが、コラボレーションを生み出すと思います。
吉田宇野さんが言われたように、ドクターとってからしばらく就職活動とかもありますし、自分がやってきたことを突き詰めたり、与えられた仕事をやるって感じになると思うんですが、今回のこの研究に参加して思ったのが、そういったこととは違って、遊び心があるというかそんなに鬼気迫ったものじゃなかったので参加すると良いと思います。学位とってすぐできるかは分かりませんけれども、ただそういった余裕を持って、他の分野の人と遊び心を持って研究するってなかなかできないとも思いますので、大事にして欲しいです。
椋平我々の仕事は、どこで楽しみを感じるかは人それぞれになってしまうと思うんですけど、全く専門が違う人と新しく何かを作り上げるって結構僕は好きなので、そういう楽しみ方も与えてくれる素晴らしい機会だと思いますので、若手研究者のみなさんも楽しんでくれたらいいなと思います。


